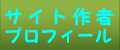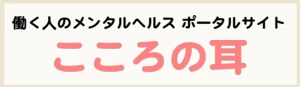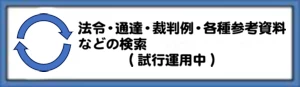労働安全衛生担当が知っておくべき法律学の基礎についてわかりやすく説明しています。
シリーズ第2回の本稿では、労働災害が発生したときの責任のうち刑事罰について取り上げます。
労働災害発生時に、安衛法及び刑法によって、誰がどのように処罰され得るのかを実態に即して解説します。
1 はじめに
執筆日時:
最終改訂:
事業場において、労働災害が発生した場合に事業者がどのような責任を負うかについて、よく5つの責任ということがいわれる。その5つの責任とは以下のようなものである。
- 1 民事責任:被災者、その遺族等に対して、民事損害賠償責任を負うことがある。
- 2 労災補償責任:労働基準法による公法上の責任。労働災害が発生すれば、ただちに責任を負う。
- 3 刑事責任:人的災害の発生により業務上過失致死傷罪、火災発生により業務上失火罪に問われることがある。
- 4 行政責任:行政上の措置(入札からの排除、助成措置・資格の停止など)、メリット労災保険料率の上昇など。
- 5 社会的責任:労働災害などを発生させたことで社会的な企業イメージが低下するなど。

私のサイトでは、このうち1から3について説明する予定だが、本稿ではこのうち3について説明する。

※ イメージ図(©photoAC)
なお、近年のネット社会においては、5の社会的責任についてもきわめて深刻なものとなりつつある。中央労働災害防止協会の「労働安全衛生への取組が取引に及ぼす影響についての調査研究報告書 要約版」(2011年)によると、「取引を発注する立場である場合に発注先に安全衛生への取組を求めることがあるとした事業場」は69.2%で、そのうちの79.2%はその理由として「発注先にも配慮することが企業の責任であるから」を挙げている。そして、災害が発生すると、報道機関のサイトに報道記事の記録が残っていつまでも企業名で検索したときにヒットするようになることがあるし、報道機関が削除したとしても様々なブログやSNSに引用されて拡散していることがあり得る。
現在、ある企業や個人が、他の企業と継続的な取引をしようとするとき、インターネットで検索してみることは常識となりつつある。そして、労働災害が発生した企業や労働災害がらみで訴訟になった企業については、取引に慎重になることはあり得よう。労働災害の発生は、企業の存続に深刻な影響をもたらすこともあり得るのである。
その一方で、労働災害の発生する恐れの少ない安全で快適な職場環境は、労働者のモラールの向上や、ひいては生産性の向上をもたらすこともあるだろう。このようなメリットは、数値で表しにくく実感しにくいものではあるが、内外の多くの報告がある(※)。
※ 例えば、欧州安全衛生機構「労働災害の社会経済的コストの明細」
2 罪とはなにか
刑事罰が科されるのは、「罪」を犯したときである。では「罪」とは何だろうか?
これについて、多くの方は「法律で禁止されていることをすることが罪だ」とお考えになると思う。すなわち刑法に「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する(刑法第199条)」と書いてあれば、「人を殺す」ことが罪になるということである。
だが、厳密にはこれは正しくない。例えば拘置所の刑務官が死刑囚に死刑を執行することは「人を殺す」ことではあるが罪にならないことは当然である。また、誰もいない暗い夜道で、若い女性にナイフを持った大男がいきなり襲い掛かってきたので、身を守るために近くにあった角材で殴りつけたところ相手が死亡したというような場合、仮にこの女性の側に相手を殺す意思があったとしてもおそらく罪にはならないだろう。また、13歳の少年が人を殺しても(道徳的にはともかく)刑法上の罪にはならないのである。
法律的な用語を使わせて頂くと、罪とは、以下の4つを満たす行為ということになる。
- ① 構成要件に該当する、
- ② 違法で、
- ③ 有責な、
- ④ 行為
この①から④について、詳しく説明しようとすると、それぞれ本を1冊書いても足りないくらいなので、ここでは労働安全衛生担当者に知っていて頂きたいことを、誤解を恐れず簡略にお示ししたいと思う。

※ イメージ図(©photoAC)
①の構成要件該当性とは、罪について定めたある条文に該当するということを意味する。ある化学物質について、ある条文で局所排気装置等の設置が定められている場合、局所排気装置等を設置しなければ、その条文に該当する。これが構成要件該当性である。
②の違法性とは、法律的な価値判断において「悪いこと」である。さきほどの例でいえば刑務官による死刑執行や、若い女性が大男を殺したことは、「悪いこと」だとはいえず、違法性がないので罪にならないのである。なお、前者を正当業務行為(刑法第35条)といい、後者を正当防衛(刑法第36条)という。
労働安全衛生担当者は、違法性についてはあまり気にする必要はない。ただ、「違法性」という言葉は、何かの条文に違反するという意味ではないので、そこのところだけ記憶しておいてほしい。
次に③である。有責性とは、その行為をした者を「非難」することができることである。さきほどの子供が人を殺した例では、13歳の子供がしたこととはいえ悪いことであることは間違いなく違法性はあるのだが、子供のしたことを非難することはできないので、有責性がなく罪には問えない(刑法第41条)ということになる。
有責性の判断で重要なのが、故意と過失である。故意・過失がなければ有責性はないことになる(刑法第38条)。なお、法的な話をすれば、故意と過失は構成要件該当性でも問題になる。どのような故意だったかで、該当条文が変わることがあるからである。しかし、労働安全衛生担当者の場合、そこまで気にする必要はない。故意と過失は有責性(責任)の要素であるとお考えいただければ十分だと思う。
なお、故意と過失については、労働安全衛生法違反と業務上過失致死の記述の中で説明する。
最後が「行為」であるが、これは「罪」の要件に含めないことが多いが、ここで説明することとする。行為とは、一言でいえば「意思に基づく身体の動静」である。ここに、「動」とはしてはならないことをすること(作為)であり、「静」とはしなければならないことをしないこと(不作為)である。
行為という言葉からは、なにかを「する」ことを思い浮かべるが、「しないこと」もまた行為であるということだけ覚えておいてほしい。例えば、ある化学物質を労働者に扱わせるときは局所排気装置等を設置しなければならないと法令に定めてあれば、これをしないことが不作為犯という犯罪になる。つまり「しない」ことがその罪の実行行為になるのである。
3 労働災害が発生したときの刑事責任
さて、労働災害が発生したときに関係者が処罰される可能性のある刑事責任にはどのようなものがあるだろうか。おそらく、多くの方は「労働安全衛生法違反」を思い浮かべることと思う。また、刑法の「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条)を思い浮かべる方もおられるかもしれない。
確かに、死亡災害などの重篤な労働災害が発生した場合、関係者が労働安全衛生法違反で起訴されることは多い。また、業務上過失致死傷罪で起訴されることは、労働安全衛生法違反に問われるケースほど多くはないが、これもかなりの件数がある。もちろん、両方の罪で起訴されることもある。
そこで、本稿ではこの2つの「罪」について解説を加えることとする。
(1)労働安全衛生法違反
ア どんなときに違反となるのか
実を言えば、法的な意味では「労働災害が発生したときに労働安全衛生法違反となる」という表現は正しくない。
労働安全衛生法(の大部分)は、事業者が実施すべき労働災害防止対策(安全配慮義務といってもよい)のうち、とくに災害発生のリスクが高いものについて具体的な内容をカタログ化して示し、その違反を罰則で防止しようとしたものと考えることができる。
つまり、災害を発生させたことによって犯罪となるのではなく、カタログに従わないこと(労働者を危険な状況においたこと)を処罰する法律なのである。
【ちょっと休憩】
では、労働安全衛生法違反はあったが、労働災害の危険性はなかったという場合はどうなるだろうか。例えば、労働者を1名だけ雇用している個人事業主が、その労働者が海外に滞在しているとき、外部から侵入できないような倉庫の中で無資格でフォークリフトを運転することは労働安全衛生法違反(安衛法第61条)に当たるだろうか?
考えてみれば、労働安全衛生法の目的(安衛法第1条)は労働災害の防止等であるから、その目的に沿って解釈すべきであり、労働災害が発生する恐れがないような行為についてまで、形式的には条文に該当するからといって、違反だとする必要はないのではないかとも思える。
確かに、労働者がいる会社で、たまたま全ての労働者が有給休暇をとっているような場合に、無資格の事業主がフォークリフトの運転をしたようなときは、労働災害発生の具体的な危険はないにせよ、たまたま労働者が来て事故にあうというような抽象的な危険はあるのだから、罪になると考えることはできるし、それが通説だといってよい。
だが、最初の例のように労働者が国内にいない場合は、抽象的な危険すらないといってよいだろう。しかし、労働安全衛生法違反は、抽象的危険がなくても成立するというのが、政府の見解である。もちろん、現実にはこのような行為が法違反として起訴されることはないだろうが、やはり違反には該当するのである。
少なくとも、「こんなことで労働災害が発生するわけがない」という理由で、労働安全衛生法に違反するようなことをするのは、避けた方がよさそうだ。
しかしながら、現実には「労働災害が発生したときに労働安全衛生法違反となる」と思っておられる方は多いと思う。
これは、実際に死亡災害など重篤な災害が発生したような場合には、ひとつには、監督官による調査が行われて、労働安全衛生法違反が発覚するということもあるだろう。しかし、それよりも、実際に災害が発生した場合には、①悪質なケースが多いこと、②社会的な問題を発生させたこと、③被害者の処罰意識も高いであろうことなどから、結果的に起訴に至ることが多いからである。なお、起訴するかしないかは、起訴便宜主義といい、刑事訴訟法では検察官の裁量にまかされている。
この点、同じような違反をしたにも拘らず、(たまたま)労働災害が発生したかどうかで処罰されるかしないかが決まるのは、公平の理念に反するとの批判があり得る。しかしながら、例えば人を殺そうとして殺人の実行行為を行ったが、結果として被害者が死亡しなかったという場合には殺人未遂となる。たまたま死亡すれば殺人罪の既遂になるわけで、結果によって「罪」そのものが異なることもあるのである。
重篤な結果が発生したか否かによって対応が異なるのは、とくに不公平というようなものではない。自ら行った違反行為によって結果が出た以上、それに責任を問われるのはむしろ当然のことといえるのである。
イ 労働安全衛生法における「故意」とは
さて、犯罪は、原則としてその罪を実行する意思がなければ成立しない(刑法第38条第1項)。過失犯は例外であり、過失犯の場合は各条文に過失犯を罰すると明記してある。労働安全衛生法の罰則は第12章にまとめてあるが、過失を罰するとはどこにも書かれていないので、故意がなければ成立しないことになる(故意犯)。
ここに、故意とは日常の言葉で言い換えると「わざと」ということになる。すなわち、ある化学物質について局所排気装置を設置するなどの措置をとることが労働安全衛生法によって義務付けられていたのに、「あえて」それをしなかったという場合である。
だが、ここで3つの疑問が出てくるかもしれない。
- ① そのような法令を知らなかったらどうなるのか。
- ② 自分の使用している化学物質が法令で義務付けられているものだと知らなかったらどうなるのか
- ③ ①及び②については知ってはいたが、局所排気装置を設置することが不可能だと思っていた場合にはどうなるのか
そこで、以下、これらについて解説してゆこう。
まず、①であるが、これは罪になると刑法に書かれている(刑法第38条第3項)。法律を知らなかったことを、法律用語で「法律の錯誤」といい、故意がないとはいえないのである。
もちろん、法改正の直後など法律を知らないことについてやむを得ないような事情があるときは、行政としても法律の周知を図ることを第一にし、仮に違反が発覚しても司法警察権の発動を差し控えるということはあり得る。ただし、その場合でも違反には違いはないし、重大な災害が発生した場合などには起訴されることはあり得る。
労働者を雇って事業活動を行う以上、法律を知らなかったでは済まされないのである。
次に②である。実は、これが意外に難しい問題なのである。
故意を法律的に説明すると、ある事実(労働安全衛生法違反になる事実)を「認識」し、「認容」していたということである。認識とはその事実を知っていたことであり、認容とはその事実を受け入れていたということである。
例えば、局所排気装置等を設置しなければならない規制対象物質(A物質)があるとしよう。ところがある事業者がA物質の入った洗浄剤を購入して、労働者に扱わせていたが、不注意のためにそれがA物質だったとは知らず、局所排気装置等を設置していなかったとしよう。すると、労働安全衛生法違反になるという「事実」を知らないのであるから、形の上では故意がなかったとして罪にならないということになるのである。
これは通常の感覚で考えると、明らかにおかしい。これでは、安全に無関心な事業者は労働安全衛生法違反に問えないということになりかねない。一方、その洗浄剤を使用している別な事業者は、作業環境管理は重要だと考えて、その物質の成分を調べたところ、A物質が含まれることが分かったとしよう。そして資金繰りが直ちにつかないため、3か月後に局所排気装置を設置することとしてメーカーに発注したとする。するとこの3か月間は違反行為を犯したということになる。ところが、作業環境管理などには全く無関心な先ほどの事業者は、その物質が何かを調べようともせず漫然と使っていたために、犯罪は成立しないということになってしまうのだ。
もっとも、実際にはSDSの提供を受けているだろうから、「知らなかった」では、捜査当局も簡単には納得しないだろう。また、仮にSDSの提供を受けていなかったとしても、洗浄剤を仕事で使っているような事業者が、「洗浄剤の中に有機溶剤が入っているとは思わなかった」などといっても誰も信用しないだろうとは思う。
ところで、規制対象であるA物質には「A’物質」という別名もあり、法令にはA物質と書かれているのだが、使っていた洗浄剤にはA’物質と書かれていたので、事業者はA’物質だと思っていたという場合はどうであろうか。この場合には故意に欠けることはないと判断されるだろう。なぜなら、法が規制をかけているA物質とA’物質は同じものであるから、法はまさにA’物質に規制をかけているわけである。従って「A’物質を用いていながら規制に従っていない」という認識はあるのだから、故意に欠けることはないからである。このことは、大審院判 大正13年4月25日(むささびもま事件)以来、確立した判例である。
やはり、何かの化学物質を用いる場合、それがどのような規制をうけるものであるかについては、最低限、調べなければならないということである。
ただその洗浄剤にB物質と書かれており、A物質とB物質は違う物質で、B物質には規制がかかっていないとしよう。そして事業者がこの物質はB物質だったと思い込んでいたとする。すると、この場合には、故意がないので犯罪は成立しないことになる。
最後に③である。この場合は特に故意に欠けることはない。確かに、講学上は「期待可能性」という理論があり、法律を守ることが期待できないような場合には無罪とすべきという考え方はある。
しかし、例えば、作業場所が地下にあって、建物の一部を壊さない限り局所排気装置をつけられず、建物所有者との関係でそれができないというような場合であったとしても、作業場所を移すことはできるであろう。そもそもそのような場所を作業場所に選ぶときに、法令のことまで考えておくべきだったとされる可能性が高い。また、局所排気装置を設置する費用を支出すると、銀行預金額が減少して手形が2度目の不渡りになるというような場合でも、同情の余地はあるにせよ、期待可能性がないとまではいえないだろう。
なお、最高裁は少なくともこれまでは期待可能性という理論を採用したことはない。大審院判 昭和8年11月21日(第五柏島丸事件)が期待可能性を認めた判決として例に挙げられることがあるが、最1小判 昭和33年7月10日(失業保険法違反事件)は、「(過去の判例は)判文中期待可能性の文字を使用したとしても、いまだ期待可能性の理論を肯定又は否定する判断を示したものとは認められない」としている。
ただ、検察官が、罪にはなるが起訴は猶予するという判断をすることはあり得ると思う。
ウ 誰が処罰されるのか
労働安全衛生法には、「両罰規定」(安衛法第122条)というものがあり、違反があった場合には実行行為者を罰するほか事業者も罰するとされている。
ここに、事業者とは、法人企業にあってはその法人、個人企業にあってはその個人をいう。つまり会社であればその会社、個人商店などであればその個人ということである。
なお、最大判昭和32年11月27日(入場税法違反被告事件)は、両罰規定は、従業員の違反行為に対して事業者の過失を推定するものだとしている。これは労働安全衛生法についての判断ではないが、労働安全衛生法の両罰規定についても同じことである(なお、雇用契約がない場合につき:東京高判昭和56年8月11日)。
つまり、会社が罰せられるだけではなく、従業員もまた罰せられることがあるということをまずご理解頂きたい。
だが、ここでの問題は、労働安全衛生法違反というのは、ほとんどが不作為犯だということである。作為犯の場合、その行為を行った者が実行行為者であることは明らかである。ところが、不作為犯の場合、その行為を行うべき者が実行行為者ということになる。しかし、現実には、会社のルールでは、その行為をしなければならないとされている担当者が決められていないということが普通である。決めてあれば、やっているであろう。そのため、誰が実行行為者であるかが問題となることが実に多いのである。
実行行為者(作為義務のある者)についての基本的な考え方は、作為義務は、法令(作業主任者、安全管理者等の義務)、契約(会社との個別契約/就業規則/業務命令)、条理等(慣行)によって発生する。というものである。なお、実行行為をさせる(作為犯の場合はさせない)義務のある者(上司や、場合によっては事業場のトップ)も処罰され得る。
作業環境管理など行ったことがないような事業場で、化学物質管理など自分の仕事ではないと思っていても、その職員の立場や権限等から、労働安全衛生法違反を問われることがあり得るのだということは理解しておいた方がよい。
(2)業務上過失致死傷罪
ア 業務上過失致死傷とは
次に業務上過失致死傷罪(刑法第211条)について考えよう。これは、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷」させる罪である。すなわち、この罪の内容は、①業務上において、②過失(業務上の過失)によって、③他人を死傷に至らしめること分けて考えることができる。
これを順に解説する。まず業務とは「社会生活上の地位をもって、反復継続して行われる行為であって、定型的・外形的に見て他人を死傷させる一定のおそれのある行為」ということができる。
業務といっても、別に仕事には限られない。レジャーのために運転をする行為も業務である。また、反復継続といっても、事故時までに反復継続されている必要はなく、反復継続して行うことが予定されていれば、1回目の行為でも業務になる。
さらに、定型的・外形的にみて危険な行為といっても、それほど危険なものでなくても該当する。現時点で該当しないものは、自転車で走行する行為や、家庭で調理をする行為くらいのものである。ただし、最近、自転車事故は多発しており、今後は該当すると判断されることはあり得る。
自動車の運転による交通事故は労働安全衛生担当者には関係ないと思われるかもしれない。しかし、心の健康問題で休業した労働者の職場復帰の可否の判断をするときには、その労働者が復帰した後で事故を起こすことも考えなければならず、まったく無関係というわけではない。
いずれにせよ、労働災害発生の可能性のある仕事が業務に該当することは間違いないと思っておいた方がよい。
次に②の業務上の過失である。過失とは日常の言葉で言えば「うっかりして」ということになる。法的には、過失の判断基準としては、判例実務などでは新過失論が用いられる。新過失論によれば過失とは、①結果(労働災害)の発生を予見すること(結果予見義務)、②予見した結果を回避すること(結果回避義務)の2つの義務を果たさなかったことである。従って、結果を予見することができることと、結果を回避することが可能なことが条件となる。
ただ、交通事故などは別にして、ほとんどの労働災害は、結果の発生が予見できれば、結果の回避は可能であろう。そして、結果(労働災害発生)の予見が可能かどうかは、問題となった危険性・有害性が事前に分かったかどうかによるといえよう。
ここで、この場合の過失は業務上の過失であるから、一般の者が予測し得ないようなことであっても、業務に従事している者であれば予測し得ることだと判断されれば過失があったとされるであろう。一般の者がSDSの内容を理解することができないからといって、化学物質を扱っている事業者が理解できませんでは通らないのである。
少なくとも、①労働安全衛生法等関係法令や通達を遵守せず、②リスクアセスメントを行えばリスクが判明し得たにもかかわらず、それを行わず(又は不適切に行って)、③SDSなどの公開された危険有害性情報を活用せず(又は誤読・誤解して)事故が発生した場合などには、過失があるとされると思われる。
【リスクアセスメントと過失】
リスクアセスメントを行う過程では、「シナリオ抽出」と「リスクの見積もり」が行われる。ここで、シナリオ抽出とは、その職場でどのような状況になると災害が発生するかを予測することである。すなわち、スイスチーズがどのように並ぶと穴が通じるかを考えるということである。一方、リスクの見積もりとは、言葉通り、結果の重大性と発生の可能性の大きさから、リスクの大きさを見積もることである。
リスクアセスメントの解説書をみると、「リスクの見積もり」についてはかなりのページを割いて論述してあるが、「シナリオ抽出」についてはほとんど記述してないものが多い。
しかし、事故が発生したときに過失があったといわれないためには、結果の発生を予見すること、すなわちシナリオ抽出が重要になるのである。
化学物質のリスクアセスメントにおいても、とくに爆発・火災の危険や、急性中毒については、このシナリオ抽出が重要になることを忘れないで頂きたい。
ところで、新過失説を前提にすると、例えば、有害性の知見のない化学物質を、有害性がないものとして労働者に取り扱わせたところ、そのときは判明していなかった有害性があり、結果的に災害が発生したとしよう。この場合、事業者は結果を予見することはできなかったわけだから、過失はなく、責任は問われないということだろうか?
確かに新過失論の考え方を徹底すると、そのように考えられる。事実、そのような趣旨の判例も多い。しかし、高松高判 昭和41年3月31日(ドライミルク事件)は、食品に化学物質が混入した事案(消費者被害)について、「新新過失論」(不安感説)を採用したといわれており、この考え方によれば過失が認められ得る。もっとも、他の多くの判例、例えば札幌高判 昭和51年3月18日(北大電気メス事件)などは、かなり明確に新新過失論を否定しており、現実には罪に問われる可能性は低い。
ただ、高松高判のいうところは、次のようなことである。すなわち、その化学物質によって発生した災害を科学的に予見することはできなかったにせよ、化学物質を摂取すれば、なにか問題が起きるという不安感は持つであろう。そのような不安感がある以上は、過失はあるというものである。確かに、科学的な証明はないにせよ、工業用の化学物質にばく露していればなんらかの健康被害を受ける恐れがあるのではないかという不安感は誰でも持つであろう。それにもかかわらず、ばく露防止措置をとらなかった結果、なんらかの健康被害が出たとすれば、過失を認定されても特に酷とはいえないようにも思える。
現実には、不安感説を否定し、新過失論を採用した上で、結果予見可能性をゆるく判断する判例(例えば大阪高判平成20年7月10日(明石砂浜陥没事件)(上告審:最1小判平成26年7月22日)など)もあり、これは新新過失論への接近ともいえよう。
罪になるかならないかに関わらず、危険有害性が判明していない化学物質の取り扱いには十分に慎重になるべきであろう。
なお、通常の事業者なら予測できたようなケースで、その事業者には予測できなかったという場合は、責任を問われることは当然である。
最後に、③の「致死傷」であるが、これは故意がなく死傷させてしまったということだと考えておけばよい。強盗致死罪などでは、故意があっても成立するが、労働安全衛生の世界でそこまで気にする必要はない。
ウ 誰が処罰されるのか
業務上過失致死傷罪の実行行為者も、不作為犯については、基本的に労働安全衛生法違反と同じだと考えてよい。作為犯の場合の考え方は、とくに問題はないだろう。
もちろん、業務上過失致死傷罪には「両罰規定」はない。
ただし、実行行為をさせた者(業務命令を出したもの)も従犯又は正犯として処罰され得る。労働安全衛生の担当者があまり詳細に立ち入る必要はないが、過失犯であっても意思に基づく「行為」というものはあり、直接の実行行為者と責任者との共同の行為だと判断されることはある。また、監督責任が問われることもある。現場の過失であっても、労働安全衛生担当者が責任を問われることもあり得るということは知っておいた方がよい。
(3)安衛法違反と業務上過失致死傷の罰の関係
最後に、いくつかの「罪」について、法定刑うち最も重いものの一覧を示しておく。これは、私がある研修会に使用するために作成して、一時、WEB上で公開していたものである。
労働基準法と労働安全衛生法については、通常の事業者に科されるもののうち、最も重いものを示している。
これをみると、労働基準法や労働安全衛生法が、立法者によって重罪であると考えられていることが分かると思う。誤って人を死なせる罪(過失致死)よりもかなり重いのである。また、業務上過失致死と比較しても、労働基準法違反の方が重いし、労働安全衛生法違反もそれほど軽いとはいえないのである。
※ 資料出所:柳川行雄「民事賠償請求訴訟からみたリスクアセスメント」より
最後に、この2つの「罪」が同時に成立する場合に、その罰がどのように課されるかを簡単に説明する。ここはそれほど重要ではないので、ざっと読み流してもよいし、難しければとばしてもよいと思う。
さて、この2つの「罪」同時に成立するのは、次の2つの場合が考えられる。
1 労働安全衛生法違反を犯しており、それによって災害が発生している場合。すなわち、被疑者のひとつの行為が労働安全衛生法違反となり、同時に業務上過失致死傷の行為にも該当する場合
2 労働安全衛生法違反が成立しているが、それによって災害が発生したとはいえない場合。すなわち、被疑者が労働安全衛生法違反と業務上過失致死傷という2つの行為を行っている場合
1については、観念的競合と呼ばれ、重い方の刑を科されることになる。2については単純併合罪と呼ばれ、双方の刑を科されることになる。ただし、拘禁刑などでは、重い方の刑期のうち長い方の1.5倍を超えることはないし、有期刑では30年を超えることもない。
なお、初犯の場合、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の場合には執行が猶予されることがある。
【関連コンテンツ】

法律理論の基礎(法律の種類と効果)
法令の種類と効果について、労働安全衛生の実務に沿って解説しています。

労働災害発生時の責任:民事賠償編
労働災害が発生したときの責任のうち民事賠償責任について、実務に沿って解説しています。

労働災害の損害を取り戻す方法
事業者が労災隠しをする場合、最初は労働者が労災隠しに協力してしまった架空の例を挙げて、労働者が損害を回復する方法について解説します。

ネットを利用した判例の探し方
労働関係の判例のネットを活用した探し方についてわかりやすく説明しています。