
※ イメージ図(©photoAC)
事業者が社内で労働安全衛生教育を行う場合、市販の DVD 等の動画を短時間放映することはよくあることです。近年では YouTube にも優れた動画があり、厚労省も「動画教材」を公開しています。これらを活用したいと思うことも多いでしょう。
社内の一般的な安全衛生教育において、既成の動画を用いることには何の問題もありませんし、むしろ奨励されることです。
事業者の中には、既成の動画を視聴することで法定の教育(※)を行うことが、法的に許されるかを気にされる方がおられます。法定の教育は、事業者の義務(ないし努力義務)で教育の科目、範囲、時間の他、講師の要件が通達等で定められていることも多く、その実施を既成の動画の視聴だけで完了としてよいのかについて疑問が感じられるかもしれませんね。
※ 例えば、特別教育(安衛法第 59 条第3項)、雇入れ時等の教育(安衛法第 59 条第1項)、職長教育(安衛法第 60 条)、能力向上教育(安衛法第 19 条の2)、危険有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育(安衛法第 60 条の2)など
結論を申し上げれば、動画の活用は法的に何の問題もありません。むしろ、市販の DVD 等の動画や YouTube の動画には、分かりやすく優れたものがあり、事業場の先輩や管理職が教育するよりも、既成の動画を活用する方が教育の効果が上がるのであれば、その方がよほど良いでしょう(※)。
※ 筆者個人は、安全衛生コンサルタントや、労働災害防止団体の安全管理士、認定産業医などの専門家が講師を務める講習を利用できるのであれば、既成の動画の視聴よりもはるかに良いと考えている。しかし、そのような専門家の講習を受けられる場合だけではないだろう。
事業場における法定の安全衛生教育を実施する場合に、既成の動画を用いることができることについて、法令や行政通達の記述を根拠に法的な観点から解説を行うとともに、それらをどのような場合に利用するのが効果的かについても解説します。
- 1 はじめに
- (1)法定の安全衛生教育の位置づけ
- (2)資格制度における既成の動画の使用の是非(参考)
- 2 事業者が行う安全衛生教育に既成の動画は使用できるか
- (1)特別教育
- (2)職長教育
- (3)雇入れ時等の教育
- (4)化学物質管理者講習
- (5)能力向上教育その他の実施が努力義務である教育
- (6)行政指導による教育(参考)
- 3 YouTube の動画を集合教育で使用する場合の留意点
- (1)著作権
- (2)コマーシャルが流れることの問題
- 4 最後に
- (1)安全衛生教育は他社任せでは効果は低い
- (2)動画を用いることの是非
1 はじめに
執筆日時:
最終改訂:
(1)法定の安全衛生教育の位置づけ
ア 法定の安全衛生教育と国家資格の基本的な違い

※ イメージ図(©photoAC)
本題に入る前に、労働安全衛生法(安衛法)に定められた各種の安全衛生教育の趣旨について、資格制度との違いを中心に簡単に解説しておこう。安全衛生教育の本旨は、あくまでもそれぞれの事業者が、自社における安全のための教育を行うということである。
すなわち、安全衛生教育は、たとえ安衛法に定められた各種の教育であっても、その事業場(ないし、対象となる個々の労働者が就く作業)における安全及び衛生に必要な教育を行う必要があり、かつ、それで足りるのである。全般的で汎用性のある内容の教育を行うことが求められているわけではない(※)。
※ また、特別教育は受講すればよく、試験があるわけではない。また、特別教育は誰でも行えるが、技能講習修了などの国家資格の付与は許された者にしか行えない。さらに、特別教育修了者に修了証を発行する必要はなく、3年間の記録の保存が義務付けられるのみであるなどの違いもある。
これに対し、技能講習や免許などの国家資格は、いったん取得すれば他の企業に移籍しても通用する。従って、汎用性のある知識等の習得が必要となるのである。また、実際に知識・技能が習得できたことを試験によって確認し、確認できなければ資格は付与されない。
この意味で、国家資格と安全衛生教育では、基本的な在り方が異なるのである。
【教育と資格の目的の違い】
- 安全衛生教育:その事業場において、対象となる労働者の安全衛生に必要な教育を行う。また、教育の成果を修了試験によって確認する必要はない。
- 各種の資格:他の企業に移植しても通用する汎用的な知識・技能を習得しなければ、資格は付与されない。また、知識・技能が習得できたことを修了試験によって確認される。
イ 特別教育が「国家資格」のように理解されている実態
もっとも、就業制限業務(安衛法第 61 条)と親和性のある特別教育(安衛法第 59 条第3項)については、国家資格のような扱いを受けてきたことも事実である。
例えば、最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転を行わせるには、予め特別教育を受けさせなければならない。一方、最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転は安衛法第 61 条により就業制限業務となっており、技能講習修了等の資格が必要なっている(※)。
※ このため、最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転の業務の特別教育は、就業制限業務(最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転の業務)と親和性があり、一般の事業者には特別教育が技能講習の下位資格のように感じられている。なお、本来は、特別教育はその事業場において必要なことだけを教えればよいので、そもそも考え方が異なることは先述した通りである。
そして、最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転の特別教育は、外部の教育機関で受けさせることが多く、受講すると教育機関は特別教育の修了証を発行することが多い。すると、この修了証を保有する者が他の企業に移籍しても、その事業者は安衛則第 37 条の規定により、特別教育を省略することができるのである(※)。
※ 昭和 48 年3月 19 日基発第 145 号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」が、特別教育の科目の省略が認められる者について、「当該業務に関連し上級の資格(免許又は技能講習修了)を有する者、他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者、当該業務に関し職業訓練を受けた者などがこれに該当する
」(下線強調引用者)としていることによる。
そのため、一度特別教育を受講しておくと、その後は会社を移動してもその業務に就くことができるのである。その結果、多くの事業者や労働者から、特別教育の受講が国家資格であるかのように思われて(誤解されて)いるのである(※)。
※ しかしながら、これは特別教育が外部の教育機関において全般的な内容で行われることが多いこと、技能講習は一度修了するとその効力は別な企業へ移籍しても有効であることとのバランスからきた妥協の結果なのである。本来は、特別教育はその事業場における固有のことについて教育すればよいという、安全衛生教育の本来の趣旨を考えれば、これは望ましいことではない。
(2)資格制度における既成の動画の使用の是非(参考)
ア 既成の動画の使用の是非

※ イメージ図(©photoAC)
さて、法定の教育を既成の動画で行えるのかという本題に入る前に、その参考として、資格制度(技能講習)における動画の使用についての考え方を解説しておこう。
技能講習において既成の動画を使用できるかについての行政解釈は、文書の形では示されていない。しかし、関係当局(厚生労働省安全衛生部安全課)は、原則として次のように考えている。
【技能講習(学科)における動画の使用の可否】
- 既成の動画を講義中にそのまま上映して、受講生にその視聴を求め、上映中は講師が講義を中断するようなことは短時間であっても許されない。
- 動画を受講生に見せながら、その動画の説明を講師が行うのであれば、動画はたんに補助教材として使用されているにすぎず、問題はない。
※ 筆者自身が口頭で、厚労省の担当者に確認した内容である。
※ なお、実技講習に関しては、実技の手順や要領を教えるために短時間 DVD などの動画を受講者に見せることは、実技講習の一部ととらえることができるので問題がないと考えられている。なお、技能講習の実技は、講師1人に対して受講者は 10 名(ガス溶接技能講習のみは 20 名)以内で行われる必要があるため、 DVD を受講者に見せる場合であっても必要数の講師が配置されている必要がある。
技能講習は、講師の要件が厳格に法定されており(安衛法第77条第2項第二号及び別表第二十)、技能講習規程で定められた時間は、法定の要件を満たす講師が講義を行わなければならない。このため、既成の動画を受講生に視聴させて、その間は講師が説明をしていないとすれば、その時間帯は法定の要件を満たす講師による講義ではないことになる。
従って、仮にその科目の開始時間から終了時間までの時間が、技能講習規程に定められた時間の通りだったとすると、その間に技能講習の要件を満たさない時間帯があるので、結果として技能講習規程に定められた講習の時間を満たさないものとなり、その技能講習全体が無効となってしまうのである。
一方、動画(例えば、フォークリフトの走行停止やクレーン業務の振れ止めの方法)を受講生に見せながら、その勘所を講師が説明しているのであれば、それは講師の説明の補助教材として動画を用いただけなので、技能講習の要件を満たしており、問題はないということになる。
要は、既成の動画が「主」となってはならなず、あくまでも講師の説明が「主」で既成の動画は「従」でなければならないということである。しかしながら、この考え方は、あくまでも技能講習という資格制度についてのことであって、法定の教育については全く考え方は異なるのである。
イ 登録教習機関が作成した動画の使用
もっとも、前項の考え方は、登録教習機関(技能講習等を実施する機関)が、自ら動画を作成してそれを受講生に視聴させることまで禁止される趣旨ではない。
コロナ禍による外出の自粛が要請されていた 2021 年(令和3年)に、厚労省は「eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施」についての解釈(※)を示している。
※ 基安安発 0125 第2号、基安労発 0125 第1号、基安化発 0125 第1号令和3年1月25日「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」
この通達は、後に2度に渡って改正され、2024年の改正で、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(令和6年4月4日基安計発 0404 第1号他。以下「eラーニング教育通達」という。)となっている。
この通達の別表の「eラーニングにより行われる雇入れ時等教育等の実施時に満たすべき要件」の中の、「使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者
」という列があることに留意して頂きたい。すなわち、eラーニングでは、(学科講習については)動画の視聴が許されることが前提となっているのである。
そこでは、技能講習の行を見ると、「講師については各技能講習規程に定める講師の要件を満たすことが確認できるとともに、動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できること
」とされているのである。役人特有の分かりにくい表現がされてはいるが、学科講習に関しては、動画に出演する講師が法定の要件を満たしていれば(動画作成者・監修者についても十分な知識又は経験を有することが確認できる必要はある)、動画を上映するだけで構わないというのである(※)。
※ ただし、受講生から質問があった場合には、ただちにそれに回答する必要があることから、上映中であっても法定の要件を満たす講師が、少なくとも1名は控えていなければならない。もっとも、動画に出演する講師と質問に答えるために控えていなければならない講師が同じ者である必要はない。
そうだとすれば、(少なくとも論理的には)この通達の要件を満たしてさえいれば、安全衛生教育動画を作成する専門業者が作成した動画(DVD 等)を購入して、それを上映すれば学科講習として認められるということになろう。
もっとも、質問に対応するために別な講師が1名必要となるので、技能講習の学科講習で専門業者による既成の動画の上映をしている登録教習機関は、現時点ではないようではある。また、技能講習の実施は、労働都道府県労働局長に登録した登録教習機関が実施しなければならないとされているのであり、既成の動画の上映のみで技能講習が完結するとすることは強い疑問がある。所轄の労働局が、窓口実務としてそれを容認するかどうかは別な問題だと考えるべきであろう。
2 事業者が行う安全衛生教育に既成の動画は使用できるか
(1)特別教育
ア 動画視聴の考え方
安衛法第 59 条第3項による特別教育を行う場合に、既成の動画(業者の作成した DVD 等の動画や YouTube 動画)を使用して行うことは可能であろうか。現実に、業者の作成した DVD 等の動画や YouTube 動画にも優れたものは多く、これを使いたいと考える企業は多い。
もちろん、これについては、次の2つに分けて考える必要がある。
【安全衛生教育における動画の使用】
- 特別教育のいずれかひとつの科目について、そのすべてを動画を放映することだけで実施したことにすること。
- 広義の大部分は講師が行うが、講義の途中で短時間の動画を流すこと。
特別教育については、その実施は法定の義務であり、科目・範囲・時間が「安全衛生特別教育規程」(昭和 47 年9月 30 日労働省告示第 92 号、最終改正:令和6年6月3日厚生労働省告示第 213 号)に定められたとおりに実施する必要がある。
しかし、学科教育を動画の放映とその視聴で行ってはならないとはされていない。従って、学科教育の中で短時間の動画を流すことは問題とはならない。問題となるのは、学科教育のすべてを動画の視聴で済ませてよいのかということである。
仮に、特別教育規程で定められた時間の全部または一部について、受講生に動画を視聴させて特別教育を終えたということで、対象業務に就かせたとしよう。その場合に、それでは特別教育として認められないということになると、安衛法違反ということになる。従って、そこは慎重に判断しなければならない。
イ 講師の要件
実は、雇入れ時教育、特別教育、及び、職長教育については、法令上は講師の要件は定められていない。また、特別教育規程にも、講師に関する規定はない。
しかし、通達(昭和47年9月18日基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」等)には、「講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者とすること
」という解釈が示されている。
行政当局としては、特別教育は社内で行うことが想定されているため、社内の詳しい職員が講師を務めればよいという考えで、講師の要件をあまり厳格に定めることを避けたのであろう。
ウ 動画の視聴による特別教育実施の可否
そして、先述したコロナ禍の中で出された「eラーニング教育通達」において、動画に出演する講師や動画の作成・監修者に十分な知識があれば、動画の放映によって特別教育を行うことも認められるとしているのである。
従って、理論的に考えれば、もし事業者がその動画が自社で行うべき特別教育の内容を満たすと判断して、事業者の責任において行うのであれば、専門業者が作成した既成の動画の上映のみで特別教育とすることも可能ということにならざるを得ない(※)。
※ しかも、eラーニング教育通達によれば、受講生の質問には教育後に解答すればよいので、講師が控えている必要もないのである。
そこにより良いものがあるのに、無理をしてまで自社の職員が教育を行う必要はないのである。
もっとも、安衛法第 59 条第3項は、事業者が特別の教育を行うことを求めている。そうであってみれば、第三者が作成した既成の動画の上映のみで特別教育を実施したとすることに、疑問を感じる事業者の方もおられるかもしれない。
エ どのような教育が望ましいのか
(ア)学科教育の在り方
筆者は、学科教育については、社外の教育機関(※)が行う教育(講義)で、その講師が労働安全衛生コンサルタント、労働災害防止団体の安全衛生管理士、認定産業医、オキュペーショナルハイジニストなどの専門家であることが確認できるのであれば、既成の動画を視聴するよりもよいと考えている。既成の動画を視聴させるより、そのような講習を受けさせる方がよほど良いのである。
※ 労働災害防止団体やコンサルタント会などの公的機関はいうまでもないが、意外にネットを活用する新参の企業において専門家を講師として優れた教育を提供していることもある。この辺は、利用する側が主体的に調べなければならない。
しかし、そのような教育機関が近くにないのであれば、専門家でない講師しかいない社外の教育機関を利用するよりも、むしろ専門業者の作成した動画を視聴する方がよいとも考えている。昭和の時代に生まれた世代には、リアルの講師でないと頭に入らないという意識があるかもしれない。しかし、生まれたときにはすでにネットが存在し、YouTube の動画の視聴に慣れた世代にとっては、かえって動画の視聴の方が頭に入るのである。
むしろ、「既成の動画の上映でも特別教育の効果は得られる」というのが常識になる時代が、すぐそこにきているのである(※)。
※ こう言っては何だが、外部の民間の教育機関は玉石混交である。講師が専門家であるすぐれた教育機関もあれば、その一方で講師が専門家ではないという例も多い。専門家でない場合、決して優秀な講師ばかりではないし、それどころか安全や衛生に関する基本的な知識に欠けていることさえ多いのである。一方、YouTube の動画は、多くのフォロワーや高評価がついた動画が優先的に表示される。すなわち、特に意識しなくてもトップクラスの動画を視聴することになるのである。
また、専門家ではない講師だと、体系立てて学んでいるわけではないため間違ったことを話すことが意外に多いのである。しかし、ネットの世界では、多くの視聴者がいる動画は、間違っているところがあればすぐに視聴者に指摘される。動画作成者としても、視聴者の信頼を得るために、指摘を受けると調べた上で即座に修正する。そのため、かえって間違いが少ないのである。講師が専門家でない限り、リアルの講師よりすぐれた動画はいくらでもあるのである。
(イ)実技教育の在り方
一方、実技教育については、筆者は、理想的な形は、学科は専門家の講義か既成の動画で受講し、実技は社内教育で行うというものだと思っている。
その理由の一つは、実技教育はその会社に固有のことを教える必要性が高いということである。フォークリフトや建設機械では、メーカによって操作方法が異なるし、クレーンの操作でもレバー式と無線式では操作の間隔が全く異なる。フォークリフトも教育機関で受ければカウンターバランス式で習うことが多いが、社内ではリーチフォークリフトを用いていると操作の感覚が全く異なる。
そのため、実技教育は、会社の設備を用いて行う方がより実戦に近い形で身に付くのである。ただし、OJTではなく、かならず Off-JTで法定の時間を教育する必要がある(※)。
※ なお、テールゲートリフターの特別教育については、通達(令和5年3月28日基発 0328 第5号)で納入業者が実機を用いて説明することを教育時間に含めることが許されている。
【納入業者による実技教育】
3 細部事項
(3)特別教育(安衛則第36条第5号の4及び規程第7条の4関係)
ウ 科目の省略
(ア)及び(イ)(略)
(ウ)テールゲートリフターの製造者、取付業者等による操作説明が、特別教育の対象である労働者に対して、テールゲートリフターの操作を実際に行わせながら適切に実施される場合には、当該説明に要した時間を実技教育の教育時間に含まれるものとして取り扱って差し支えないこと。
(エ)(略)
※ 厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」(令和5年3月28日基発 0328 第5号)より
そして、その理由のもう一つは、実技教育をその職員に行わせることで、教育をする側の職員が、もう一度、安全な教育について認識することができるからである。残念ながら、多くの職場で、リーチフォークリフトでリーチアウトしたまま荷を運んでいたり、テールゲートリフターに乗って人が昇降するということが行われていたりする。
実技教育に先立って、教育を行うためにという理由でもう一度、学科教育を受講させて教育に当たらせることで、社内の安全を再度徹底することが可能となる。現実には、外部の教育機関で教育受けた後輩が職場に戻ったときに、先輩が不安全行為を教えてしまうことがあることも実態である。しかし、先輩に安全教育を行わせることでそのような問題を解消できるのである。
(2)職長教育
次に、職長教育(安衛法第 60 条)についてはどうであろうか。
職長教育については、教育すべき事項(科目)と教育するべき時間が、安衛則第 40 条第2項に法定されている(※)。
※ なお、建設業の場合は、平成 12 年3月 28 日基発第 179 号(最終改正:平成 18 年5月 12 日基発第 0512004 号)「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」に留意されたい。
そして、特別教育の項で述べたように、講師の要件については、通達(昭和47年9月18日基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」等)により、「講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者とすること
」とされている。
また、先述したコロナ禍の中で出された「eラーニング教育通達」において、(特別教育と同様に)動画に出演する講師や動画の作成・監修者に十分な知識があれば、動画の放映は認められるとしているのである。
しかし、職長教育は特別教育よりも、その事業場における固有の知識(合図、作業標準などの考え方)の習得がより必要となる教育である。
であれば、特別教育と同様に、職長教育についても、社内の独自事項については、社内での教育を行うことが望ましい。一方、一般的な事項については専門家による講義を受けることが最も望ましいが、そうでなければ(その動画が上記の要件を満たすのであれば)第三者が作成した既成の動画の視聴を行うことには問題はない。
(3)雇入れ時等の教育
一方、雇入れ時等の教育(安衛法第 59 条第1項)については、教育事項及び内容は定められているものの、そもそも教育を行う時間が定められていない(※)。
※ 雇入れ時の教育に必要な時間は、その事業場の業種や本人の職務内容によって大きく異なるため、一律に定めることができなかったのである。
ただし、特別教育の項で述べたように、講師の要件は通達(昭和47年9月18日基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」等)により、「講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者とすること
」とされている。
従って、社内でこの要件を満たす講師が十分な時間をかけて教育を行う必要はあるが、一般的な事項について、外部専門家による講義を受けたり、DVD 等の動画や YouTube の動画を用いることには安衛法上の問題はない。
(4)化学物質管理者講習
ア カリキュラム等
(ア)リスクアセスメント対象物を製造している事業場
化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造(※)している事業場においては、安衛則第 12 条の5第3項第二号イにより、一定の講習を修了した者でなければならないと定められている。
※ ここに「製造」の意味については、当サイトの「安衛法にいう「化学物質の製造」とは」を参照して頂きたい。
そして、その講習のカリキュラムは「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」(令和4年9月7日厚生労働省告示第 276 号)に定められている。
また、その詳細は「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(令和4年9月7日基発 0907 第1号)に定められている。
(イ)リスクアセスメント対象物を製造していない事業場
なお、リスクアセスメント対象物を製造していない事業場においては、安衛則第 12 条の5第3項第二号ロにより、化学物質管理者として管理するべき事項(同規則第 12 条の5第1項各号)を担当するために必要な能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任すればよいとされており、法的には特別な資格や講習の受講は必要とはされていない。
しかしながら、その場合であっても「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(令和4年9月7日基発 0907 第1号)によって、化学物質管理者講習に準ずる講習を受講することが望ましいとされている。なお、その科目、範囲、時間等は、同通達の別表「リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場における化学物質管理者講習に準ずる講習」に定められている。
イ 政府による教育動画の開発と公開
この講習については、厚労省が上記のカリキュラムに基づいて作成した「講義動画」及びテキストを公開している。
ただし、この動画には「受講者が単独で本動画の視聴では、上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんので、ご留意ください」という注記がある。だとすれば、受講者を事業場内の会議室等に集合させて、この動画を視聴させるのであれば、化学物質管理者講習を修了したとしてよいということである。
このような動画を国が公開している理由は、現実に化学物質管理者講習を実施できる機関が、中央労働災害防止協会、日本労働安全衛生コンサルタント会、日本作業環境測定協会などの専門機関を除けばほとんど存在していないことである(※)。もちろん、それらの教育を受けられるのであれば、それが最も理想的である。
※ 現実に、化学物質管理者講習会を行っている民間機関もあるが、玉石混交であり、講師自信が化学物質管理についてほとんど理解していないようなケースさえ散見されるのが実態である。
民間機関の化学物質管理者講習会を利用するのであれば、講師が労働衛生コンサルタントやオキュペィショナルハイジニストなどの専門家であることは予め確認した方がよい。
現実問題として、厚労省の動画はきわめて完成度が高く、内容も充実しており、民間機関の一部が実施している化学物質管理者講習(と称するもの)とは比較にならないほど役に立つ。
この動画は、厚労省が作成しているということもあり、「単独で本動画の視聴」をすることのみでは受講したことにならないと明記されているので、集合教育の形でこの動画を上映することにより教育の実施とすることは可能と考えられよう(※)。
※ 繰り返すが、専門家による教育を受けられるのであれば、その方が好ましいことは言うまでもない。
ウ 他の教育への影響

※ イメージ図(©photoAC)
また、それであれば教育はすべて、ネットを通した動画の視聴で良いではないかということになろう。また、受講者からの質問に対する回答は、将来的には生成 AI でよい(※)ということになるだろう。
※ ただし、現時点ではハルシネーション(誤り)の割合が高すぎるので使用は難しいだろう。もっとも、生成 AI の改良は急速に進んでおり、リアルの講師よりも信頼できるという時代も目の前に来ているのかもしれない。
いずれにせよ、そう遠くない将来に、そのような議論が起きることは間違いのないところであろう。ある意味で、今後の安全衛生教育の在り方を示唆しているというべきなのかもしれない。
もっとも、私自身は、専門家による教育を受けられるなら、動画の視聴よりもはるかに良いと考えている。しかし専門家の数は足りず、それができるとは限らないのである。なお、動画受講とリアルの講師の、それぞれのメリット、デメリットについての議論は、本コンテンツの範囲外のことであるので、ここでの詳述は避ける。
(5)能力向上教育その他の実施が努力義務である教育
また、安衛法には、努力義務とされる教育についての定めがある。例えば、能力向上教育(安衛法第 19 条の2)、危険有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育(安衛法第 60 条の2)、健康教育等(安衛法第 69 条)などである。
このうち、能力向上教育については、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(平成元年5月 22 日能力向上教育指針公示第1号)により、また危険有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育については「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)により、実施すべき科目、範囲及び時間がそれぞれ定められている。
また、能力向上教育、危険有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育のいずれについても、教育の方法については、これらの告示によって「講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする」とあり、講師については「当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする」とされている(※)。
※ なお、実施される教育ごとに通達(例えば、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育については、平成5年6月11日付け基発第 366 号「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育について」など)が発出されており、より詳細な講師の要件が定められている。
一方、これらの教育において、具体的に何を教えるのが、最も効果的なについては、各企業の状況によって異なるであろう。
従って、教育の全体に渡って既成の動画を用いることは、現時点では望ましくない(努力義務を果たしたことにならない)(※)だろう。しかし、企業固有のことではない一般的な内容については、既成の動画を視聴させたとしても、とくに問題となるようなことはないものと考えられる。
※ そうでなければ、講師の要件(一定の研修を受講した者、労働安全コンサルタント等)を通達で定めている意味がない。
(6)行政指導による教育(参考)
安衛法では、行政指導その他による安全衛生教育の種類は実に多い。いくつかの例を挙げると「フィットテスト実施者に対する教育」「熱中症予防管理者労働衛生教育」「情報機器作業に係る労働衛生教育」「騒音障害防止管理者教育」「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」などがある。
これらはいずれもカリキュラム(科目(事項)、範囲、時間)についての基準や講師の要件が通達中に示されている。
しかしながら、(そもそも行政指導によるものということもあるが)本来、これらの教育で何を教えるか、また、教材として何を使用するかについては、各事業場における状況等に応じて、事業者がある程度、修正することが可能と考えるべきであろう。
行政が定めているからという理由で、必要のないことを教える必要はないし、またその事業場固有の必要な事項を漏らすべきではないのである。
また、教育の中で、一般的な内容について、既成の動画を用いることは、その動画がその事業場における教育として効果的なものであれば差し支えないであろう。しかし、既成の動画のみで教育が完了したと考えるべきではない(※)と思える。
※ もちろん、法違反になるわけではないが、たんに動画を上映するだけでは、事業場側の安全に関する意識が向上しない。また、既成の動画は、一般的、抽象的な内容になりやすく、その事業場に固有の安全衛生に関する知識の付与は困難なのである。
ここでも繰り返すが、最も望ましいことは、あくまでも一般的な事項は専門家によるリアルでの教育を受け、その企業に固有のことはその企業において教育を行うことである。しかし、それができないのであれば次善の策として、一般的な事項については既成の動画を視聴し、その企業に固有のことは社内で教育を行うということも考えられよう。
3 YouTube の動画を集合教育で使用する場合の留意点
(1)著作権等
ア YouTube と著作権等
ただし、YouTube の動画を集合教育等で使用することの権利関係(著作権)の問題は、ここまでの議論とは全く別な問題である。YouTube の動画を使用するのであれば、次の3点に留意しなければならない。
【YouTube の動画を集合教育等で使用することの留意点】
- 投稿者の著作権を侵害しないこと。
- Google の利用規約に反しないこと。
- 使用する動画が他者の権利を侵害していないこと。
ここで、YouTube の動画を集合教育等で使用することについて、動画の投稿者に対する著作権侵害の問題と Google の利用規約に違反しないかどうかは別な問題であることに留意しなければならない。
イ 投降者の著作権
現時点では、YouTube の動画を集合教育等で上映することが、著者(動画制作者)の権利を侵害しているかどうかについての判例はない。
厚生労働省が作成した動画は別として、個人や企業がアップした動画を利用するのであれば、著者に問い合わせて、許可を得ておくべきであろう。
ウ YouTube の利用規約
また、動画の著者の許可を得たとしても、それは YouTube の利用規約に違反しないということを意味しない。動画を集合教育等で上映することについて、Google の利用規約は次のようにしている。このため、動画を(有料であるか無料であるかを問わず)集合教育等で上映することは、Google の利用規約に違反するおそれがあるとする専門家は多い。
9 本サービスを個人的、非営利的な用途以外でコンテンツを視聴するために利用すること(たとえば、不特定または多数の人のために、本サービスの動画を上映したり、音楽をストリーミングしたりすることはできません)。
Google「利用規約」
とりわけ、その動画のバックグラウンドに、著作権で保護された音楽が流れている場合には、権利者の許可を得ない限り使用は避けた方が無難である。
なお、現時点では、YouTube の動画をローカルディスク等に保存することは認められていないので、上映するのであれば(著作者から譲り受けるか)ネットにつながる環境で YouTube のサイトをブラウザで表示して直接上映する必要がある。
エ 投稿された動画そのものの著作権
さらに、使用する YouTube の動画そのものが著作権に違反していないことも、利用する者の責任において確認する必要がある。Google は YouTube に投稿されたすべての動画が著作権法に違反していないなどと保証してはいないのである。オリジナルの動画を作成しているチャンネルのものを使用するべきである。
(2)コマーシャルが流れることの問題
なお、YouTube の動画には、無償のアカウントで使用する場合は、一定間隔でコマーシャル動画が流れることは当然である。この時間は教育の時間に入らないので、その時間は講義時間を延長するか、YouTube Premium としてコマーシャル動画が流れないようにしておく必要がある。
4 最後に
(1)安全衛生教育は他社任せでは効果は低い
ア 外部の教育機関の教育に頼ることの問題

※ イメージ図(©photoAC)
安衛法で義務付けられている特別教育や雇入れ時等の教育等について、外部の教育機関の実施する研修へ参加させることだけで終わらせることは、あまり好ましいことではないと筆者は考えている。
外部の教育機関の教育は、どうしても一般的で抽象的なものになりやすい。もちろん、それはそれで意味はあるのだが、自社に固有のことについては、別途、OJT でも構わないので必ず自社で独自に教育する必要がある。
例えば、外部の教育機関の教育では、有害な化学物質には保護具を使用しなければならないことは教えられる。しかし、自社の特定の製造工程で用いる特定の化学物質について、それを扱うときはどの保護具を用いて、その保護具をどのように管理するかまでは外部の機関では教えられないのである。
また、建設機械やフォークリフトなど、それぞれのメーカーによって操作方法が異なっていたりする。従って、外部の教育機関で操作方法を習ったからと言って、自社の機械が扱えるとは限らないのである。それらの自社に固有の事情は、必ず自社における教育で教える必要がある。
そして、その場合も一般的な内容については、労働安全コンサルタントなどの専門家による教育を社内で行うか、専門家が講師を務める外部の教育機関の実施する研修に参加させたることが望ましい。そして、それができないのであれば、専門業者の提供する動画の視聴の方が効果的ではないかと筆者は考えている。
イ 自ら教育を実施することの効果
もっとも望ましいことは、安全衛生教育を社外の教育機関まかせにするのではなく、社内で企画・立案して社内で実施することである。そうすることで、講師や関係者が自ら学習することになり、社内の安全衛生の意識・レベルがアップしてゆくからである。安全衛生教育を行うということは、自らの安全衛生に関する知識を高め、かつ意識を高めることにもなるのである。
もちろん、社内で講師が確保できないときは、外部の安全衛生コンサルタントなどに講師を直接依頼する方法も有効である。そのような場合は、講師を社内のみで確保しようとはしない方がよい。
どのような教育を行うべきかについて、事前に講師と情報交換することにより、また、その教育の場に立ち会うことにより、外部の教育機関まかせにするよりも、自社の安全衛生のレベルを大きく向上させることができる。
(2)動画を用いることのメリット・デメリット
安全衛生教育を社内で行う場合であっても、既成の動画を使いたいという要望は強い。ときには、民間の教育機関にさえ、既成の動画を使用したいという要望は根強く存在しているのが実態である。
現実に、一般的な内容についての教育は、講師が行うよりも動画の方がよく分かるということは、現実にはよくあることである。一般企業の職員が社内教育の講師になろうとしても、安全衛生についての知識が十分ではなかったり、インストラクションの技術が弱いことはやむを得ない面がある。
また、社外の教育機関で専門家による教育を受けられるならそれに越したことはないが、残念ながら、民間の教育機関の専門家でない講師には、安全衛生に関する基本的な知識に欠けていることが少なくないのが実態なのである。
そのため、安全衛生の専門家が監修し、動画のプロが製作した既成の動画の方が、講師が説明するよりも、分かりやすくしかも間違いがないという実態があるのである。
そうした現状がある以上、安全衛生教育において既成の動画を視聴するということがむしろ効果的であるという場合もあり得よう。
時代は変わりつつあるのである。
なお、ここで特別教育を題材に、どのような教育が望ましいのかを一覧表としてみた。ただし、これは社内に安全衛生の専門家がいない中小規模事業場を念頭に置いている。社内に安全衛生の専門家が確保できるのであれば、社内の社員が教育を行うことが最も望ましいことは言うまでもない。
【どのような教育が望ましいのか】
| 種類 | 最も望ましいもの | 次に望ましいもの | その次に望ましいもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|---|---|
| 学科教育 | 安全又は衛生の専門家を講師とする内部又は外部の教育の受講 | 専門家が作成又は監修した既成の動画の視聴 | 安全又は衛生に詳しい社内の職員による内部教育 | 専門家ではない者が講師をする外部教育の受講 |
| 実技教育 | 安全又は衛生に詳しい社内の職員による内部教育 | 外部の専門家を招聘しての内部教育 | 専門家を講師とする外部教育の受講 | 専門家ではない者が講師をする外部教育の受講 |
また、当然のことであるが、教育を行う機関の「権威」とその機関が行う教育の講師が専門家かどうかとは、(完全には)一致しない。外部教育機関は「権威」ではなく「実質」で選ぶべきである。
【関連コンテンツ】
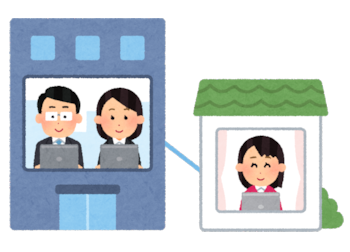
ネットを活用した安全衛生教育
厚生労働省によるリモートによる安全衛生教育についての通達により、何が可能か、またそのメリットや、これによって何が起き得るのかを論じています。

技能講習・特別教育等の講師要件
技能講習等の資格制度の講習等や、特別教育等の安全衛生教育の講師になるための条件をまとめました。
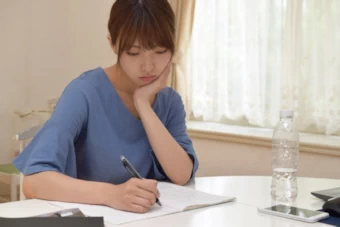
化学物質関連の作業主任者制度の行方
化学物質関連の作業主任者制度は廃止されるのでしょうか。厚労省の担当部局に問い合わせた結果などを踏まえ、その疑問に現時点で分かっていることを整理します。

安全衛生教育で大切なこと
労働安全衛生教育の講師を行うとき、どのように話すべきかを解説します。

化学物質管理者講習の効果的活用
化学物質管理者の養成講習を適切に実施・活用するために、何が必要かをその背景を含めて詳細に解説します。









