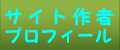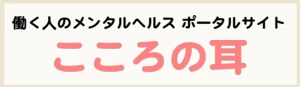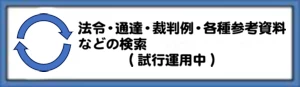※ イメージ図(©パリ廃兵員にて著者撮影)
映画「セデック・バレ」(原題 seediq-Bale:2021年 中華民国映画)は、日本支配下の台湾で発生したセデック族の反乱事件(霧社事件)を題材にした映画です。日本による台湾支配から、反乱の壊滅までを史実に則して描いており、セデック族と日本人の関係を描く人間ドラマとなっています。
霧社事件は、日本でも何種類かの解説書が出版されていますが、現代の日本人にはほとんど知られていないと言ってよいでしょう。筆者も、五味川純平氏の「戦争と人間」で知り、図書館で中川浩一他「霧社事件」(三省堂 1980年)を借りて読んでみた程度です。この映画は、中華民国では大ヒットしましたが、やはり日本人の関心は低く日本の観客動員数は残念ながら低調だったようです。
この映画は、誇り高きセデック族による日本人支配への怒りと、植民地支配による暴圧への抵抗という解釈ができることは当然です。しかし、極力な軍事力を背景にした支配構造の中で、支配される人びと、支配する側の人びとの考え方の齟齬という観点からも視ることができると思います。
これは、決して過去の事件としてみるべきではありません。今もなお、世界の各地から日本へ働きにやってくる人びとと日本人の間に、やや緩和されてはいますが起きていることなのです(※)。
※ ガザでは、同様な事件が発生しています。もちろん、様ざまなシチュエーションは異なってはいますが、私は、この映画を視ていて、ガザで起きた10月7日事件を想起せざるを得ませんでした。
この映画を題材に、外国人労働者との関係について考えてみたいと思います。
- 1 はじめに
- (1)霧社事件とは
- (2)霧社事件後の討伐
- 2 なぜ霧社事件は起きたのか
- (1)植民地支配による差別構造
- (2)セデック族の好意を拒否した態度
- (3)争いを収束させなかったこと
- 3 最後に
- (1)霧社事件から何を学ぶべきか
- (2)相手の立場に立って考える能力こそが求められる
1 はじめに
執筆日時:
最終改訂:
(1)霧社事件とは
ア 霧社事件までの経緯
(ア)日本による支配の始まり

※ イメージ図(©photoAC)
映画は、下関条約で日本が日清戦争の賠償として清帝国から台湾の割譲を強要するところから始まる。それまで、台湾は清帝国が領有してはいたが、実質的な支配が及んでいたとは言い難かった(※)。
※ 明末に、明の武将だった鄭成功が、当時東インド会社が支配していた台湾へ渡って根拠地を築こうとしたが、風土病に悩まされ、結局は清に敗れ去っている。
その後、清帝国は本格的に台湾経営に乗り出すことはなく、漢人の植民にも消極的であったが、少なくない漢人の商人や農民が台湾へ植民し、農耕や先住民族との交易を行っていた。
台湾に漂着した日本国民の台湾先住民による殺害事件に端を発して日本が出兵すると、ようやく清帝国は台湾に関心を持ち、人口調査などに取り組もうとしていた。日清戦争が起きたのは、その直後である。
台湾の割譲を受けた日本は、台湾の資源開発を目指して、台湾経営に乗り出す。日本軍は、先住民族であるセデック族に対しても支配を試みる。誇り高いセデック族は、日本に支配を受けることを潔しとせず、勇猛に戦った。
当初は、地の利を知り抜き、山岳地系の移動になれたセデック族の遊撃隊が優位に立った。しかし、先込め銃と弓矢を主な武器とするセデック族に対し、日本軍は機関銃、迫撃砲、手榴弾を保有している。日本軍の側が反撃に転じ、さらに先住民の居住区を襲うとセデック族の抵抗は途絶えることとなる。
日本軍は、少しでも逆らうそぶりを見せた住民は、たんに刀を持っていただけの子供を含めて容赦なく殺害した。恐怖政策をとったのである。
(イ)日本による支配
日本人の植民が始まると、セデック族の生業である狩猟のための銃は没収されてしまった。狩猟は許可制となり、結婚式等で野生動物を捕る必要がある場合は、日本人から没収された銃を一時的に借りて狩りを行うことになる。
また、漢人商人との取引は禁じられ、日本人の商店でしか商品は購入できなくなった。そして、低賃金で雇用され、日本人の植民者のための住居や警察署、学校等を建築するための木材の伐採と運搬に従事するようになっていた。
自らの生活の場である森林を破壊して、わずかな賃金を得るしか、生活する術がなくなっていたのである。大人たちは、働いていないときは酒を飲むしかやることはなくなっていた。民族の誇りは失われつつあったのである。
そして、子供たちは藩族用の学校で日本語や日本人の考え方を習うようになっていた。セデック族の伝統文化の継承も困難となっていたのである。
さらに、民族間で支配し支配される関係が生じたときには、必ず起き、支配される側の憎しみを掻き立てる現象がここでも起きていた。強制による若い女性への性的な支配・抑圧である。
だが、日本人には別な風景が見えていた。商店や学校をつくって、「未開の地の蛮族」に文化を施し、さらには仕事や教育も与えているという「良いことをしている」という意識だったのである。日本人はセデック族を保護していると考え、セデック族が日本人に対して反感を持っているなどとは夢にも思っていなかった。
その背景には、大人から子供まで多くの日本人の中にある、セデック族を下等民族とする差別意識があった。そして、実際に差別的な行為があらゆるところで行われていたのである。
もちろん、セデック族にも日本人にも例外的な人物はいた。セデック族で日本に留学して霧社藩の日本人警察官になっている者もいれば、日本人でセデック族に対して同情的でセデック族の女性と結婚した者もいたのである(※)。しかし、彼らは、決してセデック族や日本人の主流になることはなかった。
※ 大東和重「台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす「美麗島」」(中央公論社 2020年)によると、現地に居住している間の利便のためだけに結婚し、内地へ帰還するときに妻子が置き去りになるケースもあったようだ。このような場合、土地の有力者の子女と(都合上の)結婚をするケースが多く、そのことがセデック族の日本人への反感を強めた面があることは否定できない。
(ウ)事件のきっかけ
セデック族の不満は高まっていた。しかし、日本人の軍事的な優位性を知っていた彼らは、表向きは日本人に同調して生きていた。当時の台湾は日本の領土であり、「二流の日本人」という屈辱的な立場に甘んじるしかなかったのである(※)。そして、相変わらず日本人はセデック族の鬱屈した意識に気付いていなかった。
※ このような状況は、現在も世界各地に存在している。例えば、イスラエル国内のパレスチナ人がその例だと言えよう。
事件の直接のきっかけは単純なものであったし、普通であればそれだけで収まるような事件であった。セデック族の結婚式の会場を通りかかった日本人の警官に対して、セデック族の有力者が酒を進めたのである。
日本人警官は、セデック族の有力者の手が、獣を屠ったばかりで血にぬれているのを見て、酒の勧めを断ったのだが、セデック族の方は好意で強く警官の手を握って席に座らせようとした。
このとき、日本人警官がセデック族との友好に意を払うように教育されていたら、違った結果になったかもしれない。しかし、警官は腹を立てて、有力者を持っていたステッキでぶん殴るのである。怒ったセデック族は警官を袋叩きにしてしまった。
セデック族のリーダーが気付いて止めに入ったときは、警官はすでに血だらけで殴り倒されていたのである。
翌日、セデック族のリーダーと有力者数人が、警官に詫びを入れに宿舎を尋ねたのだが、警官は被支配者から暴力を受けたことで頭に血が上っていた。詫びに来たリーダーたちに対して「巡査殴打の件として上申済みだ。今回の件は、貴様らの部族全体で落とし前を付けてもらうからな
」(※)と怒鳴りつけて追い返したのである。
※ 映画「セデック・バレ」の DVD の日本語字幕より引用。
実際には、それまでもセデック族による日本人官憲に対する暴行事件や侮辱事件は頻繁に起きていた。たいていはその場で日本人側がやり返して、相手を威圧して収めているのである。大した事件ではなかったのだ。
警官としても、セデック族ともめごとを起こして、しかも殴り倒されたとなれば、無能という評価を受けるだろう。実際に上申したかどうかは怪しいものである。また、警察機構の同僚や上司たちもとくに問題にはしておらず、暴行事件を起こした部族を鎮圧する気など、まったくなかった。
しかし、支配される側はそうは考えなかった。日本人官憲を殴り倒した以上、自分たちは殺されるだろう。どうせ殺されるなら、いっそ、その前に日本人に対して反乱を起こして、万に一つの成功に賭けようと考えたのである。たまたま近辺の日本人が集まる運動会が開催されることになっていたので、これを攻撃しようとしたのだ。
相談を受けたリーダーは、最初は抑えようとしたが、結局は反乱に同意する。7つの部族に反乱に加わるよう檄を飛ばしたのである。この時点で日本人は誰も気づいていなかった。
イ 事件の経緯
セデック族は、1つの部族を除き、6つの部族が反乱に加わった。元々、闘いになれている部族である。武器は、日本人から奪った三八式歩兵銃(※)の他、弓矢、槍、湾刀を備えていた。日本人の側は警官がサーベルを持っているだけである。この時点では日本人がかなうわけがなかった。
※ この当時の植民地の日本人警官は、普段の武装はサーベルのみで、銃器は所持していない。なお、サーベルは刃引かれており、抜くことは禁じられていた。
しかし、非常事態のために、三八式歩兵銃を武器庫に保有していたのである。映画では、単発式のライフル銃が用いられており、三八式歩兵銃ではないが、実際には三八式歩兵銃だったと思われる。
まず、セデック族は夜明けとともに三八式歩兵銃の保管してある警察署を襲った。日本人警官は寝込みを襲われ、銃器を手に取る間もなく多勢に無勢で全滅してしまう。さらに周囲の警察署を襲い、警官はなすすべもなく殺害されるだけであった。
その後、運動会と周囲の日本人の施設を襲う。日本人側は、非武装の民間人がほとんどであり、逃げ惑う以外にどうすることもできなかった。さらに周囲の道にはセデック族が配置されて逃げる日本人を殺害したのである。この事件で、殺害された日本人(内地人)は134名であった。
※ 死者数は、「台湾新聞資料:霧社事件」による。
ただ、運動会には漢人や日本人(内地人)の妻となったセデック族の女性もいたのだが、彼らは殺害の対象からは外されていた(※)。また、セデック族で日本警察の警官になっていた者が2名いたが、2人とも殺害されることはなかった。
※ 日本人以外の死者は漢人が2名である。1名は和装していて日本人と間違われて殺害され、もう1人は流れ弾に当たって死亡している。
(2)霧社事件後の討伐
日本政府は事態を重く見た。当時、台湾は日本であり、日本の国内法ではセデック族も漢人も日本人なのである。当時の政府としては、天皇の赤子である日本人の反乱など、あってはならないことだった。
また、台湾全体に反乱が広がることも危惧されたのである。そのようなことにならないために、政府としては、迅速に鎮圧を行う必要があった。このため、鎮圧には、台湾総督府警察だけではなく、日本軍も警察の要請を受けて加わっている。
さらに、セデック族で反乱に加わらなかった藩(味方藩と呼ばれた。)も鎮圧に駆り出されている。被支配民族を鎮圧の道具にしたのは、現地住民と日本人(内地人)の争いという印象を弱めたかったこともあるだろう。
当時、日本政府はセデック族に首狩り(出草と呼ばれる)を禁止していた(※)が、このときは味方藩に報奨金を出して反乱部隊の首狩りを奨励している。
※ 「文明国家」の日本政府としては、首狩りを禁じたことはやむを得ない面があるが、これもセデック族の不満の一つになっていた。なお、下関条約締結まで、セデック族は首狩りをした頭部の遺骨を保管していたが、日本がセデック族への支配を行ったときに、警察が回収して埋葬している。映画では、埋葬のシーンで、セデック族が日本人警官と争うエピソードが描かれている。
結果的に、霧社藩の反乱軍の支配地域は、2日で日本人に奪還される。その後、敗走する反乱軍が最終的に降伏するまで、鎮圧にそれほどの期間は要しなかった。この過程で反乱軍はその家族を含めて 644 人が戦死又は自殺で死亡したとされる(※)。なお、討伐隊の死者は、軍人22名、警察6名、官役人夫29名、在郷軍人18名となっている。
※ 死者数は霧社藩、討伐隊の死者とも、酒井久能「営内神社・陸軍墓地等から見た霧社事件死没軍人の慰霊」による。
死者の一部には、鎮圧の過程で日本軍が用いた毒ガスによる者が含まれる。毒ガスを使用したのは、それだけ鎮圧を焦っていたこともあるだろうが、実戦における毒ガス使用の実験又は訓練として用いた可能性もある。
戦場で、非人道的な武器の実験が行われることは、現実にはよくあるのが現実である。米軍が用いた原子爆弾には実験の意味が含まれていたことは否定し得ない。また、イスラエルがガザなどで市民に対して用いている米軍供与の白隣弾や、「骨に当たれば砕けて体内で飛び散るタイプの弾丸
」(BuzzFeed Japan「トランプの決断で銃に撃たれた人々を治療した日本人の話」(2018年6月11日))なども同様であろう。
その他、500人程度が投降して捕虜となり、収容所に収容されていたが、日本人にそそのかされた味方藩に襲われて、214 人が死亡した(※)。これは第二霧社事件と呼ばれる。
※ 死者数は、毎日新聞 2019年10月27日「(下)セデック族を徹底的に追い詰めた日本」による。なお、中川浩一他「資料紹介・高永清「回想録」--川中島移住をめぐって」(茨城大学教育学部紀要 Vol.36 1987年)は死者 216 名とする。
この第二霧社事件は、1982年9月16日にイスラエル軍が、レバノンの避難民キャンプをレバノン右派の民兵に襲わせて、多数のパレスチナ人市民を殺害したサブラー・シャティーラ事件を彷彿とさせる。
映画では、この討伐と抵抗は戦争アクションのような描き方となり、セデック族の勇敢さを強調した筋立てとなっている。しかし、実際には戦死者数の差からも分かるように、一方的な鎮圧(ジェノサイド)だったのである。
女性たちの自殺シーンも、映画では戦闘の初期に男たちに食料不足が起きないようにと、進んで自決したように描かれている。実際は、戦闘終結が近くなって追いつめられ、殺されるよりはと死を選んだというのが実態に近い(※)。現実は、悲劇的な結末だったのである。
※ 映画の終わり近くに、セデック族のリーダーが味方には投降を許しておきながら、自分の家族を「生きていてもよいことはない」として殺害するシーンがある。現代の倫理観からは共感できるようなものではない。なお、これは映画の創作であると付け加えておく。
2 なぜ霧社事件は起きたのか
(1)植民地支配による差別構造
セデック族は、なぜ霧社事件を引き起こしたのだろうか。もちろん、直接のきっかけは警官による結婚式での殴打事件にあることは間違いはない。だが、これはきっかけにすぎない。反乱のエネルギーは醸成されていたのである。
また、被支配民族であるセデック族は、植民地支配下の民族として反乱を起こす正当な権利を有しているということを忘れてはならないだろう(※)。確かに、彼らが非戦闘員である非武装の警官や市民を殺害したことは許されざる犯罪行為である。そのことは否定はしない。
※ 写真の「霧社事件原住民抗日群像」は台湾にあるブロンズ像だが、これは(見れば分かるように)反乱軍を肯定的にとらえている。なお、この像のすぐ近くに、反乱事件のリーダの像も置かれており、レリーフには「抗日英雄」の文字がある。これらの像の碑文についての詳細は、竹内康浩「霧社事件の記念碑について」(北海道教育大学釧路校研究紀要 Vol.50 2018年度)、竹内康浩「続・霧社事件の記念碑について -補遺-」(北海道教育大学釧路校研究紀要 Vol.51 2019年度)参照
しかし、何よりも彼らは民族としての誇りを奪われ、民族固有の伝統を奪われ、かつ生活のための自律的な経済活動の手段を奪われていたのである。彼らが生きる方法は、支配者である日本人のために材木を伐採して運搬してわずかな手間賃を得る以外になかったのである。
もちろん、日本人として警察官になるなどの道がなかったわけではない(※)。しかし、それは、被支配者の側から仲間を支配する側に回るということを意味していた。名前も奪われて日本人風に改名し、宗教も奪われて国家神道を強制され、民族としての誇りも奪われるということが前提のことなのである。
※ どれほどの能力があったとしても、下位の職位に甘んじるしかなかったのではあるが。
これは、決して過去のことではない。現代のパレスチナ人がガザや西岸で受けている屈辱と共通するものがある。このような状況=植民地支配とアパルトヘイト政策こそが反乱を呼び起こすのである。
(2)セデック族の好意を拒否した態度
そして、反乱の直接の原因は、日本人警官が結婚式における祝い酒の勧めを断り、あろうことかステッキで、好意を示してくれた相手を殴ったことにある。
映画で、日本人警官が「唾で作った酒なんか飲めるか」とどなっている。明確ではないが、ことによると、唾が混じっている酒だったのかもしれない(※)。さらに映画でも血の付いた手で酒甕から酒を汲みだしていたので、日本人としては飲むことには抵抗があったのだろう。
※ 沖縄では少女が穀物を噛み砕いて吐き出した唾から神にささげる酒を造る習慣がある。セデック族の酒の作り方は調べても明確にならなかったが、同じようなものだったのかもしれない。もっとも、私の知り合いの沖縄出身者でも、飲むことには抵抗があると言っていたので、このような酒の作り方はそれほど一般的なものではないようだ。
しかし、異文化を有する民族と交流をしようという場合、このようなことは避けては通れぬことなのである(※)。この場合、この警官は好意を受けるか、せめてやんわりと断るかするべきだったのである。どうしても飲みたくなければ、勤務中は酒は飲めないと言えば済む話だっただろう。
※ 本多勝一「極限の民族」(朝日新聞出 1967年)の「ニューギニア高地人」の中で、現地の人が口で噛んだバナナを、本多氏が食べるシーンが出てくる。
それを、強く拒否した挙句にステッキで相手を殴りつけたのであるから、相手を対等な人間として見ていなかったのである。このような態度が、長年の植民地支配の鬱屈した気持ちに火をつけるのである。
(3)争いを収束させなかったこと
警官は、セデック族に袋叩きにあって頭に血が上り、詫びを入れた相手に対して「部族全体に落とし前を付けさせる」などと脅すようなことを言うのである。
実は、先述したように警官の上司も同僚もこの警官への暴行事件には、あまり関心を持っておらず、この時点ではセデック族に対して報復攻撃しようなどとなどという気はまったくなかったのである。
このとき、上司がセデック族のリーダーと警官の間に入って、セデック族の詫びを警官に受け入れさせておけば、少なくともその時点での運動会襲撃事件は起きなかっただろう。ところが、上司がこの事件についてまったく介入しないのである。
その理由は、セデック族を見下しており、反乱を起こすなどとはまったく考えなかったからであろう。彼らを、部下との仲直りをさせる対象などとは考えなかったのか、仲介をするほどの手間をかける必要性を認めなかったかである(※)。要は、大した事件でもないと思っていたのである。
※ あるいは、この殴打事件を、被害者警官の恥になることだと考え、警官への温情主義で見てみぬふりをしたのかもしれない。
セデック族の鬱屈とした不安があることを理解できておらず、かつ、部下がセデック族に対してどれほどの不安感を与えかたかを理解する気もないのである。これも、結局はセデック族に対する差別意識から起きていることなのである。
これも、現代の私たちに通じるものがある。それは現代における日本における外国人への意識の中にも垣間見えるのである。また、イスラエルのパレスチナ人に対する意識と共通する部分があると、筆者には思える。
3 最後に
(1)霧社事件から何を学ぶべきか
我々がここから学ぶべきことは、まず何よりも支配する側と支配される側、社会的強者と弱者では、同じものを視ていても、全く違うものが見えるということを知ることである。
南アフリカで、アパルトヘイト政策がとられていたとき、アフリカーンス(白人)の少女が、自分の豪邸を紹介しながら「黒人への差別などありません」と言っている動画を視たことがある。また、イスラエルでパレスチナ人の「テロ」を批判している人びとの多くは、自分たちがそれまでどれほどパレスチナ人を迫害し、苦しめてきたかを知りはしないのだ。
日本人もまた、外国人差別の意識を持ちながら、その意識に気付いていない人々は多い。そのような知ろうとしない、理解しようとしない態度こそが、民族間の対立の遠因となるのである。
この映画も、台湾では大ヒットしたにもかかわらず、多くの日本人は関心を寄せようとしない。そもそも台湾で日本人が何をしようとしたかを知ろうとさえしないのだ。だが、このことこそ、異なる文化を有する人びとと付き合うために最も大きな障害となるのである(※)。
※ 現在、ガザ地区においてイスラエルが数万人の市民を殺害しているが、日米欧(欧は一部)の政府は、イスラエルの行為を「自衛戦争」として容認し、ほとんど批判の声を上げていない。米国に至っては、イスラエルによる虐殺を支援している。さらには、欧米の政府はイスラエルを批判する自国民を「反ユダヤ主義」として取り締まってさえいる。
日米欧(欧は一部)の政府は、これまでイスラエルがパレスチナ人に対して何をしてきたかを知ろうともせず、現在ガザ地区で何が起きているかにも関心を持っていないようだ。日米欧(欧は一部)の政府が、これまで声高に主張してきた「人道主義」「人権主義」は何だったのだろうか。
このような態度こそが、アラブ社会のみならず、イスラム圏、さらにはグローバルサウスの人々の怒りを生み、国際社会を不安定化させるのである。
(2)相手の立場に立って考える能力こそが求められる

※ イメージ図(©photoAC)
少なくない日本人は、外国人が日本へ来るなら、日本の風習、言葉を覚えてから来るべきだと考えているようだ。確かにそのような考えにも一理あるかもしれない。
しかし、だからと言って、外国から日本へ働きにやってくる労働者に対して、相手の国家、文化、宗教に対して何も学ぼうとせず、尊敬の意識も持たなければ、外国人との関係がうまくいくはずがないのである。
我々日本人は、いまだに日本を先進国、アジア各国を開発途上国だと信じているが、すでに日本は凋落国家、アジアの少なくない国は急進国家となっている。今後は、外国とのグローバル化が何よりも必要である。
我々が諸外国の異なる文化を有する人びとと接することは必然的に必要になる。そのときに、なぜ、我々の祖先は霧社事件のような事件に遭うことになったのかを考えてみることも悪くはないだろう。
それは、我々の祖先が、異なる文化を持つ人々を見下し、相手の気持ちになって何が見えているかを考えようとしなかったからなのである。
【関連コンテンツ】

人類の未来の危機としてのガザにおけるジェノサイド
現在、ガザで行われているジェノサイドは、パレスチナへのホロコーストを目的としています。これを放置する危険性を人類の未来への危機という観点から解説します。

映画「バトル・ロワイアル Ⅱ 鎮魂歌」が発したメッセージとガザの状況
映画「バトル・ロワイアル Ⅱ 鎮魂歌」には、強いメッセージが含まれています。ガザにおけるイスラエルによる大量殺戮とこの映画の持つメッセージを解説します。

人権感覚を理解しないことは企業のリスク要因である。
人権の問題による炎上が企業のリスクとして無視できないものとなっています。いくつかの例を挙げて、人権感覚を磨くことが企業としても重要であることを解説します。

映画「アギーレ神の怒り」に学ぶ労務管理の失敗例
映画「アギーレ神の怒り」を題材に、企業の人事管理の禁忌について論じています。

映画「アポロ13」に学ぶ危機管理の成功例
危機的な状況から帰還を果たしたアポロ13を題材に危機管理について論じています。