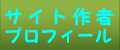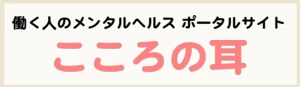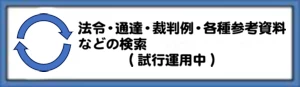ジェームズ・キャメロン監督のタイタニックを例に挙げ、国際規格の統一について自由に書いてみました。
その他、秦の始皇帝の度量衡の統一、航空機のポンドヤード法、身の回りの規格統一などについても紹介しています。
1 タイタニックと右・左
執筆日時:
最終改訂:
(1)面舵一杯・・・なのになぜ右へ?
1997年のジェームズ・キャメロンの超大作、タイタニックは大ヒットしたこともあって、ちょっとしたことがネットでおおきな話題になったものである。タイタニックが氷山に衝突する直前、一等航海士のマードックが"Hard-a-Starboard"と操舵士のヒチンズに命じるシーンがある。翻訳者はこれを、たぶん辞書か記憶に従ったのだろうが、「面舵一杯」と訳した。右側いっぱいに舵を切れという意味である。ところが画面ではヒチンズは操舵輪を左に切り、タイタニックは左側に転進しはじめる。
これがさっそくネットで話題になった。面舵一杯なら右側に転進するべきである。キャメロンの間違いではないかというのだ。だが、過去に作られた他のタイタニック映画でも、マードックは"Hard-a-Starboard"と命じ、タイタニックは左側に転舵している。しかもキャメロンはタイタニックを制作するにあたって、詳細な時代考証を行っている。もちろん間違いなどではない。
(2)舵手が間違えたのでもありません
だからといって、史実のヒチンズがあわてて操舵を誤ったわけでもない。映画の中でも、マードックは後になって船長のスミスに"I put her hard’a starboard and run the engines full astern・・・"と報告している。
(3)当時は現在とは舵の意味が逆だった
では、なぜこのようなことが起きたのだろうか。古代から現在まで、英語では船舶の右舷のことを "Starboard"といい、左舷を"Port"と呼んでいる。そして、タイタニックの事故の当時、英国では、Starboard側(すなわち右側)に舵を切ることを"Port"といい、Port側(すなわち左側)に舵を切ることを"Starboard"といっていたのである。一方、日本では、タイタニックの事故の前から一貫して右側に舵を切ることを面舵といい、左側に舵を切ることを取舵といっている(※)。したがって当時の日英の用語に従うなら、"Starboard"は取舵と訳すべきで、面舵としたのは誤訳というべきだと思う。
※ ちなみに日本の「取舵」「面舵」の語源は、かつて船首部分に取り付けられていた舟磁石の右側に酉と書かれ、左側に卯が記されていたことから発生している。つまり酉側(右側)に舵頭を切ると左転し、卯側(左側)に切ると右転したわけだが、「酉の舵」がなまって取舵となり、「卯の舵」がなまって面舵になったのである。
イギリスがこんなややこしいことをしていた理由には、歴史的な船舶の舵の構造が関係している。原始的な船(※)の舵は、舵柄をStarboard側に回すと船はPort側に転進し、Port側に回すとStarboard側に転進するのである。すなわち、"Hard-a-Starboard"とは、舵柄をStarboard側に一杯に回せということだった。・・・だったのだが、タイタニックの頃の大型船舶では、舵の構造がすでに操舵輪に変わってしまっていた。そして、操舵輪は逆にPort側に回さなければならないわけである。
※ 現在でもモーターボートや、手漕ぎ式の小型のボートなどはそうである。
(4)理由は国際規格の統一だった
ところが、これではあまりにもややこしいというので、タイタニックの事故当時でも大陸では、Starboard側に曲がることは"Starboard"といい、Port側に曲がることは"Port"というようになっていた。しかも米国ではStarboard側に曲がることは"Right"、"Port"側に曲がることは"Left"といっていたのである。
しかし、当時から船員が各国の汽船会社を渡り歩くことはあったし、船員が危急の際に命令を誤解することもあった。また、嵐などの騒音の激しい気象条件化で命令を聞き間違えることもあるというので、各国で統一しようということになり、最終的に大陸方式に合わせたのである。
2 異なる規格の統一の難しさ
(1)規格を合わせるだけでも国際関係は大変
船舶の操舵方法に限らず、現在でも、各国で規格が異なっているという例は実に多い。そればかりか、会社ごとに規格が異なっていることもある。ややこしいばかりか、操作者が、いつもと異なる規格の下で作業をしなければならないようなことになると、とっさのときに慌てて誤操作をして、重大な事故の原因となりかねない。このことは、誰しも判ってはいるのだが、実際にこれを統一するとなると、これがなかなか至難の業なのである。
規格を変更する側の国家や企業にとっては、大量のマニュアルやら設備・機械の変更を余儀なくされる。膨大なコストがかかるばかりか、一時的には両者が並列に存在して混乱のもとになる。また、それまで慣れ親しんだ方法を変更しなければならないわけだから、その直後にはミスを誘発して事故が発生する恐れもある。しかも、なぜ自分の国が変更しなければならないのかという国民感情やプライドもあって簡単にはいかない。
(2)MSDS を SDS に変えるだけでも一苦労
かつて、化学物質のMSDSの呼び方(だけではないが)がSDSに変わったときは、MSDS派の日米がSDS派のEU勢に合わせたのである。そのときでさえ、事業者の方から、MSDSをSDSに書き換えないと法違反になるのかという問い合わせを何度も受けたものである。そういうときは安衛法違反にはならないからそのままでかまわないと答えるのだが、本当に問題はないかときかれた場合は、MSDSのままにしておくと、新しい知識がないと思われる恐れがあると答えることがある。そうすると、お金がかかることですからねえと反応されることがあった。確かにその通りで、規格の統一には費用が発生するのであり、つねに費用と利益を衡量せざるを得ないのである。
また、一方では、SDSを下さいといったのに、渡された書類にはMSDSと書いてあっていくら言ってもSDSをもらえませんという問い合わせを受けたこともある。この程度なら笑い話で済むが、誤解から事故にでもつながると大変なことになる。
3 まだまだある異なる規格
(1)航空機のコクピットの天井の傾きが違う?
思いつくままに異なる規格で、話題になっている例を挙げると、航空機のコックピットのスイッチの例がある。コックピットの天井は前方に傾斜しているが、ここに多くのスイッチが取り付けられている。この斜めの天井を、ある会社は上下に傾いていると思い、別な会社は前後に傾いていると思うらしい。

別にどうでもよいと思うかもしれないが、意外にやっかいな問題が派生する。つまり、上下なら天井に取り付けるスイッチは、上がオンで下がオフにする方が分かりやすい。一方、前後だと前がオンで後ろがオフにするべきだろう。
つまり、みごとに逆になるのである。つまり製造会社が異なる飛行機に乗ると、スイッチのオン・オフの向きが異なるわけだ(※)。
※ 現在は、コントロールパネルがタッチ操作になっているので、この問題は生じない。
(2)操縦方法や信号くらいは統一して欲しいが・・・
航空機の例では、このような単純なことばかりではなく、自動操縦の考え方が違っているケースもある。中華航空機の名古屋空港での墜落事故では、その遠因にはまさにこの考え方の違いがあった。また、国際便で外国の空港へ降りる場合、国によって信号や標識の意味が違っていたりする。人間であればどうしても勘違いをすることもあるだろう。統一すべきだとパイロットの組合は要求しているが、いまのところ改善のきざしはない。
また、やや古い話になるが第2次大戦中のドイツ空軍は、ヤードポンド法ではなく、メートルキログラム法を使っていた。それだけなら、外国の航空機を使用しなければよいわけだが、ドイツ国内の航空機でも、スロットル(自動車のアクセルのようなものと思っていただきたい)の操作の向きが逆になっているものがあった。軍のパイロットは、異なる種類の航空機を操縦することは多かったから、大変な負担だったろうし、とっさのときには誤操作をすることもあっただろう。ナチの空軍大臣のゲーリングは元パイロットだったからそのへんの事情は知っていただろうが、独裁国家のナンバー2の強権家にさえもこれを統一することは難しかったようだ。
(3)“独裁者”秦の始皇帝でもないと・・・

一方、歴史的に単位を統一した成功例として有名なのは、独裁者として評判の悪かった秦の始皇帝の度量衡の統一が挙げられる。秦が中原を支配するまでの春秋・戦国時代の中国では、各国で度量衡がバラバラだった。また車の車軸の長さ(左右2つの車輪の間隔)も各国でバラバラだった。なぜ車軸の長さが問題になるかというと、中国の渇いた大地では、車両で道路を走ると、道の両側に轍による溝ができる。車両はその溝に車輪を入れて走ることになり、溝は長年の間に深くなってゆくから、車軸の幅が異なると道路を走れないようなことになってしまうのである。そのため、当時は別な国に行くときは国境で車両を乗り換えなければならなかった。
だったら最初から同じにしておけばよいと思うかもしれないが、最初に車両を作ったときは、どの国も国外へ行くことまで考えて車両を作ったわけではない。実際にグローバル化が始まってみてから、物流や人の流れ円滑にするには同じにしないと不便だとわかったわけである。ただ、戦車で攻め込まれることを防止するためには違っていた方がよいという面もあり、必ずしも悪いことばかりではなかったようだ。
しかも、各国とも長い歴史の中で度量衡などが決まっていたわけだし、車軸の長さを統一されてしまうと、多くの車両を作り替えなければならず、その直後は道路を作り替えなければ走ることもできなかったわけだろうから、大変な負担だったろう。これを統一してしまったのだから、始皇帝の権力は大変なものだったわけだ。しかし、このときに度量衡と車軸の幅を統一したおかげで、はるか未来の清の時代にいたるまで、中国の経済や国家経営には大きなメリットがもたらされたはずである。なお、「軌を一にする」とは、この車軸の幅の統一からきた言葉である。
(4)安全衛生の世界でも意外な不統一が
労働安全の分野では、クレーンの合図の不統一が問題になることがある。クレーンや玉掛け関係の技能講習のテキストは、国内で数種類発行されているが、それらの間でクレーンの合図の記述が微妙に異なっているのである。場合によっては、技能講習の登録教習機関ごとに異なっているケースもある。
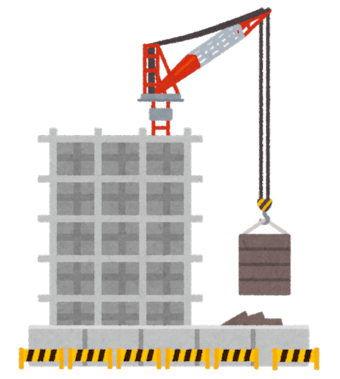
建設業の現場では、クレーンの運転手は様々な現場で作業をするため、合図の「方言」を熟知しているので混乱をきたすことはあまりないが、製造業では問題になることがある。統一して欲しいという要望は強いが、技能講習の制度が始まって以来、統一化が図られる兆しはみえない。
最近の日本で問題になっているのが、各鉄道会社間の信号と標識の統一である。各会社間で微妙に内容が異なるのである。各鉄道とも単独で運行しているときは、問題にもならなかったが、相互乗り入れが普通になるとそうもいっていられなくなる。一人の運転士が複数の会社の路線を走ることになるのだから、統一した方が望ましいとは分かっているのだが、これもそう簡単にはいかないのである。
(5)身近にもある規格の不統一
もっと身近な例を挙げると、かつては水道の蛇口はレバーを下げると水が出るものとレバーを上げると水が出るものが混在していた。これもなかなか統一できなかったのだが、これは意外な事情によって統一されてしまった。阪神淡路大震災のとき、上から物が落ちてきて蛇口のレバーを押し下げて水が出っぱなしになった例があることから、現在ではほぼ、上げると出るという形に統一されたのである。
また、米国のドアのレバーは、縦型のレバーは引いて開く、横向きのレバーは押して開くように統一されている。厚生労働省が入居している合同庁舎5号館でもそうなっていたのだが、セキュリティ強化のためオートロックを取り付けたとき、逆になってしまったドアがあった。日本だから問題にもならないが、米国だったら間違いなくドアを取り換えることになっただろう。
4 単位を変更したことによるインシデント事例
(1)航空機はなぜ今でもヤード・ポンド法に固執するのか
過去においては、国際規格の統一ではないが、単位の統一をしたことによって大きなインシデントが発生した事例がある。航空機の世界では今でもヤードポンド法が用いられることは、よく知られているが、一時期、メートルキログラム法が用いられたことがある。その際に、いくつかのミスが重なって、あわや大事故というインシデント事例が発生したのだ。
事故そのものは、労働災害の分野でも参考になる点があると思われるので、簡単に経緯を説明する。
(2)最初は致命的ではない燃料系の故障
大型の航空機の燃料計は2系統からなっており、片方だけが故障しても、その系統のブレーカーを切ってやれば、見かけ上はとくに問題なく動作するようになっている。あるとき、ある航空機の燃料系の1系統が故障した。それだけであれば、そのまま機長判断で運行しても会社の規定に違反してはいなかった。そこで、機長はそのまま目的地まで運行することにして、目的地に到着後、帰りの便のクルーにそのことを引き継いだ。
(3)2つのミスが重なって故障が致命的に
最初のミスがこのときに起こった。帰りの便の機長は、燃料計が2系統とも故障していると誤って認識してしまったのである。2系統とも故障していれば、それを運行することは規定に違反している。だが、前のクルーの機長は会社の規定に違反して運行してきたのだと誤解した。であれば、自分もそうすべきだと考えた。もし運行を中止すれば、キャンセル料やなにかで会社は莫大な損失を受けるのである。
それからしばらくして、彼らの知らないところで、2度目のミスが行われていた。航空機に乗り込んだ整備員が故障しているという燃料計の動作状況をチェックしようとしたのである。彼にはそのような権限も義務もなかったにもかかわらずである。彼は、故障している方の燃料計のブレーカーを入れてみた。予想通り燃料計は作動しなくなった。だが、そのとき地上から呼び出しを受け、燃料計をそのままにして地上の業務に戻ってしまったのだ。
クルーがコックピットに入ると、燃料計は引継を受けた(と思った)通り、動作しなかった。
(4)燃料の量の計算ミス
そして、ここで最も重要なミスが発生する。積み込む燃料の計算をするにあたって、機長はまずポンドで計算してからキログラムに換算して用紙に記入し、それを副操縦士に渡した。副操縦士はこれをポンドに換算してから計算しなおしてそれが「正しい」ことを確認した。ところが、実は2人とも同様なミスを犯しており、必要量よりもかなり少なく計算していたのだ。
実際にクルーは燃料棒を用いて積み込んだ燃料の量を調べてみたのだが、そもそも積み込むべき量が間違っているのだから確認してみても、あまり意味はない。
その航空機は、いったん別な空港に降りてそこでも燃料を積んだのだが、そこでも同様なミスを起こして、必要な燃料の量を誤ってしまう。これが4度目のミスである。こうしてインシデントを避けることができる最後の機会は失われてしまった。
(5)太平洋上空で燃料切れ・・・エンジン停止
そしてエンジンが止まったのは太平洋の上空である。こうなると大型ジェット機はグライダーのような飛び方はできない。ある程度の速度がないと揚力が保てないのだが、空気の抵抗に抗して速度を保つためには、位置エネルギーを速度エネルギーに変換し続けなければならない。分かりやすく言えば、飛んでいたければ徐々に高度を下げざるを得ず、いったん高度を下げたら二度と上げることはできないということである。
幸い、かなりの高度を飛んではいたが、その位置エネルギーを使い果たして地上に激突するまでに飛行できる距離は限られており、その範囲内に空港はなかった。しかし、さらに幸いなことに、その距離内に、現在では使用されていない軍の飛行場があることが分かったのだ。そこで、そこに降りることにした。失敗は許されない。失敗しても上昇できない以上、着陸をやり直すことはできないのである。
(6)滑走路を間違い・・・あわや大惨事
ところが、着陸時にさらに5度目のミスを犯す。その空港には2本の滑走路があるのだが、指定された滑走路とは別な方に降りてしまったのだ。そしてその滑走路の先端ではサーキットレースが行われていた。そこへ航空機が突っ込めば大惨事となっただろう。幸いなことに最後のスイスチーズには穴はなかった。航空機はサーキットレース場の直前で止まったのである。
(7)やはりヤード・ポンド法の方が良かった・・・ということにしておこう
これは、燃料計が動作しないという異状と、いくつかのミスが重なって発生したものではあるが、メートルキログラムを採用したことにも問題があるとされた。そんなわけで今でも航空機の世界では、ヤードポンド法を使用しているのである。それが、長い目で見てよかったかのどうかは分からない。