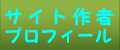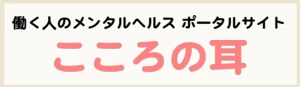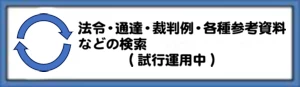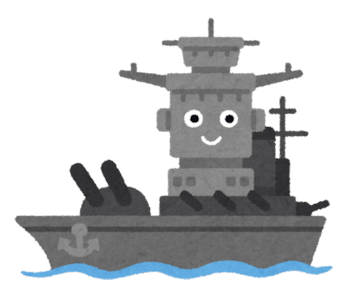
エドワード・ドミトリク監督のケイン号の反乱を例にとり、
①目的意識を持つことの重要性、及び、
②事業場に新しい安全衛生のシステムを導入する場合のトップの役割
について自由に書いてみました。
- 1 ケイン号の反乱について
- 2 現実に即した変化のできない組織
- (1)目的がないと組織は腐る
- (2)旧日本軍も同様だった
- (3)現代の企業はどうなのか
- 3 Uボート側の取組み
- 4 組織における制度改善の成否
- (1)ケイン号の新艦長のやり方
- (2)現代の企業での例
- 5 安全衛生のシステム導入のために
- (1)トップはシステムの中身を理解せよ
- (2)システムの目的と意義を明らかにせよ
- (3)具体的な方法を示せ
- (4)PDCAサイクルを確実に回せ
- (5)本当に役に立つことをした者を評価せよ
- 6 最後に
1 ケイン号の反乱について
執筆日時:
最終改訂:
ケイン号の反乱はハーマン・ウォークの同名小説を映画化したものであり、実際に起きた事件ではない。映画化のための撮影にあたって、米国海軍では反乱は起きたことがないという理由で、一時、海軍が協力を渋ったという話が残っている。反乱という言葉に敏感に反応したようだ。結局、映画の冒頭に説明文を挿入することで、折り合いをつけることとなった。
ところで、数年前に中国へ行ったとき、北京のホテルで何の気なしにテレビを点けたらこの映画を上映していた。さしもの中国でもアメリカのことなら反乱を扱った映画も問題にならないらしい。
さて、私自身は、小説の方を学生時代に読んでおり、映画化されたと聞いて観てみたいものだと思っていたのだが、なかなか機会がなく、地方局に単身赴任していたときにツタヤでみかけてようやく観ることができたものである。
原作はかなりの長編なのだが、映画は原作をかなり省略している。主人公キースのアナポリス海軍兵学校時代のエピソードは、卒業式以外は省略されているが、本稿では、この省略された部分の話から始めたい。
2 現実に即した変化のできない組織
キースは兵学校に入学したとき、いくつかの失敗をしてマイナスキングというニックネームをつけられてしまう。その後、奮起して優等生となるのだが、授業中に教官から潜水艦はどのように運用するべきかとの質問を受けるシーンがある。兵学校の使用しているテキストには「潜水艦は航続距離が短いので沿岸での使用に適している」との趣旨の記述があることをキースは知っていた。しかし、当時、アメリカの西海岸では、ドイツから遠洋を航行してきたUボート(潜水艦)が出没して通商破壊戦を行っていたのである。
キースは、米国の西海岸にUボートが出没していることを指摘するが、教官は納得しない。そこで、テキストに書かれている通りの回答をすると、教官は満足するのである。
(1)目的がないと組織は腐る
どこの国の軍隊でも、平和な時代には形式主義や官僚主義がはびこるものである。実を言えば、この当時の米国とドイツの軍隊は、日本や英国、フランス、ソ連などに比較すればかなりよい状況だった、また、キースが兵学校にいた頃はすでに日・独との戦争にも突入していた。それでも、このような状況があったのだろう。
なにしろ平時の軍隊では成果主義をとることは困難である。成果主義というのは、目的(利益の確保など)があって初めて成り立つものだが、戦争をしていなければ目的など存在し得ないのである。かくして如才ない者や事務能力のある者、人間関係をうまく築くことができる者が出世することになる。こうなると、世の中の変化に合わせて自らの組織を変えてゆこうなどとは、誰も思わなくなる。ルーチンワークをしている方が楽だし、自らの組織を変えることなど、やる気のない組織の中では、かえって組織の和を乱すやっかいな人物と評価されることになりかねないからだ。
人事評価制度を導入して(第二次大戦当時の米国海軍も導入していた)、各自に目的を設定させても、目的のための目的、評価のための評価になってしまいがちである。もちろん、一般論としては、人事評価制度そのものは組織の活性化に有効なものである。しかし、目的の無い組織では、形式主義に陥りやすいのである。そして、実際にそうなると、被評価者の納得性が得られないようになってしまい、かえって組織の活力や職員のやる気が削がれたりする。頑張っても頑張らなくても、正しく評価されないと思えば、人間はやる気をなくすものなのだ。平時の軍隊というものはまさにそのような弊害の出やすい組織なのである。
かくして潜水艦は沿岸で使用するものという固定観念(と兵学校のテキスト類の記述)は、実際に西海岸でドイツのUボートに自国や友好国の商船を破壊されるようになっても、誰も変えようとはしなかったのである。
面倒だということもあったのかもしれないが、教条主義に陥っていた面もあろう。「教科書」に書かれていることを金科玉条のごとく扱って、現実との違いを認識しようともしなかったのである。
(2)旧日本軍も同様だった
ア 真珠湾攻撃の失態
当時の日本軍も決して例外ではない。真珠湾を攻撃した南雲部隊が、旧式の軍艦だけを沈めて、燃料タンク群や修理工廠などを攻撃しなかったこと、真珠湾に空母がいないことが分かったときに索敵機を飛ばして空母を探そうともしなかったことなどもその表れである。大艦巨砲主義の残存があって、補給の重要性や航空機の重要性に、本当には気付いていなかったのであろう。
そもそも、日本軍の沈めた大型艦は、その後アリゾナを除いてすべて引き上げられてしまった。そして、損傷が激しくてスクラップにされた1隻を除いて、すべて戦線に復帰することになる。つまり、損害はそれほどでもなかったのだ。これも修理工廠を破壊しておかなかったことが一因である。
また、当時は米国でも大型タンカーは開発されておらず、大量の燃料をそう簡単に運ぶことはできなかった。このため燃料タンク群を破壊しておけば、その後の米国海軍の動きはかなり制約されたはずである。この点について、当時の軍艦の燃料は重油であり、航空機でタンクを攻撃しても炎上させることは不可能で、さしたる効果はなかったはずだという説もある。しかし、片っ端から爆弾でタンクを破壊して、湾内へ大量の重油を流出させれば軍港としての機能をマヒさせることもできたはずである。
イ 真珠湾攻撃失態の原因
そもそも、南雲は真珠湾攻撃の本当の目的を知らなかったのである。山本が、南雲に真珠湾攻撃の意味を明確には伝えていなかったのだ。山本のねらいは米国の空母部隊を壊滅させることだったのだが、南雲との関係がそれほどよくなく、山本の人間的な問題で、人間関係のよくない人間に対してきちんと話をすることをしないのである。
むしろ南雲は、軍令部から連合艦隊を無傷で戻すように言われていた。つまり、第二次攻撃をしなかったのは軍令部からの指示に忠実に従ったという見方もできるわけで、目的が不明確なままでは、最初から成功などおぼつかなかったのである。
南雲が第二次攻撃をしなかったことについて、山本は不満だったといわれるが、それなら最初から目的を共有しておくべきだったろう。歴史にイフは許されないが、湾内に空母がいないことが分かれば、ただちに索敵機を出すようにと指示しておけば、当日の米軍空母の位置関係から発見できた可能性は高かったと思われるのだ。また、彼我のパイロットの能力差から考えれば、発見後にただちに攻撃をしかければ勝算はかなりあったはずである。
ウ 真珠湾攻撃がもたらしたもの
当時、米国は(形の上では)中立国だったし、国民世論は戦争に参加することを拒んでいた。最後まで参戦しなかった可能性もないわけではない。それなのに、真珠湾を攻撃して、旧式の軍艦を沈め、それと引き換えに米国を戦争に引き込むという最悪の結果を生じたのである。すなわち、真珠湾攻撃は戦略的には失敗であったし、戦果も軍事的には意味のあるものではなかったのである。
ところが軍令部は、真珠湾攻撃について、大戦果だと国民に発表した。さしたる戦果を挙げることもなく、米国を戦争に巻き込むという大失態を主導した山本が国民的英雄となってしまったのだ。
かくして、真珠湾の失敗について反省されることもなく、また、山本も責任をとらされることもなく連合艦隊司令長官の地位にとどまるのである。こうして、この無能な人物はミッドウェイでさらなる失態を重ねることとなる。
エ 真珠湾攻撃の失態は海軍の組織の欠陥にあった
真珠湾での失敗を避けるためには、まず真珠湾攻撃の前に、関係者が目的を共有し、その目的を達成するためには何をするべきかを民間人の専門家も含めて徹底的に検討しておくべきであった。湾内に空母がいないことも考えられるのだからそのときの対応や、また、第二次攻撃で優先して破壊すべき目標を定めていれば、真珠湾での失敗は防げた可能性があるのである。
また、少なくとも事後にきちんと、攻撃の「成果」が戦争遂行という大目的にとってどのような効果があったのか、さらに効果を上げるためにはどうすればよかったか、失敗を繰り返さないためにはどうすればよかったかについて検討していれば、その後の珊瑚海海戦やミッドウェイ海戦の状況は大きく異なっていたはずだ。
(3)現代の企業はどうなのか
ア 安全衛生部門が抱えやすい問題とは
ある意味で、労働災害の減少した企業の安全衛生部門というのは、平時の軍隊と似たような面があることは否定できない。どうすれば労働災害が減少できるかという目的をもって、工夫や努力をしても評価されにくいのである。結果が数値として表れないからだ。
イ 目的のための目的を定めたら組織は腐る
よく、年間にわずか数件程度の不休災害の発生件数や数年に1回程度発生する休業災害を「分析」して、災害が増えたとか減ったとか「評価」している企業があるが、もちろんそんなことには何の意味もない。災害が増えたときの職員の意識付けのためというならともかく、数件程度の不休災害では、件数は偶然によって左右され、努力したからといってどうなるものでもない。努力してもどうなるものでもない数値で評価されれば、組織はやる気をなくすのである。
不休災害を問題にしなければならないのは、以下の2つのケースくらいに限られる。めったに発生しないような不休災害についてまで、気にする必要はないのである。
- 同種の災害が、作業に伴って繰り返して発生する恐れがある場合(例:バリのある材料を素手で取り扱って怪我をする、濡れた床で作業していてころんでけがをするなど)
- 重大な災害が発生する可能性があったが、たまたま不休災害となったにすぎない場合(例:高所から落ちかけて近くのロープにつかまり、かるく腕に痛みを感じたような場合)。
このような価値のないことを目的にすれば組織は確実にやる気を失うのである。また、数の少ない不休災害は運によって発生件数が変動するため、努力する意味がなくなってしまう。さらに労災隠しの誘因にさえなりかねない。このようなことをしていたら、組織は停滞し腐るのである。
ウ マネジメントシステムの本当の意味とは
実を言えば、このような現場の目的意識の希薄さや、それに必然的に伴う能力の低下などに対応するために考えられたのが、労働安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントの各種のシステムなのである。つまり、誰が行っても同じような効果が出るようにマニュアル化をし、全体的なシステム化をしたわけである。
その意味で、マネジメントシステムやリスクアセスメントの各種のシステムというのは「必要悪」という面がある。やらなくてもよければそれに越したことはないが、現状を考えるとやらざるを得ないというものなのである。
もちろん、実際のマネジメントシステムやリスクアセスメントなどの各種のシステムは、いつ誰が実施しても同じ効果が出るようなところまではいっていない。そのため目的意識もなく、形式主義に陥って、マネジメントのためのマネジメント、リスクアセスメントのためのリスクアセスメントになってしまうと、何の役にも立たないことになってしまうのだが・・・。
エ マネジメントシステムを実行あらしめるために
これを役に立つシステムとするには、少なくとも、自社において発生する恐れのある労働災害の未然防止という目的を立て、それを予見しかつ結果を回避するためにはどのようにすべきかを、組織的に検討した上で、現場が納得できる形で示さなければならない。現場が、本音では納得できていなければ形だけ整えても成功することはないと思った方がよい。また、本当に効果的な活動をする部署があればきちんと検証したうえで、その部署や功労者を評価・顕彰することも必要である。
厚生労働省がマネジメントシステムやリスク評価の指針を示しているのだからというので、その内容の意味や目的も理解せずに、とにかくその通りにやってみようというのでは、効果が上がらないばかりか弊害さえ出るということを理解するべきであろう。
3 Uボート側の取組み
さて、いささか話が横道に逸れた。元に戻そう。沿岸で使用するべきものとされた潜水艦(Uボート)で、ドイツの艦員たちはどうやって大西洋を横断し、アメリカ西海岸まで活動範囲を広げたのだろうか
この辺の事情は原作にも書かれていないが、実は、かなりのルール違反が行われていたのである。艦長たちはUボートのありとあらゆる隙間に燃料を積み込んだ。中には魚雷発射管の中にまで燃料を積んだ猛者がいたという。だが、実を言えば、このようなことは禁止されていたのである。全体の重量が増して危険であるし、魚雷発射管の中にまで燃料を積み込んだのでは、駆逐艦に襲われたときに速やかな反撃ができにくくなる。
Uボート艦隊の司令は、米国へ赴くUボートの燃費がやたらによいことに気づいていた。表向きは燃料を規定通りに積んでいるのだから、いくら航行しても燃料がなくならないわけである。だが、彼らはUボート艦長たちのやる気を削ぐような愚かなことはしなかった。
Uボートの艦長や乗組員は、自分たちがやろうとしていることの意味を理解していた。近代戦においては通商破壊戦がきわめて重要であること、商船は世界中のどこで沈めても戦争行為への効果は同じであり、護衛の薄い地域を狙うのが効果的であることを、である。
戦場で10輌の戦車を破壊するよりも、戦場へ100輌の戦車を運ぶことができなくすることの方がはるかに効果的である。また、米国西海岸で船舶を沈めれば、米国は欧州向けの船舶を米国内向けに振り替えざるを得なくなり、結局は欧州での戦闘を有利にすることができるのである。
だからこそ、その時点で護衛の薄い米国西海岸で攻撃するための必死の努力が行われていたわけである。
枢軸国の戦争目的が侵略であり、正義に反したことは言うまでもないが、目的意識をもって、その目的のために邁進しようとするとき、組織はその本来の強みを発揮するのである。
もちろん、現代の工場では目的意識を持って創意工夫でルール違反を犯すことなどは許されることではない。しかし当時は、戦時だったのである。このような場合に危険を冒すことは、平時とは異なった評価がされるべきことは当然である。
4 組織における制度改善の成否
(1)ケイン号の新艦長のやり方
さて、話を映画まで戻そう。キースがケイン号に赴任したとき、彼には、艦内の乗組員の規律(服装や態度)がかなり乱れていると感じられた。これは艦長のド・ブリースが、結果を出しさえすれば形には拘らないという人物だったからである。なにしろキースが最初にド・ブリースに会ったとき、この艦長は素っ裸で執務していたほどなのである。さすがに映画では腰にタオルらしきものを巻いてはいたが。
キースはこのためド・ブリースと対立する。実はド・ブリースは乗組員には慕われていたのだが、キースにはその理由も理解できなかった。
やがて、ド・ブリースから艦長の交代があると聞いてキースは喜んだ。ハンフリー・ボガートが演じる新艦長のクイーグが赴任してくると、この新艦長は、艦内の乱れた規律を徹底的に正そうとした。当然ながらそれまでのやり方に慣れた乗組員は反発する。そして、形だけの服従をするようになってしまった。クイーグにもそれは分かるから自分が馬鹿にされていると感じるのか、異常なまでに乗組員の規律に拘りはじめ、乗組員と対立を深刻化させてゆく。
この対立が決定的になるのが、海兵隊の上陸支援の任務に際してクイーグが臆病な態度をとったときである。士官たちさえ陰ではクイーグを侮るようになってしまい、副長のマリクを除くと誰もクイーグを擁護しなくなる。さらに、一部の士官たちはクイーグが精神的に異常をきたしていると疑い始める。そのような中、クイーグの行動はますます異常なものになっていった。
もちろん、一般論としてはクイーグが着任の直後に、行おうとしたこと=服装の乱れに関する規律の回復は、間違っていたわけではない。しかし、あまりにも性急すぎた。ズボンからシャツの裾を出している乗組員を士官たちの前でどなりつけたり、事前に警告することもなくいきなり罰(上陸禁止)を与えたりするようなことをするのだ。
現代の日本の企業ならハラスメントといわれそうだが、もちろん当時の軍隊ではそんなことは問題にもならない。しかし、このことが艦長と士官たちとの間の意思疎通に問題をもたらしたのである。そしてそのことが「反乱」の誘因となってゆくのである。
規律の改善は必要だったかもしれないが(副長のマリクもこの艦は異常だと言っている)、しかし、その必要性を理解させずに、形だけ無理やりに直そうとしてもうまくはいかないのである。その意味では、艦の本当の目的が何かを理解したうえで、乗組員に納得させて、必要なことだけをさせたド・ブリースの方が艦長としては適任だったのである。もちろん、現代の企業で安全パトロールが入ったら、クイーグの方がはるかに好成績の評価を受けるだろうが・・・
(2)現代の企業での例
目的は正しくても、組織の反感を買う恐れのあることは、いきなり命じるのではなく、その必要性を相手に理解させなければ、形だけは導入されるが、実質的には効果が上がらないのだ。
よくある深刻な例が人事評価制度と成果主義である。人事部長や総務部長クラスの管理職が人事評価制度や成果主義を導入しようとする。うまく機能すればよいのだが、失敗するケースが実に多い。制度の必要性や有効性を組織に理解させないまま、早急に導入しようとするから、実態は評価のための評価になってしまうのである。
また導入にあたって、恰好だけは評価制度の研修をするのだが、一般的な知識だけで具体性のある研修になっていないから、評価の方法や目的が組織内に浸透していかないのである。結果的に、形式的な評価をするようになる。こうなると「頑張ってもボスは評価してくれない」ということになり、形式的な成果だけを挙げようとするかやる気をなくしてしまうことになる。
また、人単位や部署単位で、短期間の成果について評価しようとするから、情報の抱え込みなどセクト主義の問題が起きる。なにもわざわざ競争相手の他部署に貴重な情報を与えることはないだろう。さらに、長期的な思考の欠如なども起こりやすくなる。「とにかく今期だけ成果が上がれば後のことなど知ったことではない」「若い連中を教育しても評価されるわけではない」ということになるわけだ。
最大の問題は、トップが形式的な成果だけを見て、わが社はうまくいっていると思い込むことである。こうなると組織は活力を失ってしまう。
安全衛生マネジメントシステムも、形だけ導入しても効果はないばかりか弊害が出るだけなのだが、現実にこうした弊害はよく起きているので注意しなければならない。導入しようとする安全衛生の担当者はその目的も意味も解っているのかもしれないが、現場にその必要性や有効性、さらには目的を理解させることは簡単ではない。そこで、手っ取り早く形だけ導入しようとして失敗することになるのだ。
導入される側の現場の方は、内心は「意味のないことをさせる」と思ってはいるが、組織としての命令なので形だけは服従する。そして、形だけは「成果」も上がるのである。例えばリスクアセスメントの実施率が○○%になった、リスクレベルが○○まで下がったなどという「成果」である。なぜなら「成果」を出しておけば、人事評価をする上司の覚えがめでたくなるし、数字を出すだけなら簡単だからだ。だが、実際には、リスクアセスメントそのものがどこまで、効果的に行われているかなど分かったものではないのである。
その気になれば、リスクレベルを下げやすいリスクだけをリスクアセスメントの対象に取り上げることも可能だし、対策を立てた後のリスクレベルが下がったことにするなど、どのようにもできるのだ。
そしてここでもトップが形の上での成績だけを見て満足するようだとことは深刻になる。こうなってくると、労働災害の防止など覚束ないばかりか、組織そのものがじわじわと腐り始めるのだ。
5 安全衛生のシステム導入のために
(1)トップはシステムの中身を理解せよ
これを防ぐためには、安全衛生管理について、トップが内容を理解するようにしなければならない。もちろん、細かなことまで理解する必要はないが、「安全衛生のことは難しいから君にまかせるよ」では、まかされた「君」の方は、トップが安全衛生について重視しておらず、その重視していないことを担当させられたと感じてしまう。これではだめなのだ。
例えば、リスクアセスメントを導入するのであれば、担当者に対して、リスクアセスメントとは具体的に何をしようとするのかを聴くのである。リスクを洗い出して、その大きさを評価するのだとの答えがあったとしても、具体的にどうするのかが分からなければさらに尋ねるべきである。ある程度、納得できる回答があるまで尋ねるのである。
もし、簡潔で、納得できる回答が返ってこないようなら、うまくいっているとは思わないことだ。「複雑な方法なので詳細な説明は難しいのですが・・・」などという答えが返ってきたら、まずうまくいっていないと思った方がよい。説明もできないような複雑な方法が現場に浸透するわけがない。また、本人が理解していないのでそのように説明している可能性もある。
そんなときは、「いついつまでに分かるように報告してくれ」といって納得できるまで説明させるべきだ。聴くまでもなく分かるようなことは別だが、少なくとも新しいシステムを導入しようというときに、その仕事を部下にまかせるのであれば、トップとしては自分に納得できるように説明させることが最低の条件である。説明もしないような部下に仕事をまかせてはいけないことは当然なのである。
(2)システムの目的と意義を明らかにせよ
さらに、組織に対して、なぜそのシステムを導入し、どのような効果を上げることを期待しているのかを明確に示すことである。幸か不幸か、現時点では個々の企業における労働災害の発生件数はきわめて低いため、目的を示しにくいことは事実である。だからといって何かが起こればマイナス評価を受けるが、何もなければ評価されないというのでは、安全衛生担当者はやる気をなくしてしまう。
目標を示すにあたっては、以下のことが重要である。
【安全衛生管理活動における目標の要件】
- ① 目標は実質的なものであること
- ② 現場が努力することによって達成することが可能で、かつできるだけ偶然に左右されないものであること
- ③ 形式的な件数主義であってはならないこと
③についていえば、件数だけを目標として示すと、現場は形だけの件数を挙げて「成果」としてしまうからだ。
ある企業で、提案制度が1人当たり月に数百件という例があった。もちろん、役に立っていないのだが、当事者たちは満足しているのである。
詳しく提案の内容を見ると、掃除機を買ったので、どこそこの床にテープで印をして置くべき場所を決めるとよいというようなものばかりで、しかもテープをガムテープに変えたり、どこそこの場所を変えたりして、何件となく出してくるのである。もちろん、中身がこんなものだとは判っているから、上司も提案の中身を見ようとはしない。また、提案をする側もまともな提案を出しても見てもらえないことが分かっているので、本気で提案を出したりはしない。
つまり、実質的にみれば、提案制度はないのと同じである。いや、まともな提案をしたくてもできないというストレスがたまるだけ、ない方がましかもしれない。
(3)具体的な方法を示せ
次に、組織として、システムに関しての具体的な手法を示すことである。例えば、リスクアセスメントについていえば、厚生労働省の指針に書いてあるからそれを使うというのではなく、担当者や現場が、以下のように思えるから使うというものでなければならない。
【リスクアセスメント手法の要件】
トップ、担当者、現場のすべてが、
- ① その目的・必要性を真に理解することができること
- ② これなら「確かに役に立つ」と思えるようなものであること
- ③ これなら「マンパワーの面からも能力の面からも、実施可能である」と思えるようなものであること
確かに、このようなシステムを作ることは難しい。しかし、出来合いのやり方を、権威のある方法だというだけで、内容について納得もしていないのに形だけ導入するというのでは、「成果」も形だけのものになってしまうことが多いのである。そして、自ら作ったシステムが、現場で理解されないようなら、理解されるようにしなければならない。
なお、出来合いのシステムを用いることが、常によくないと言っているのではない。ただ、使うのであればそのシステムの原理を理解したうえで、メリットとデメリットを十分に分かったうえで使うことである。それを理解せずに用いると、かえって危険を呼び込むことになりかねないからである。
(4)PDCAサイクルを確実に回せ
もちろん、目標とやり方を示しただけでは足りない。確実にPDCAを回すことにより、会社にとって役に立っていること、コストに見合う利益が出ていることを確認しなければならない。また、よりよい方法がないかを常に検討しなければならない。そうでなければ自己満足に過ぎないからだ。
もちろん、ここにいう利益とは会計上の利益だけではない。モラールの向上や災害リスクの低下など、目に見えないような利益も含めて考えるべきである。
また「C」については、「決められたことが決められたとおりに行われているか」だけをチェックするのではない。これだけをチェックしていたのでは、システムに欠陥があった場合は、欠陥を維持するだけである。そうならないようにするためには「決められたことが、本当に役に立っているのか」をチェックする必要があるのだ。ここを間違えてはいけない。
また、現場が本当にシステムの必要性と有効性について納得しているかもチェックした方がよい。現場の忠誠心を図るためではない。現場の納得性が得られていないと、システムが有効に動かないからだ。ただ、「納得しているか」と聞いてみても「YES」としか回答は返ってこない。会社の作ったシステムに現場が納得していないとしても、そのことを引き出すのは簡単ではないということは理解しておいた方がよい。「当社のシステムはアンケートの結果、現場の納得度が90%です」などと言ってみても意味はないのである。たんに、本当のことがいいにくい雰囲気だけなのかもしれないからだ。
(5)本当に役に立つことをした者を評価せよ
また、リスクアセスメントについてのツールを用いたとしても、シナリオ抽出やリスク評価については「いつ誰が行っても同じ結果が出る」などというものではない。これはファストフード店のマニュアルではないのだ。
内容を理解してよい結果を出した職員も、形だけ実施して意味のない結果を出した職員も、人事評価制度の中で同じように「実施した」という評価がされるだけというのでは、誰も真剣に取り組まなくなる。
この評価もなかなか難しいが、リスクアセスメントのシナリオ抽出について言えば、○○係の○○がこのようなシナリオを発見したとして、発表することなど、様々なことが考えられる。
6 最後に
安全衛生管理システムのみならず、新たなシステムを効果的に動かすためには、「決まりごとを作って、決められたとおりに組織が動いているかをチェックする」だけではだめなのだ。組織を作っているのは人間であり、たんに決められたとおりに動けと言われても効果は出にくいのである。
目的を共有して、その目的を達成するために組織の心を一つにすること、そしてそのための納得できる手段を示すこと、トップの役割はまさにそこにあるのだ。
ケイン号のド・ブリース艦長とクイーグ艦長の違いは、そのことができたかどうかの違いなのである。