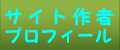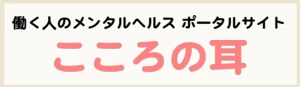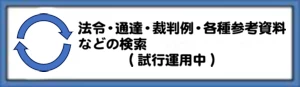映画「スパイゾルゲ」には、人間の行動の不条理が描かれています。
ひとつはスターリンがゾルゲの警告を無視してドイツ軍による奇襲攻撃を受けたこと、もうひとつはゾルゲ諜報団がばかげた不注意によって壊滅させられたことです。
これを題材に企業の危機管理について論じています。
- 1 映画「スパイゾルゲ」とは
- 2 ゾルゲの功績とは
- (1)日本がソ連攻撃をしなかったのはゾルゲの功績なのか
- (2)ゾルゲの真の最大の功績とは
- (3)なぜゾルゲは危険を察知できなかったのか
- 3 スターリンはなぜドイツ軍の侵攻を信じなかったのか
- (1)緒戦の大敗の原因
- (2)スターリンはなぜドイツ侵攻を信じなかったのか
- (3)ここから何を学ぶべきか
- 4 ゾルゲはなぜ必要な注意を払わなかったのか
- (1)危険への慣れのこわさ
- (2)私の経験から(ある工場のリスクについて)
- 5 最後に
1 映画「スパイゾルゲ」とは
執筆日時:
最終改訂:
「スパイゾルゲ」は2003年公開の篠田正浩監督の映画である。監督は、この映画を最後に、映画監督を引退するとの覚悟で作られた作品である。当時のコンピュータ技術の最先端を活用してコンピュータグラフィクスを多用して作成されている。この映画では、フィルムを用いずに撮影し、画像はハードディスクに保存されて、最終的にフィルムに焼き付けられるまでは電子データとして処理されている。
監督は、第二次世界大戦において当時のソヴィエト連邦のために命を懸けてスパイとして働き、祖国に裏切られて処刑されたゾルゲの人間像を描きたかったのではないかと拝察する。残念ながら興行的には必ずしも成功したとはいえず、ネットの評価も高いとはいえなかった。しかし、ゾルゲばかりか尾崎や宮城らの鎮魂の役割は果たし得たのではないかと思う。
2 ゾルゲの功績とは
一定の年齢以上の日本人なら、ゾルゲの名前を知らないことはまずないといってよいであろう。我が国で発刊されたゾルゲに関する文献はきわめて多い。そしてその多くは、彼のソ連への最大の成果を、ドイツがソ連に侵攻した後に、日本にソ連侵攻の意図がないとの情報をモスクワに報告したことであるとしている。
この情報があったために、スターリンは極東のソ連軍を西部戦線(ドイツにとっての東部戦線)に移動させることができ、日本軍による攻撃の憂いなくドイツ軍への反撃に専念できたというのである。
私自身は、このことについては疑問を持っている。日本にソ連侵攻の意図がなかったと言っても、それは東京のことである。東京が意図していないことは起きないというのであれば、張作霖の爆殺も柳条湖事件も盧溝橋事件の後の戦闘の拡大も起きはしなかったであろう。
(1)日本がソ連攻撃をしなかったのはゾルゲの功績なのか
ア 日本陸軍(参謀本部)は独ソ戦を望んでいなかった
そもそも関東軍(※1)の参謀たちが、東京の参謀本部(及び大本営陸軍部)のコントロールに従わなかったために、日本は日中戦争の泥沼にはまり込むことになったのである。実を言えば、日中戦争が拡大するそれぞれの場面で、参謀本部は本音のところではあまり日中戦争を拡大したくなかったというのが実態なのである(※2)。
※1 中国の関東地方に配属されていた日本軍の呼称である。日本の首都圏の関東とは関係がない。
※2 陸軍は好戦的で、海軍は戦争に反対していたなどといわれることもあるが、そんな単純なものではなかった。実を言えば、参謀本部は蒋介石と和解したかったにも拘らず、トラウトマン工作のときなど外相の広田や海軍が和解の努力を無にするような行動をとったこともあったのである。
イ ノモンハンの戦いは、中央政府が現地の判断に引きずり込まれて起きた
日本軍とソ連・モンゴル軍が激突したノモンハン事件にしても、大本営は不拡大方針をとっていた(※)が、現地軍の小松原が戦機を良好とみて攻撃を始めたのである。初期の頃は必ずしも積極的とは言えなかった関東軍がまずこれに乗じて積極策に転じた。結局は参謀本部もこれに引きずられて、ノモンハン事件はその後、数次にわたって日ソ両国の戦車部隊が激突する大戦闘にまで発展したのである。そして最終的には、ソ連・モンゴル側が国境線と主張していたところまで日本軍が押し戻されて終結する。
※ 関東軍も事件勃発後しばらくは不拡大方針をとっていた。小松原がこれを無視したのである。確かに奇襲をかけられたソ連軍は混乱し、ごく初期には小松原は一定の"戦果"をあげたことは事実である。しかし、その後、ソ連軍は体制を整えて猛反撃に転じ、このために侵攻した日本軍は事実上壊滅してしまう。
ウ ノモンハンの戦いは、緒戦では勝利をおさめたが最終的には敗北であった
ノモンハン事件では、ソ連軍の戦車は装甲の厚さや砲の能力では日本軍の戦車の能力を上回っていた。しかし、ノモンハン事件の初期に、ソ連軍の戦車が日本軍の火炎瓶攻撃でかなりの被害を受けたこともよく指摘される(※)。当時の戦車はグリースや潤滑油などの油の層で覆われており、エンジンの熱で高温となっていて意外に簡単に燃え上がったのである。実際に緒戦におけるソ連側の被害は、相当に甚大なものだった。
※ 火炎瓶による戦車攻撃は日本軍のお家芸と思われているが、必ずしもそういうわけではない。欧州戦線でも戦車に対する攻撃に火炎瓶は使用されている。ソ連軍に対するフィンランド軍の攻撃でも、ソ連軍による独軍への攻撃でも火炎瓶は使用され、かなりの効果を上げた。なお、火炎瓶のことをソ連ではモロトフカクテルと呼んでいた。
そのため、最近は、ノモンハン事件は実質的に日本側の勝利だと評価する向きがあるようだ。しかし、最後は、ソ連側が圧倒的な兵力を繰り出して、日本側はソ連側の主張する国境まで押し戻されて終結したのである。戦闘の原因(※)が、日本側の主張する国境線をモンゴル側が超えたことにあったのだから、どうみても敗北としかいいようがない。
※ 原因というよりも、それを理由にして始めたという方が正確かもしれないが。
エ ソ連の軍事力は、日本群をはるかに凌駕していた
また、このときのソ連軍は、緒戦の苦い経験に学んでいた。第二次ノモンハン事件になると、エンジンを燃え上がりにくいディーゼルに変え、エンジン室から乗員室に炎が入り込まないような工夫もした。彼らは失敗に学んだのである。その結果、ノモンハン事件の中期以降では日本軍の火炎瓶などでは簡単には破壊できないようになっていた。
なお、独ソ戦で勇名をはせた重戦車、T-34やKV-1は、この時点ではソ連軍は保有していない。
一方の日本軍は、主力戦車に軽戦車を用いていた。猛攻撃を加えてせっかく敵陣地に突入しても、敵の砲を鹵獲するにも牽引するだけの力がなく、押しつぶして破壊しようにも重量が足りずに破壊することもできないような状況だったのである。当時の日本軍の主力戦車は、イタリアは別として世界的な水準からかなり遅れており、近代的な戦闘などできるような状況ではなかった。しかも、その後もノモンハンの戦闘の経験が生かされることはなかった。
オ 関特演の際にもソ連へ侵入することは不可能だった
関東軍は、ドイツがソ連に侵攻した1941年6月22日のわずか21日後の7月13日には、大規模な動員を行って関東軍特殊演習(関特演)と呼ばれる演習を行っている。もちろんたんなる演習などではない。極東のソ連軍が独ソ戦のために手薄になるようなら、奇襲攻撃をかけることをねらった"演習"である。ヒトラーも日本軍がソ連を攻撃することを強く望んでいた。
しかし、結局は攻撃を開始することはできなかった。日本は、ノモンハン事件の経験からソ連軍の能力が侮れないレベルだと知っていた。そして期待したようにはソ連軍の東部戦線への移動も進まなかった。このため、ソ連侵攻をあきらめざるを得なかったというのが実態なのである。できるものならやりたかったが、できなかったというにすぎない。
すなわち、日本はソ連侵攻をしないとゾルゲが報告したから、ソ連が極東の軍を西部戦線に異動できたのではなく、そもそも日本軍が攻め入るスキを与えるほどにはソ連軍が手薄にならなかったので、その結果として日本軍による攻撃が行われなかったというのが本当のところなのである。
カ 関東軍は中国戦争で戦争遂行能力が限度に達していた
この当時の日本陸軍は、実のところ、中国軍に対して手を焼いており、ソ連を攻撃する余力を欠いていたというのが実情だったのである。確かに、蒋介石軍は南京、徐州、武漢、重慶と次々に退却しているので、一見すると日本軍が一方的に押しているように見える。
事実、この頃の中国軍は、装備の面で近代的な戦闘能力を有していたとは言い難く、同規模の部隊同士であれば戦闘能力は日本軍に及ばない状況だったことは間違いないだろう。ただ、援蒋ルートによる米国の支援で徐々に力を蓄えつつあった。一方の日本軍は補給ルートが伸びきっており、どこかのタイミングで反撃されて、一気に押し戻される危険もかなりあったのである。
なお、柳条湖事件の直後には、少数の関東軍が圧倒的な兵力を有する張学良軍を制圧しているが、これは張学良軍の主力部隊が留守だったときを狙ったことと、張学良の側が不抵抗主義を採ったことも大きな理由である。
キ 結局のところ関東軍は対ソ連戦争を遂行することは不可能だったのである
日本軍は、近代の地上戦の主力を担うべき戦車の能力が低かっただけではなかった。野戦砲は自走能力を有しておらず、"機動砲"という名称を付けられている砲は、実は馬が牽引していたようなレベルだったのである。歩兵用の銃も1発撃つたびに遊底を引かなければならない38式歩兵銃が使用されていた。
一方、ソ連側はやがてT-34やKV-1、KV-2という重装甲、長身大口径砲の戦車を配備するようになる。これは当時の日本の戦車で立ち向かえる相手ではなかった。また、カチューシャロケット砲も大量に配備していた。これは、命中精度はよくなかったが、飛行距離と破壊力は通常の砲の比ではなく、心理的な効果も大きかった。
歩兵にもトンプソンマシンガン(マンドリン)を一部の兵士に配布するようになっている。38式歩兵銃しか持っていない日本兵がマンドリンを持ったソ連兵に対抗することはきわめて困難であったろう。日本側が性能で優っていたのはヘルメット(※)と航空機ぐらいのものである。
※ 当時の日本軍のヘルメットは世界的に見ても優れた性能を有していた。
繰り返しになるが、当時の日本軍にはソ連を攻撃するだけの能力などなかったというのが本当のところなのである。
(2)ゾルゲの真の最大の功績とは
ア ヒトラーがソ連侵攻を企てていることを通報した功績は大きい
私は、ゾルゲの本当の最大の功績は、結局は無駄になったとはいえ、バルバロッサ作戦(独軍のソ連侵攻作戦)をかなり正確にソ連側に報告したことではないかと思っている。ゾルゲは在日ドイツ大使館では絶大な信頼を得ており、オット大使ばかりでなく、ドイツ本国からやってきた武官のマイジンガーからもソ連侵攻が近いことを知らされていた。
つまりは、そのニュース源からみてほぼ確実な情報をモスクワに伝えていたのである。もし、スターリンがこの情報源を正しく理解して、必要な準備をしていれば、バルバロッサ作戦の初期で、史実ほどの決定的な打撃は受けなかったであろう。
イ スターリンは知っていた
もちろん、ドイツ軍による攻撃が近いとの情報は、ゾルゲ諜報団以外からもモスクワにもたらされていた。ソ連国境付近に布陣していたドイツ軍からソ連側への脱走兵がいたことは有名な史実である。また、ドイツの印刷工場の労働者が、在独ソ連大使館へ、彼が勤める工場で大量に印刷している独ロ辞書を持ち込んだこともあった(※)。その辞書には「手をあげろ」「降伏しろ」などという文章がドイツ語とロシア語で記されていた。
※ ハリソン・E・ソールズベリー「攻防900日包囲されたレニングラード」(早川書房2005年)による。
では、なぜスターリンは、ドイツがソ連に侵攻するという明白な予兆があるにもかかわらず、それを信用しようとせず、ドイツ軍の奇襲を成功させたのであろうか。私の、この事件に関する"危機管理"についての問題意識のひとつは、この点にある。
(3)なぜゾルゲは危険を察知できなかったのか
ア 日本から脱出したかったが認められなかった
そして、もうひとつはなぜゾルゲ諜報団は、日本の捜査当局による捜査に対する必要な対策をとろうとしなかったのかということである。
実は、ゾルゲは、逮捕される1年ほど前から本国に対して日本から出たいと希望を伝えていた。ソ連へ帰国していれば粛清された可能性もあったろう(※)が、中国へ渡って、汪兆銘支配地域か満州国内へもぐり込めば生き残れた可能性もあろう。戦後のドイツ人に対する中国政府の扱いは、蒋介石、毛沢東ともに寛大であった。意外に、蒋介石に重用されて大戦後のソ連のために働き、フルシチョフ政権になってから、ソ連へ凱旋することができたかもしれない。
※ 事実、本国にいた彼の妻は、ゾルゲの死後にソ連当局によって逮捕されている。
しかし、当時のソ連はゾルゲから送られてくる日本の情報に価値を認めていた。簡単には、移動が認められなかったのだ。だが、それならそれで、捜査当局に対する十分な注意が必要であったろう。ところが、ゾルゲの側もかなりの不注意なことをしているのである。
イ ゾルゲ諜報団逮捕のきっかけとは
ゾルゲ諜報団が、日本の捜査当局によって逮捕されることになった端緒がなにかについては諸説あり、今後も明確になることはないだろう。現時点では、ゾルゲ諜報団の一員であった宮城(※)が米国共産党員の北林トモと接触したのが発覚の端緒になったとされている。
※ 宮城が米国共産党員であったことは当局に把握されており、彼を仲間にしておくことは危険な状況だった。
ウ 必要のない危険を冒していた
これは常識的に考えてみれば不思議な話だともいえよう。ゾルゲはオット大使の私的顧問で大使館の情報官という地位を得ていた。また、尾崎は日本の財政会の中枢とのつながりがあった。宮城はたんなる画家にすぎず、彼の収集できる情報など限定的なものであった。宮城があえて危険を冒してまで、米国の共産党員(※)から情報をとる必要などなかったのである。
※ 北林も日本政府や財界の情報を得られるような立場にはいなかった。なお、宮城と北林が男女の仲だったのではないかと疑う者もいるが、当時を知る者の多くは否定している。
エ 危険は予測できたはずである
確かに、宮城は米国に居住していたときには、米国共産党員であることを明らかにして活動をしていたわけではない。しかし、彼の周辺にいた者がロングビーチ事件で検挙されるという事件があった。ゾルゲとしても、宮城が米国共産党員であると、捜査当局によって察知されているという疑いを持つことはできたはずである。(※)
※ 実を言えば諜報団のヴーケリッチも同様な問題を抱えていた。
確かに、ゾルゲが訪日した直後は、英語が理解でき、日本の事情に通じている宮城が必要だったろう。マックス夫妻もヴーケリッチも日本語は全くできず、日本の実情にも通じていなかった。このため、宮城は、最初の頃は和文の情報を英文に翻訳する役割も果たしていたのである。また、映画スパイゾルゲでは、尾崎に連絡をつけるのも宮城が行ったこととされている(※)。
※ 実際には尾崎と連絡を取ったのは宮城ではなかったようだ。なお、尾崎はそれ以前に中国でゾルゲと知り合っていた。
オ 必要な対応がとられていなかった
しかし、ゾルゲ諜報団が活動を開始した頃には宮城は必要な人材だったろうが、ある程度、活動の基礎ができてからは、通訳と翻訳の他は、彼が行わなければならないことはほとんどなかった。彼を仲間に留めるにしても本当に必要なことだけをさせておくべきであったろう。彼が北林に接触したのは、取るに足らない情報のためにゾルゲと尾崎という重要な人物を危機にさらすというばかげたリスクを犯したとしか評価し得ないのである。
ゾルゲが尾崎と連絡を取れた後は、尾崎が英語に堪能だったのだから、宮城の役割は終わったといえる。適当な時期に沖縄に帰すか、満州を経由して第三国に出すかしておけば、終戦まで逮捕されず、生き残れた可能性もあろう。なぜ、あえて日本で危険な仕事をさせておいたのだろうか。
また、ゾルゲ諜報団から離しておけば、仮に逮捕されたとしても、宮城は命に代えてでも秘密を守ったであろう(※)。つながりさえ断っておけば、ゾルゲや尾崎までたどられることはなかった可能性が強いのである。
※ 事実、宮城は逮捕された直後に、建物から飛び降りて自殺を図っている。
また、ゾルゲは宮城のことだけではなく、他にも不注意というべき行動をとっている。機密書類を持ったまま酔っぱらってバイクで事故を起こしたり、女性の問題でも禁欲的とは言い難い行動をとっている。世界的な諜報団にしては、やることがお粗末すぎるのである。ソ連に残した妻のことや、常に危険に晒される生活の中で精神的な重圧はあったのだろうが、もう少し注意をするべきではなかったろうか。
では、なぜそうしなかったのか。これが疑問点の第2である。
3 スターリンはなぜドイツ軍の侵攻を信じなかったのか
ソ連へ侵攻したドイツ軍は、北方軍集団、中央軍集団、南方軍集団の3つに分かれており、中央軍集団にもっとも戦力が集中していた。北方軍集団は、レニングラードに向けて進撃し、レニングラードを陥落させた後、中央軍集団と合流してモスクワを目指すことになっていた。首都モスクワの攻略に最も力を入れていたのである。
対するソ連軍は、南方に主力を置いていた。ウクライナの穀倉地帯と、その先にある中東の油田地帯を守ることが彼らの使命であった。
中央軍集団がまさに国境を越えようとしたそのとき(※1)、ソ連側から列車がやってきた。列車には、独ソ不可侵条約に基づいて、ソ連側からドイツ側に送られてきた物資が満載されていたのである(※2)。もちろん、貨物には軍事物資も含まれていただろう。スターリンはぎりぎりまでヒトラーとの約束を守ろうとしていたのである(※3)。
※1 爆撃機はすでに開戦前に国境を超えており、地上軍が国境を超えると同時に、後方の部隊を襲うことになっていた。
※2 パウル・カレル「バルバロッサ作戦」(1986年フジ出版)による。
※3 独ソ不可侵条約によってドイツ側の得たメリットは、軍事物資だけではない。空軍パイロットの訓練もソ連で行われていた。もちろん、当時は極秘であり、事故で死亡したパイロットの遺体は、機械部品などの名目でドイツ側へ運ばれていた。
(1)緒戦の大敗の原因
ア 緒戦のソ連軍は遺体の責任はスターリンにある
スターリンは戦後しばらくの間は、大祖国戦争でドイツからソ連を守り抜いた英雄だとされていた。フルシチョフ批判で、"祖国の偉大な指導者"という幻想は打ち砕かれたものの、その後も、ドイツから祖国を防衛し得たという点においてはソ連国民の評価を得ていた時期もあったのである。
しかし、現在では独ソ戦緒戦の大敗の主要な責任はスターリンにあるとされている。スターリンがドイツの侵攻を信じようとせず、準備が不十分な中で奇襲を掛けられたことがその大敗の主要な原因であったというのである。そして、事実は、まさにその通りであった。
イ 軍事的に意味のない死守命令
さらに、緒戦にスターリンが無意味な死守命令を出したことで、ドイツ軍のお家芸の電撃戦による被害を増大させたことも指摘しておくべきだろう。スターリンが前線部隊に後退を許さないため、部隊が前線に留まっていると、ドイツ軍の戦車部隊はソ連軍の弱い所をすり抜けて、後方に回り込んでしまう。複数の戦線を破ったドイツ軍が後方で、包囲網を形成してソ連軍に猛攻を加える。そうすると降伏が許されないソ連軍はフラーを叫びながらドイツ軍に突撃して、全滅してしまうという悲劇が繰り返されたのだ。
ソ連軍も、ペリリューや硫黄島の戦闘の頃までの、旧日本軍と同じような欠陥を抱えていたのである。敵側にとっては、「激しいが短い戦闘で終わる」、「猛烈に抵抗するが、ある程度時間がたつと玉砕してくれるから楽なもの」ということになる。軍事的な効果をいかに上げるかよりも、潔さを示すことを重視するという傾向は、ソ連においても後にジューコフが最高司令官代理に就任するまで続いたと言ってよい。
ウ 現場の自主性を奪ったことが最大の問題
このような状況の背景には、日ソ両国とも、恐怖政治によって現場の指揮官の自主性が損なわれたことがあるといってよい。ソ連の場合は、スターリンがその猜疑心から、将軍や高級将校たちの多くを粛清したトハチェフスキー事件が挙げられる。高級将校のほとんどを処刑してしまったので、まともな作戦が建てられなかったばかりか、将校たちの志気や自主性も低下し、さらには指揮系統もマヒしていたのである。
また、ソ連軍はポーランド侵攻やフィンランド侵攻などで一定の戦闘経験は有していたものの、ほとんどの部隊は戦闘経験がなく、またドイツ軍のような優秀な軍隊と戦うことには慣れていなかった。対するドイツ軍は、クライストやグデーリアンなど優秀な高級将校が豊富におり、戦闘の経験や志気がソ連軍よりも格段に勝っていた。
エ 兵器の質では(数字上は)ドイツ軍を凌駕していた
しかし、この時点でソ連軍の装備がドイツ軍に比して劣っていたと考えるのは必ずしも正しくない。確かに、航空機の性能ではドイツ軍が勝っていたといえるものの、当時のドイツ軍の主力戦車であるⅢ号戦車は、ソ連のT-34やKV-1、KV-2の装甲を破壊することができなかった。フランス戦線では対戦車戦に有効だったⅢ号戦車の砲が、ソ連ではまるで役に立たないのである。これに対し、ソ連の戦車砲はかなりの距離からⅢ号戦車を破壊できた。
また、Ⅲ号戦車のキャタピラは幅が狭く、ソ連の道路事情では雨が降ると泥に埋まって立ち往生してしまうのである。当然のことながらソ連の戦車はソ連の道路事情を前提としていたため、キャタピラの幅が広く多少のぬかるみくらいなら自由に行動できた。
オ ソ連軍戦車の欠陥
ただ、ソ連の戦車には重大な欠陥があった。当時の中型以上の戦車の乗員は、どの国でも5人が普通だった。これはドイツでも日本でも同じである。ところがソ連の戦車は、乗員が4人しかいなかった。操縦手、前方銃手、砲手(装填手)、戦車長の4人で照準手がいない。当時の戦車は止まらないと照準ができなかったので、砲撃するときはいったん停止した。そして戦車長が照準をしている間に周辺の状況が変化してしまうのである。
戦車の設計段階で、現場を知らない者が設計しているため、装甲の厚さや、キャタピラの幅、砲身の口径などといった、(これまた現場を知らない)上司の気に入られるような"数字として評価される性能"は確保するのだが、実際の戦闘で必要な肝心のことがなされていないのである。
(2)スターリンはなぜドイツ侵攻を信じなかったのか
ア 起きては困ることは起きない
スターリンがドイツ侵攻を信じなかった最大の理由は、「起きては困ることは起きないと信じ込む」というスターリンの性格的な欠陥であるとされることが多い。また、他人の言うことを信じないため、下の者もきちんと説明しようとせず、情報が適切に利用されないという組織的な欠陥もあっただろう。
確かに、粛清の影響で当時のソ連軍は作戦能力・指揮能力が低下し、恐怖政治のために現場の志気や兵士の自発性も低下していた。このような状況で、ドイツ軍に攻撃されては困るのである。だから、「起きては困ることは起きない」と思い込んでしまったという面も否定はできない。
イ スターリンがドイツ侵攻はないと考えたことに合理性がなかったわけではない
しかし、私自身は、このような考え方とはやや異なる考え方をしている。当時の知識で合理的に考えれば、ドイツ軍がソ連に侵攻してくることなどあり得ないのである。そもそもドイツは準備不足のまま英仏との戦争に突入した面がある。ドイツ海軍の艦隊の整備は計画途上にあった。英仏両国の宣戦布告をうけたとき、ヒトラーは海軍大臣のレーダに「どうする?」と言ったという。大型の戦闘艦(戦艦、巡洋艦)は揃いつつあったが、肝心の空母が建造されていないのである。Uボートの数も少なく、駆逐艦の数も十分とは言えなかった。英国に対する航空決戦に敗北した状況で、さらにソ連という新たな敵を増やすなどとは考えられないのである。
第二次世界大戦で枢軸国の敗北を決定的にしたのは、ドイツのソ連侵攻と日本の真珠湾攻撃と米国の核開発の3つだといってよい。ドイツが形の上では友好国だったソ連を連合国の側においやり、形の上では中立国だったアメリカを日本が戦争に引きずり込んだ。そして、すでに戦いの趨勢は定まった後ではあった(※1)が、最後に米国の核開発が決定的な影響を与えた。核の使用が枢軸国最後の国家となった日本の敗北を若干ではあるが早めた(※2)のである。
※1 その意味では米国の核開発は間に合わなかったといってよい。彼らは、戦争を早期に集結するためではなく、たんに①戦後におけるソ連との立場を優位にするため、②核兵器の効果を実際の都市と市民に対して試すため、③莫大な開発費用が無駄ではなかったと米国民に説明するためなどの理由で核兵器を用いたのである。これは当時の国際法に照らして犯罪行為だとする説も強く主張されている。戦争を早期に終わらせるのであれば、日本の指導者に"国体の護持"を約束するだけでことは足りただろう。
※2 敗戦を決定した御前会議では、長崎への新型爆弾の投下とソ連軍の満州侵攻の報が入った段階で、最終的に天皇が"このままでは米軍の本土上陸がある"という理由で敗戦を決したとされている。日本が敗北を決定したのは、必ずしも原子爆弾だけではなかった。
ウ ヒトラーのソ連侵攻は愚かな行為であった
歴史にイフは許されないが、形の上とはいえ友好国だったソ連にドイツ軍が侵攻していなければ、その後の状況はどうなっただろうか。もちろん、ソ連がドイツを攻撃しないという前提ではあるが、簡単に予測してみよう。
まず、ドイツには英国に侵攻する能力はなかっただろう(※)。だが、補給の問題が解決すればではあるが、北アフリカからロンメル指揮下のDAKが中東の石油地帯を占領する可能性も、なかったわけではない。
※ ドイツは最終的にバトル・オブ・ブリテン(英本土航空決戦)に敗北している。制空権を確保できない限り、あしか作戦(英本土上陸作戦)は不可能だっただろう。また、英本土上陸のために必要な船舶も不足していた。
そして、米国は最後まで参戦しなかった可能性があり、その場合、Uボート群でイギリスの周辺海域の通商破壊を徹底することにより、英国と有利な条件で和平を結ぶ可能性もあっただろう。
そのような可能性があるにもかかわらず、超大国のソ連と戦うことは、ドイツにとってもリスクの高い危険なかけである。先述したように、西部での戦争を遂行する上で、ソ連からかなりの恩恵も受けていたのである。すなわち、ヒトラーが合理的な判断をする能力があるなら、ソ連への侵攻はあるはずがないのである。
そのように考えると、スターリンがドイツの侵攻を信じなかったことも、まったくの妄想というわけではないだろう。
エ しかし現実を直視しなかったスターリンの罪は大きい
ただ、いかに偽装していたとはいえ、さすがにドイツ軍がソ連国境付近に大規模に布陣していることは隠しようもない。もちろんスターリンもそれは知っている。では、ソ連国境付近に集結しているドイツ軍はなんのためにそこにいるとスターリンは思ったのだろうか・・・。
実は、ドイツは、ソ連国境付近のドイツ軍は、英本土上陸作戦を隠すための陽動作戦だというニセの情報を流していたのである。例えば、宣伝相のゲッペルスは、個人的な機関誌"ディア・アングリフ"に英本土上陸作戦が近いことを匂わせるような記事を書いている。もちろん、明確な書き方はしていない。そして、発売日に書店に並んだ数時間後に回収する措置をとった。外国人特派員やスパイたちがそれを目にできるだけの時間的な余裕はおいている。すなわちドイツは、英本土上陸をしようとしているが、それを英国に知られたくないために情報統制をしていると装ったのである。
また、ヒトラーは冗談で「最高機密として英本土上陸作戦をムソリーニに知らせてやろうか」などと言っていたといわれる。同盟国のイタリアに機密情報を管理する能力がないことは、よく分かっていた。イタリアに知らせてやれば、ソ連まで伝わるだろうというわけだ。
オ スターリンはヒトラーの西部戦線での勝利に幻想を抱いていた
スターリンは、ドイツ軍がソ連国境付近に集結しているのを、英本土上陸作戦を隠すための陽動作戦だと信じたようである。そう、ドイツと英国が争いあって疲弊してくれる方が都合がよいのである。都合の良い方へ信じたという面はあるだろう。ことによると、周囲にスターリンの考え方に迎合する者もいたかもしれない。
ヒトラーがソ連侵攻を意図していないとすれば、ヒトラーを刺激することは避けなければならない。下手に刺激して、ソ連がドイツに侵攻する意図があると思われて、それならやられる前に先制攻撃をしてやろうと思われても困るのである。
話はやや遡るが、独ソ不可侵条約を締結した後のパーティのとき、ソ連側の人間が乾杯をしようとして、両国の永遠の友情(フロイントシャフト)というべきところを"誤って"、敵意(ファイントシャフト)と言いかけ、すぐににやりと笑って"フライントシャフト(※)"と言い直したことがある。
※ パウル・カレルによると、友情(Freundschaft)というべきところを、本音が出たというわけでもあるまいが、敵意(Feindschaft)と言い誤ったので、FeindschaftのFとeindの間に"r"を挿入してFreindschftと言い直したのである。もちろん、こんな単語はない。それまでの独ソの関係を考えると、かなりきわどいジョークである。
もちろん、独ソ両国ともにこやかに乾杯をしたものだが、独ソの間はこんなジョークが出るような微妙な関係だったのである。もちろん、ヒトラーもスターリンもお互いを信じてはいなかっただろう。
だが、お互いに、相手側は自分(相手側)にとって利益になる行為をとるだろうとは考えていただろう。スターリンにしてみれば、ソ連にその時点で侵攻することはドイツの利益にならないはずだったのである。
ところが、結果的にヒトラーは侵攻することが自国の利益になると考えた。もちろん、それが正しかったかどうかは別な問題ではある。そして、スターリンはそこを見誤ったのである。その報いは大きかった。
だが、それは本当に避けることはできなかったのだろうか。避けることができたのだとしたら、その点にこそ学ぶべき点はあるだろう。
(3)ここから何を学ぶべきか
緒戦の敗北の原因は以下のような点にまとめることができよう。
【独ソ戦緒戦の敗北の要因】
- ① スターリンが猜疑心の塊となって、有能な高級将校を粛清したため、ドイツ軍の攻撃を受けたとき、反撃のための作戦を、現場が建てることができなかったこと。
- ② ドイツ軍の侵攻の兆候があったにも拘らず、ドイツを刺激することを避けるために対独戦の準備を怠ったこと。そのために、奇襲を受けて現場が大混乱に陥ったのである。
- ③ 現場の意見を吸い上げない組織になっており、スターリンの無意味な死守命令のため、貴重な兵力が前線に張り付いている間に包囲殲滅されてしまったこと。
- ④ 戦車の設計に当たって、現場の知識が反映されていなかったために、上司の気に入られるような性能ばかりを向上させ、実際の戦闘時に能力を発揮することができなかったこと。
このうち、現代の企業にとっても学ぶべきことは、②から④であろう。
ア 常識を疑うことも必要
(ア)様々な考え方を検討できない組織は危うい
②については、「合理的に考えればあるはずがない」ことから、明白な証拠となる情報を否定してしまったことが問題なのである。ゾルゲの情報にはニュースソースが書かれていなかったかもしれない(※)が、ソ連は大使館を東京に置いていた。当然、すべての大使館員に特高の見張りが付いていただろうが、ゾルゲがドイツ大使館に入り込んでいたことくらいは分かったはずである。
※ 発信源を特定されないようにするため、長文の電報を打つことはできなかった。なお、ゾルゲの電文は、現在では一部公開されている。
公開された情報を集めて、互いに照らし合わせていけば、かなりのことが分かるものなのである。もちろんゾルゲと接触するわけにはいかないだろうが、独軍のソ連侵攻という国家存亡にかかわるような情報を得たのである。多少のリスクは犯してもその情報の正確性を調べてみることはするべきだろう。それをスターリンによってたわごとだと決めつけられて、顧みられなかったのが最大の問題なのである。
すなわち、常識的では正しそうな方向で考え方が固まったときに、他の情報をばかばかしいと考えて、そこに目がいかなくなることが問題なのである。くだらない、なにをばかな、というわけだ。
(イ)部下の経験や知識を活かせない管理職
現代の企業でも、管理職などで、自分の経験から、自分が正しいと思い込んで部下の意見に耳を貸さない人間がいるものだ。確かに、彼は部下に比べれば経験は豊富なのだろう。
しかし、経験に従っていればよいという時代は過ぎ去っている。とりわけ最近のように、幅広い知識が必要な時代には、部下の方がよりよい情報を持っていることがないとは限らないのである。
こういう管理職は、業務の方向を誤りばかりか、優秀な部下や若い職員をつぶしてしまいかねないのである。部下や若い職員に対して、俺はお前よりも優秀なのだという態度をとる管理職は、会社にとってきわめて有害なのだということを、会社も理解する必要があろう。
このようなことを言うと、そのようなことはあまりにもばかげており、我が国の企業ではあり得ないと思われるかもしれない。しかし、このようなことは現代の日本の企業でも起きているのである。
(ウ)福島第一の事故は管理職が部下の考えを無視したことも一因だった
いわく「5.7メートル以上の津波はこないものと想定する」、いわく「全電源喪失は起きるはずがない」、いわく「我が国の原発ではメルトダウンなど起きるはずがない」。なぜなら、政府がそのように決めたからだ・・・。だが、すべて起きた。
図書館へ行って、郷土の歴史コーナーで有史以降の災害について調べるだけでも過去に5.7メートルより高い津波が来たことがあるという事実は簡単に分かっただろう。そして、想定を大きく超える津波が来れば地下に設置されている自家発電装置が機能を失うことは、電気について基本的な知識があれば誰にでも分かることであろう。そして、そのことを指摘した社員もいたという報道もある。ところが、そのような情報はなぜか顧みられなかったのである。
(エ)部下の知識を活かせない管理職は多い
また、数年前のことだが、ある企業で若い職員が、上司がWEBサイトのSEO対策(※)の重要性を理解してくれないと言ってやる気を失いかけていた。さすがに最近ではこのようなことはないだろうが、当時のこの上司はSEO対策などという聞いたこともないことについて、部下の持っている豊富な情報を使いこなすことができなかったのである。
※ サーチエンジン最適化のこと。誤解を恐れずに実質的な定義をすれば、Googleの検索順位を上位に持ってくるための手法である。一般消費者を直接の顧客としている中堅の企業にとってSEO対策に成功するかどうかが企業の命運を決すると言ってよい。
(オ)現在の平穏な状況はいつまでも続かない
我々は、無意識のうちに、ある平穏な状態を想定して、それを疑うことをしないという愚を犯してはいないだろうか。
ひとつの例を挙げれば、かつては、土地を購入すれば価格が下がることはないと信じられていた。そして、その信念に基づいて土地を購入して人生設計を立てた人も大勢いた。だが、今となってしまえば、少子化で人口が減り、これにデフレが重なれば土地の価格が下がるということは、だれも疑うことのない真理となっている。
ドイツはソ連に侵攻してこない、日本軍がハワイを襲うことなどできるわけがない、SEO対策などで企業の業績が変わるわけがない、土地の価格が下がるわけがない・・・というわけだ。
(カ)リスクアセスメントを効果的に勧めるために
最近、労働安全衛生の分野においてもリスクアセスメントが行われることが多い。ここでも、スターリンが犯した誤りを犯してはいないだろうか。重要なリスクについて、無意識のうちに、またはあえて無視して、解決できるリスクだけをアセスメントしてはいないだろうか。これではリスクアセスメントをする意味がないが、実は意外に多くの企業でこうしたリスクアセスメントが行われているのである。
会社の首脳がリスクアセスメントについての深い知識もなく、現場に実施を押し付ける。すると、現場では、とにかくリスクアセスメントをしなければならないので、起きそうにもないような災害のシナリオを無理やりに想定して、いささか非現実的な算定方法でリスクを算定し、対策はまあできる範囲でやろう、というリスクアセスメントをしてお茶を濁しているのである。
現実に重大なリスクがなければ、それでも実害はないのだが、実際には、危険なリスクがあるにもかかわらず、そちらの方は無視されているのである。
イ 現場からの情報を取り上げることも重要
(ア)スターリンの偏狭な性格が独ソ戦を困難なものにした
また、無意味な死守命令のために、貴重な兵力が無意味に殲滅されたことも重大な問題であった。後にジューコフが行い、中国では蒋介石や毛沢東が行っていたように、有力な敵とはぶつからずに退却するようにしていれば、かなりの部隊が温存できたはずである。これを緒戦で全滅させてしまったことは、その後の独ソ戦の進展に大きく悪影響を与えたことは間違いないだろう。
この死守命令の弊害は、現場にはよく分かっていたはずである。たんなる精神主義のために、貴重な戦力がむざむざと失われたのである。かつて日本軍でも航空機のパイロットがパラシュートを積まずに戦闘に赴くことがままあった。これは、きわめてばかげたことである。本人が勇敢かどうかなどということではなく、軍事目的の存亡にかかわるのである。
(イ)部下を大切にすることが戦争遂行にも必要だった
第二次大戦中の欧米各国の熟練したパイロットは、何度か撃墜された経験を持つ者が多い。英本土航空決戦では、英軍のパイロットは撃墜されてもパラシュートで脱出して、数日後には再び飛び立っていた。一方のドイツ空軍のパイロットは脱出しても捕虜になるしかない。このことも英軍勝利の一因だったと言われる。
「無駄に死ぬな、無駄に部下を死なすな」これは戦争に勝利するためにはきわめて重要なことである。確かに、ちょっと考えると、戦争に勝ちたければ、兵士に対して「死を恐れるな」「逃げるな」というべきだと思えるかもしれない。確かに、個々の戦闘においては、そう言わざるを得ない状況もあるだろう。しかし、近代戦に勝ち残るために必要なことは、実は、「死ぬな」「生き残れ」ということなのだ。生きていれば、戦うことができるからである。ところがそのことをスターリンは理解できなかったのだ。
(ウ)ドイツ軍は友軍を見捨てないことが伝統だった
そして、自軍を無駄に消耗してはならないということは、近代戦の専門家の軍人たちには分かっていることなのだ。ドイツ軍は、伝統的に、味方が包囲されたり困難に陥ったりすると、なにがなんでも助け出そうとする。海軍でも味方の艦が沈没すると、戦闘中でも周囲の艦が生存者の救助に赴くことがある。これに反する行動をとることは軍人として批判の対象となった。
兵士たちもそれが分かっているから、包囲されたりしても簡単には降伏しないのである。後のスターリングラードにおいて、パウルスの第8軍が絶望的な状況になっても簡単には降伏しなかったのもこのドイツ軍の伝統があるからだと指摘する識者も多い。
日本軍も大戦末期になると特攻作戦を採用したが、実を言えば、特攻には、当時すでに時代遅れになっていたゼロ戦やさらに性能の低い練習機を用い、パイロットも練度の低い予科練生を乗せていたのである。性能の高い紫電改や、練度の高い古参のパイロットは本土決戦に備えて温存していたというのが本当のところであった。
(エ)スターリンには何も見えていなかった
ところが、スターリンの猜疑心が強いことは、将軍たちもよく分かっているから、当時のソ連の高級将官たちは意見を上げようとしなかったのである。誰も粛清されたくはないのだ。
これが、スターリンが犯した過ちの大きな要素である。結局は、他人の知識を活用することができなかったのである。このことこそが、ここでもスターリンの大きな過ちだったのである。
(オ)現場を知ることの大切さと困難さ
現代の企業運営においても、もっとも大切なことは、職員を大切にし、その能力を活用することである。スターリンは独ソ戦においてその2つともにできなかった。また、無意味な死守命令によって、多くの将兵を無意味に死なせた。そして、それがソ連の存亡に関わりかねないことを、緒戦においては部下から知ることもできなかったのである。
もちろん、だからといって現場の情報を得ることもまた、簡単ではないということは知っておいた方がよい。組織のトップがLINEやTwitterで現場の職員や、若い職員とつながって、現場や末端の支持を得ているなどと考えているとしたら、ほとんどの場合はナンセンスである。いったい現場や若い職員の誰がトップに対して、本音でものを言うというのか。まして、トップが他人の言うことをきかない人物だという噂でもあればなおさらであろう。
現場の本音を知るには、かなりの努力を必要とするのだということは理解しておいた方がよい。
4 ゾルゲはなぜ必要な注意を払わなかったのか
(1)危険への慣れのこわさ
ア ゾルゲ諜報団の不注意は突出していた
さて、ゾルゲもまたかなりの不注意によって、日本の捜査当局に逮捕されたと思われるのである。常識的に考えても、当時の欧州各国や米国にもソ連のスパイたちはいただろう。しかし、大戦中に捜査当局に逮捕されたソ連のスパイというのは、他には聞いたことがない(※)。しかも、ソ連と交戦中のドイツではなく、形の上とはいえ友好国だった日本にいて逮捕されたのである。
※ 戦後になってからだと、米国では、ソ連のスパイとしてローゼンバーグ夫妻が逮捕されて、後に処刑されている。他にも戦後にソ連のスパイであるとされたり、自らスパイだと名乗ったりした人物もいないわけではない。
先述したように、捜査の端緒は宮城が北林と接触したことだとされているのだが、これは、ほとんど理解困難なほど不注意な行為である。映画「スパイゾルゲ」では、宮城は、広島でゼロ戦の訓練を観察したり、肖像画のモデルの軍人から情報を得たりしている。しかし、諜報団の最大の情報源はドイツ大使館である。そして、尾崎の政財界とのつながりからの情報がそれに次いでいた(※)。果たして宮城の情報がどれだけ役立っていたかは未知数である。
※ 尾崎はゾルゲに対して情報を伝えたというよりも、その知識を用いて、日本の軍人や政治家たちの思考についてゾルゲに教示したという役割の方が大きかったようだ。
他に日本政府の重要な情報を得る手段があったにも拘らず、なぜ、諜報に関する特別な訓練を受けていたわけでもなければ、政府の情報を知り得る立場にいたわけでもない、素人の宮城にこのような活動を行わせたのだろうか。
イ ゾルゲ諜報団検挙の端緒は
先述したが、尾崎秀樹氏によると、伊藤律が当局に北林のことについて話したため、北林から宮城が浮かび、そこから諜報団の活動の全貌が発覚したとされている(※1)。映画スパイゾルゲでは、マックスによるソ連への無線通信が、当局に探知されているが、発信源や内容を特定するには至らなかった(※2)と描かれている。これは史実のようだ。
※1 捜査当局の公式記録もそうなっている。もちろん、捜査当局が他のスパイの存在を隠すために、伊藤の発言から北林について知ったのだと装った可能性もなくはない。しかし、だからといって、北林が米国共産党員であることは当局も察知しており、マークはしていた(宮城も同様だった)のであるから、あえて伊藤を裏切り者に仕立て上げる必要はないだろう。
※2 マックスは発信源を察知されないようにするため、真空管などを入手して携帯できる無線機を自作し、通信のたびに場所を変えていた。また内容を暗号化していたことはもちろんである。
いずれにせよ北林=宮城ルートから調査団の全貌を捜査当局が把握することとなったことは事実であろう。ゾルゲも尾崎も捜査当局に疑われるようなことはしていないのである。映画ではゾルゲが、誰もいないときに大使の部屋のロッカーから機密情報を抜きだして写真に収めたりしているが、実際にはそのような形での情報収集はしていなかったし、する必要もなかったのだ。
ウ 危険に慣れることの怖さ
やはり、ゾルゲも危険に慣れてしまったということではなかろうか。危険な状況の下でも、平穏な状況が続けば、人はその状況がいつまでも続くと思うものなのである。ダモクレスの剣の下にいたからといって、いつまでも落ちてこなければ、これからも落ちてこないと思うものなのである。
ホテルなどの火災事故では、避難のための誘導をおこなうときに、パニックを恐れて"危険はないが念のために非難して欲しい"などと案内して、被害を大きくする例が多いといわれる。実際には、人は簡単にはパニックなど起こさないものなのである。それよりも緊迫感を伝えることの方が難しいのだ。
タイタニック事件でも、氷山との接触後しばらくは、乗客を救命ボートに乗せることに苦労したと伝えられる。緊迫感が伝わらなかったからである。
現代でも、日本で生きていれば、いつ大地震に遭うかは分からない。海辺にいれば大津波に襲われることもある。近くに噴火記録のある火山(※)があれば、いつ噴火するかは分からない。それでも、理屈の上ではそれらを理解はしていても、生活上の感覚として、大地震が来たり、津波が来たり、火山が噴火したりするとは思わないものだろう。
※ 現在では、かつての死火山、休火山という区分は用いられない。今後、噴火記録のある火山や噴火の恐れのある火山は、すべて活火山という区分がされる。
(2)私の経験から(ある工場のリスクについて)
私が労働省でまだ若かったころ、ある事業場で巨大な変圧器の破裂板(※)の下に、電気工事関係の作業者の詰め所の小屋があるのを見たことがある。破裂板の下に小屋を置くのは危険ではないかと企業の責任者の方に指摘したのだが、その方は「あれは何かが出てくるようなものではありませんよ」といって、私の指摘を一蹴した。
※ 放圧装置の一種である。短絡事故などで、変圧器内部の絶縁湯が気化して高圧となったときなどに、破裂して圧力を逃がす装置である。
おそらく破裂板の役割を知らなかったか、知っていても通常は、何も出てこないという趣旨だったのだろう。私も、若い頃で、それ以上のことは言えなかったのだが、その後、かなり長い間、気になっていた。
確かに何もなければ変圧器の破裂板が破裂するようなことはないし、大型の変圧器の破裂板が破損するような事故というのは、まず起きることはない。従って、責任者の方が言うように、現実に事故になるようなことはないだろう。そして、その事業場では、破裂板の下のスペースが空いていたから(たぶん変電設備の設計者が空けておいたのだろうが)そこに小屋を建てたというだけのことなのだろう。
しかし、やはり破裂板は破裂板である。内部が高圧となったときに、高温の絶縁湯が一気に噴き出すように作られたものなのだ。いくらスペースが空いているからといって、そこに詰所の小屋を建てるという発想は何かがおかしいのではないだろうか。
仮に破裂板の下に詰所の小屋を設けることのリスクアセスメントを行うとしたらどうなるだろうか。実際に災害が発生すれば、災害による被害の大きさは"複数の死亡者"になるだろう。高温、高圧の絶縁湯がその蒸気と共に小屋に襲いかかれば、発生し得る最大の被害を考えればそのようになる。そして発生の頻度は"可能性がある"としか言いようがない。可能性がないのなら、破裂板など設置する必要はないのだ。
だとすれば、リスクは低いという結論にはならないだろう。
しかも、その工場には、他にも小屋を建てることのできそうなスペースはいくらでもあったのである。にもかかわらず、あえてそこに小屋を建てたのは便利だったからなのだろうが、やはり不要なリスクは避けるべきであるという考えからはおかしい。
では、彼らはなぜそのような場所に詰所の小屋を建てたのだろうか。その理由は先述したように2つであろう。
- ① 破裂板の役割を知らなかった。
- ② 破裂板の破裂する頻度はきわめてまれなので、リスクは許容できると判断した。
私は、当初は、②が理由なのだろうと思っていた。破裂板の役割を知らないなどということはあり得ないと思っていたからだ。
だが、最近では、①と②の複合的なのかもしれないと思っている。確かに、電気技術者であれば、破裂板の役割が何かを知らないはずはない。だが専門家であれば、その発生する確率が低いということも知っている。だからほとんど気にすることもないのだろう。
一方、労働安全の担当者や、そこに小屋を建てることにかかわった事務部門の職員は、破裂板の意味など知らないと考える方が自然である。すなわち、破裂板の役割を知っている者は、それが実際に破裂する可能性が低いことを知っていて気にすることもなく、災害発生を防止すべき担当者はそれを知らないために気にすることもないということだ。
要は、以下の2点が問題なのである。
- ① 人はこれまで起きていない災害というのはこれからも起きないと思うものだということ。
- ② ある職員が知っている知識というものは、それを必要とする職員に対しても伝わりにくいということ。
残念なことに、大規模な災害が発生した後で、「なんでこんな危険なことをしたのだろう。こんなことをすれば事故が起こるのは分かるだろうに」と思うことはきわめて多い。その原因は、この2点が挙げられることがある。
あの大津波の後の全電源喪失の事例でも、大規模な津波が来る可能性があるということを知っていた職員はいるのである。一方、大規模な津波が来れば自家発電装置が全滅することは、自家発電装置のシステムについて知っている電気の専門家であれば誰でも分かったであろう。
組織の誰かは必要な知識を持っていたのである。にもかかわらず事故は発生してしまった。要は、危険に対する感性のマヒと、知識の共有化の失敗こそが原因なのである。
5 最後に
結局のところ、スターリンの失敗も、ゾルゲの失敗も基本的なところは、同じ原因に根差している。
そのときの平安な状態、スターリンの場合はドイツとのみせかけの友好であり、ゾルゲの場合は捜査当局に活動が発覚しないこと、これに慣れてしまい、その状態がいつまでも続くと思い込んだことである。
2つ目は、スターリンについては、現場や部下の知識を活用することについての失敗である。実は、自分の考えと異なる部下の知識を活用するということは極めて難しいことなのである。どうしても自分と考えの異なる部下の知識などは軽く見たくなるものである。また、部下もまた上司と異なる意見を述べることには抵抗を感じるものなのだ。
だが、これからの時代は、若い労働者や現場の感覚を活用できなければ、企業の未来がないという時代に来ている。そして、そのことはすべての企業の経営者は理解しているのである。
にもかかわらず、それが実践できている企業が少ないと思えるのもまた事実なのである。