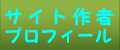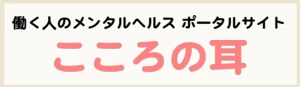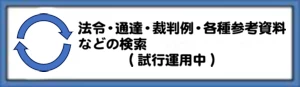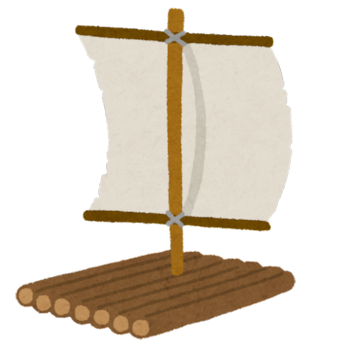
映画「アギーレ神の怒り」はヴェルナー・ヘルツォーク監督のドイツ映画です。
中世の南米大陸のスペイン軍で起きた反乱事件に取材した映画ですが、現代企業における労務管理(人事管理)の反面教師としても優れた映画です。
この映画を題材に、企業の人事管理の禁忌について論じています。
- 1 「アギーレ神の怒り」とは
- (1)岩波ホールの作品中、最も印象に残る映画
- (2)絶望的な状況における意志の強さか、たんなる狂気か
- 2 卑劣なピサロの問題点
- (1)全滅が予想される先遣隊を出したこと
- (2)人選について志願があったと嘘をついたこと
- (3)人選を誤ったこと
- 3 最後に
1 「アギーレ神の怒り」とは
執筆日時:
最終改訂:
(1)岩波ホールの作品中、最も印象に残る映画
「アギーレ神の怒り」は1972年公開のヴェルナー・ヘルツォーク監督のドイツ映画である。フランシス・コッポラ監督の地獄の黙示禄は、この映画に啓示を受けて作成されたといわれている。日本では1983年に岩波ホールでエキプ・ド・シネマの一環として公開されている。
私は映画が好きで、学生時代から結婚する 1989 年まで、岩波ホールで公開された映画は、ほとんどすべて観ている。もし、岩波ホールで観た映画のうちでもっとも印象に残っている映画を5本あげるとすれば、この映画は間違いなくそのひとつに入る。
【アギーレ神の怒りに見える差別と偏見】
しかしながら、この映画にはインカの先住民族に対する差別的な偏見が見え隠れするところがあることは指摘しておくべきだろう。
この映画では、先住民族の一部が食人種であるかのように描かれている。しかし、南米に食人種がいたという信頼できる記録はない(※)。そもそも、中世以降の食人種に関する記録などというのは、あったとしても憶測で書かれた偏見に満ちたものが多い。石器時代などを別にすれば、宗教的意味合いや、戦争で敵側を侮辱する目的による場合を除き、習慣として食人をする民族がいたという信頼できる記録はほとんどないといってよい。
※ 山本紀夫「ジャガイモとインカ帝国 文明を生んだ植物」(東京大学出版会 2004年)など
なお、インカ帝国が滅亡したのは16世紀のことで、当時の中国は明の時代ですでに"文明国"であったが、それ以前の時代では、三国志演義(時代背景は3世紀)や水滸伝(10世紀)ばかりか、正史である史記(前10世紀)や隋書(7世紀)などにさえ"食人"のシーンが出てくるのである。また、意外に思われるかもしれないが、礼を重んじたはずの孔子も、食人を肯定するかのごとき発言をしている(※)。
※ 国王の歓心を買うために、人肉料理を提供した者を、最高の料理人として称賛しているのである。
しかし、正史の記述はいずれも悪王によるものや、戦争などの極限状態におけるものである。また小説は、単なる作り事にすぎず、実際に食人行われたとする証拠にはならない。清代の紅楼夢(18世紀頃)にも登場人物が食人をネタにした冗談を言うシーンが随所にあり、日本人はやや違和感を受けるが、もちろん実際に食人が行われているわけではない。
いずれにせよ、このようなインカ文明などの先住民族に対する偏見は、この映画が作られた1972年頃には、欧米のみならず、日本にも広く存在していたのである。そして、日本の場合、現在においてもそのような偏見が払しょくされたとは言い切れない面がある。その意味で、このような映画を見るときには、十分に注意しなければならない問題である。
さて、岩波ホールの映画に話を戻そう。印象に残った映画のうち、他の4本の選択はかなり難しい。あえて挙げるとすれば、アンジェイ・ワイダ監督の"約束の土地"、ジャン・ルノワール監督の"大いなる幻影"、D・W・グリフィス監督の"イントレランス"、ウスマン・センベーヌ監督の"エミタイ"といったところだろうか(※)。
※ この他にもルキノ・ヴィスコンティ監督の"山猫(完全版)"、テオ・アンゲロプレス監督の"アレクサンダー大王"、グェン・ホン・セン監督の"無人の野"、アンジェイ・ワイダ監督の"ダントン"、小栗康平監督の"伽揶子のために"、村野鐵太郎監督の"国東物語"、ユーザン・パルシー監督の"マルチニックの少年"、謝晋監督の"芙蓉鎮"、サ タジット・レイ監督の"大地の歌3部作"なども捨てがたい。"大地の歌3部作"は一 挙上映されたが、それぞれが完結しているので、かえって個別に上映した方がよかったのではないかと思う。また、この他にも素晴らしい映画が上映されている。
なお、この5本については"大いなる幻影"と"イントレランス"を除けば、DVD などで閲覧することは、かなり困難だろうと思う。"エミタイ"に至っては、DVD 化されてすらいないようだ。
"アギーレ神の怒り"のストーリーはきわめて単純である。時代背景は、スペイン人がインカ帝国を滅亡させ、アマゾンの一帯を支配していた頃のことである。エル・ドラド(黄金郷)を探索する探検隊の隊長のゴンザロ・ピサロが、先遣隊にアマゾン川を下らせる。物語は、先遣隊の出発から、全滅までを描いている。
先遣隊の隊長のウルスアは途中で引き返そうとするが、副隊長のアギーレが謀反を起こしてウルスアを銃撃して逮捕し、貴族のグスマンを皇帝に押し立てて、エル・ドラド探索のためにさらに下流へ向けて筏を進めようとする。
しかし、先住民族による攻撃や食料不足によって部隊はアギーレを残して全滅し、アギーレはこの地に大帝国を打ち立てると誓いながら筏に乗って流されてゆく。
(2)絶望的な状況における意志の強さか、たんなる狂気か
ただ、これだけの単純なストーリーなのだが、アギーレを演じた個性的なクラウス・キンスキーの強烈な印象のため、ぐいぐいと映画の世界に引き込まれてゆく。映画の中では、脱走を企てる兵士が1、2・・と数を数えて"9"まできたところで、忍び寄ってきたアギーレの腹心にいきなり首を切られ、地に落ちた首が"10"と唱えるという、普通の感覚ではチープなブラックジョークに思えるような演出もしているのだが、こんな普通なら笑えるようなシーンが、映画を見ていたときは妙なリアリティを感じたものである。
映画の登場人物たちは、僅かな人員で、アギーレという強烈な個性のリーダーに支配され、原始的な筏に乗って、敵意を持つ先住民族が支配する河を下るということになる。
そして、先住民族の襲撃や仲間割れで、次々にメンバーが死んでゆく。まさに極限状態におかれるのだ。
その中で、まず、国王に仕立て上げられた、人は良いが無能なグスマンが精神に異状をきたす。大帝国の国王になれたと思い込んでしまうのだ。食料を独占したり、貴重な馬を筏から追い払ったりといった奇行によって、仲間から殺されてしまう。しかし、彼の異常な行動が精神に異常をきたしたためなのか、たんに幼稚な人格と無能のなせることなのかが、映画を観ているときには分からないのである。
映画の描く極限状況のもとで、正常でいられる者がいるとすればその者こそが異状なのかもしれない。異状が正常との区別がつかなくなるほど、観客にも極限的な状況が伝わってくるのである。
比較的、平常心を失っていないように見えるのは修道士のカルバハルだが、彼とても、敵意を持っていない先住民族を"聖書に敬意を払わなかった"という理由で殺害してしまう。激しい敵意を有する先住民族に囲まれているという状況の下で、味方になり得る先住民族を殺害するのである。これこそ異状としか言いようのない行為であろう。しかし、映画を観ているときは、不条理な残虐行為とは思えるのだが、異状とは感じられないのである。
最後のシーンで、一人だけ生き残ったアギーレが、自らが支配する帝国をこの土地に打ち立てるのだと、自らに言い聞かせるように誓う。もちろん、客観的にみれば、そのようなことはすでに不可能である。精神の平衡を失っているとしか思えず、むなしい妄執にすぎないのだが、映画を観ていたときは、アギーレの強烈な執念に共感を受けたものである。この男なら、本当にやってのけるのではないかとさえ思えるのである。
これを、絶望的な状況にあっても希望を捨てない強力な意志の強さと感じるのか、たんなるむなしい狂気にすぎないと感じるかは、観る者によって異なるだろう。私は、前者だった。
なお、大貫良夫の「黄金郷伝説」(講談社現代新書)によれば、史実では、アギーレは河口から海へ到達し、ある島に上陸して先住民族の一部を支配して彼の"帝国"を打ち立て、スペイン本国に対して叛旗を翻している。しかし、結局は部下に裏切られてスペイン軍の捕虜となり、最終的には処刑されている。
2 卑劣なピサロの問題点
なお、実を言えば、史実のアギーレが、エル・ドラドの探検隊のピサロ隊長から先遣隊の副長に任ぜられてアマゾンを下ったという事実はない。大貫の前掲書によると、アギーレが、上官だったウルスアを殺害してスペインに叛旗を翻したことは事実である。しかし、それはエル・ドラド探検の先遣隊における事件ではない。アマゾンを下って海へ出て島を占領したのは、反乱を起こした後の話である。
実は、この映画のストーリーの元になったモデルは他にあるようだ。大貫によると、エル・ドラドの探索隊の隊長をしていたピサロという人物が、分遣隊を組織してアマゾンを下らせたという史実はあったようだ。しかし、この分遣隊では反乱は起きず、海まで出て海岸伝いに本国まで帰還しており、全滅したという事実はない。
すなわち、この映画は、アギーレによる反乱事件と、ピサロによるエル・ドラド探検隊が分遣隊を出したことの2つの歴史的な事実をモデルにして、創作を加えて組み立てているようだ。もちろん、本稿は、あくまでも映画についての話である。
この映画については、さまざまな解釈が可能だろう。この悲劇的な事件の、表向きの最大の責任者はアギーレである。ストーリー上では、彼こそが最大の悪役とされている。
しかし、私には、この全滅事件の最大の原因は、ピサロにあるのではないかと思えるのである。映画ではピサロはたんなる端役にすぎない。だが、アギーレというよりも、先遣隊を組織するに当たってのピサロの卑劣さや誤りの方が、原因としては重大だったのではないかと思えるのだ。
以下にピサロの卑劣さと誤りの内容を挙げてみたい。これが本稿の主要なテーマとなる。
(1)全滅が予想される先遣隊を出したこと
ピサロは、先遣隊を組むに当たって、隊員の前で"先遣隊が1週間経っても戻らなければ全滅したものとみなす"と宣言している。すなわち、先遣隊は全滅する可能性があり、また全滅してもかまわないという、いわば"捨て駒"として組織されているのである。
戦時における戦闘中の軍隊であればこのようなことをせざるを得ないような場合もあるだろう。しかし、時代は戦時ですらなく平時なのである。しかも目的も"仲間の人名救助"というような、若干のリスクをとらざるを得ないようなものでもない。たんにエル・ドラドを発見するという、いわば経済的な利益目的にすぎないのである。しかも、仮にエル・ドラドを発見したとしても、多くの兵士にとっては、名誉や十分な報酬が約束されているわけでさえないのだ。
しかし、兵士たちの多くは優秀な者だったろう。先遣隊は、探検隊の成否を決するきわめて重要な役割である。目的を達するためにも、優秀な兵士を選んで編成したに違いないのである。しかし、兵士の立場に立ってみれば、優秀だからという理由で見返りのない危険な役目に就かされることになったのである。
これでは不満感が高まることは当然であろう。すなわち、組織化された最初から、隊員の兵士たちには絶望感や不安感ばかりでなく、強い不満感があったと考えられるのである。このような役回りをさせられた兵士たちは、スペイン国の名誉や国王の利益などより、どうすれば生き残れるかが重要だと感じられたことは当然だろう。
アギーレは、まさにそこを利用することで、先遣隊長のウルスアに対して反乱を企てることが可能となったのである。アギーレはたんに恐怖心だけで兵士を掌握しようとしたわけではない。兵士たちもまた、ウルスアとアギーレのどちらに左袒することで生き残ることができるかについて迷っていた。そして、アギーレとしても、兵士の多くが迷いつつも自分につく方がよいと判断すると見て取れたからこそ、ウルスアを撃つことができたのである。
もし、兵士の多くが、ピサロとスペイン国王に対する忠誠心を失っていなければ、いかにアギーレとはいえ反乱を起こす余地はなかっただろう。だが、ピサロは、自ら兵士たちの忠誠心を失ったのである。
最近は、企業においても M&A が盛んである。しかしながら、しばしば優秀な社員が、優秀だからという理由でリスクが高いにも拘わらず見返りの少ない仕事に就けさせられることがある。
これでは社員の中には不満が高まるだろう。だったら自己研鑽や努力をして能力や成績を上げるよりも、上司におべっかを使っている方がよいということになってしまう。そして、そのような不満が、長い目で見ると組織をおかしな方向へ向けてしまうのである。
(2)人選について志願があったと嘘をついたこと
ア ピサロの責任逃れ
また、ピサロは自ら人選をしたにもかかわらず、先遣隊に参加させた2人の女性について、本人が強い志願をしたからだと嘘をついている。なぜピサロが2人の女性を先遣隊に加わらせたかったのかは分からない。もしかすると、ウルスアとアギーレに慎重な行動をとらせるためなのかもしれない。2人の女性はウルスアとアギーレの関係者だからである。
女性の一人はウルスアの愛人のアティエンサで、もう一人はアギーレの愛娘である 15 歳のフローレスである。なお、この他にもアティエンサ付きのインディオの女性も参加させられている。
だが、アティエンサはともかく、フローレスは先遣隊に参加することを希望してはいない。フローレスは自らの意志で行動するタイプではないし、その参加をピサロが公表したとき、アギーレが驚いていることから見て取れる。もし、本当に志願したのだったら、アギーレが驚くはずはないだろう。
彼女たちについて、ピサロは、"自分は望まなかったが本人の志願だ"と言っている。これはきわめて卑劣な行為である。最悪の場合に、女性を危険な先遣隊に参加させたことの非難が、自らに及ぶことを避けたかったのであろう。
イ わが国の特攻隊と責任の所在
我が国においても数十年前に、同様な卑劣な行為がより大規模に行われたことがある。第二次世界大戦における神風特攻隊は、建前では志願制ということにされている。しかし、実質的には強制だった。例外的な場合を除けば、人選は軍が行ったのだ。軍による人選の後で、形式的に本人の意思を尋ねてはいるが、拒否することはできなかったのが実態だった。
志願制という形にしたのは、軍の上層部に責任や批判が及ぶことを避けるための措置である。軍の上層部は、第一線のパイロットたちに死を強要しておきながら、自らには責任が及ばないようにしたのだ。
彼らは、死に赴くパイロットたちに"自分たちも後から続く"と言って送り出しておきながら、ほとんどの者は後に続くことはなかった。自らは、生き残ったのである。戦後に政財界において功をなした者も多い。
宇垣纏は、終戦の詔書の放送後に特攻を敢行しているが、これは数少ない例外的なケースである。なお、宇垣については、死後に勲一等旭日大綬章が授与されている。しかしながら、豊田正義「妻と飛んだ特攻兵」によると、尉官クラスの軍人で、勅書の放送後に妻と共に特攻を敢行した者がいるが、彼らは軍機違反とされて戦死とさえ認められていないそうである(※)。
※ 豊田正義「妻と飛んだ特攻兵 8・19 満州、最後の特攻」(角川書店 2013年)による。なお、この他にも配偶者と共に特攻を敢行した者がいる。宇垣も含めて、彼らは幸か不幸か"戦果"を挙げたとする戦勝国側の記録はない。従って、"終戦後"に敵兵を殺害したという事実はないと考えてよい。
ピサロもそうしたように、このような"志願"や"自らの意志"はしばしば美談に仕立て上げられる。もちろん、私は、特攻に参加した兵士たち、個々の軍人の至誠を毫も疑うものではない。しかしながら、彼らの行為を美談に仕立て上げようとする者たちには限りないうさん臭さを感じるのである。
そもそも、勝ち目のない戦争に突入した者たちの責任はどうなるのか。彼らを特攻に向かわざるを得ないような戦況にした者たちの責任はどうなのか。さらには、このような非人間的なばかりか、戦術的にも効果の低い攻撃方法を採用した者たちの責任はどうなるのだろうか。
これを"美談"で終わらせてはならないのではなかろうか。特攻を美談に仕立て上げることは、これらの者の責任の追及を曖昧にしてしまうことになる。そして、責任者に対する責任の追及を曖昧にすることは、将来において同じ愚を繰り返すことにつながるのだ。
ウ "美談"を"美談"で終わらせてはならない
わが国は幸運なことに、第二次世界大戦後は直接の戦争当事国になることはなかった。しかし、大規模な災害や事故などでも、しばしば自己を犠牲にして他者を救うという"美談"が伝えられることがある。もちろん自己犠牲の当事者の行為は称賛されるべきである。しかしながら、本来は、"美談"などが起きなくても被害が出ないようにしておくべきなのである。
このような"美談"を美談で終わらせることは、責任の所在を曖昧にすることにつながりかねない。そればかりか、失敗に学ばず、同じ過ちを繰り返すこととなる原因ともなるのだ。
自己犠牲によって他者を救う人々を称賛することは正しいことだ。だが、"美談"を"美談"に終わらせてはならない。なぜ、彼らを自己犠牲に向かわせるような状況が起きたのかを明確にしなければならない。それこそが、自己犠牲によって亡くなった人々への鎮魂になるのではなかろうか。
(3)人選を誤ったこと
ア ウルスアとアギーレの組合せ
さて、先遣隊の人選においても、ピサロはいくつかの致命的な過ちを犯している。そのうち最も重大なものは、愛国心が強く沈着冷静だが、慎重すぎるウルスアを隊長とし、勇猛果敢で行動的なアギーレを副長にしたことである。このような組み合わせは現代の企業などのプロジェクトチームなどの組織でも多く見られることではある。
しかし、慎重派のトップが、行動派の副長を心酔させられればよいのだが、現実にはなかなかそのようなことにはならないのである。そればかりか、トップと副長の双方が、自分の方がより優秀だと考えており、それが態度に表れたりすると、さらに厄介なことになる。
また、比較的外部との接触の多い仕事だと軋轢はそれほど深刻化することはないのだが、外部との接触の機会の少ない仕事だと軋轢が深刻化することが多い。
そうなると、場合によっては、組織が2つに割れてしまうことさえある。これは、組織のメンバーのストレスを高めるだけでなく、組織の効率を低下させることにもなるのである。
これが平時であれば、まだ組織の沈滞化を招くだけで済むが、この映画のエル・ドラドの探検隊の先遣隊のような場合は、軋轢が深刻化して反乱にまで進んでしまうのである。
イ 貴族のグスマンの参加
また、貴族のグスマンを参加させているが、これは先遣隊がエル・ドラド発見という"偉業"に成功したときに、平民ではなく貴族にその栄光を追わせるための人選である。ところが、グスマンは育ちがよいからか、人は良いのだがストレスに耐えることができないのだ。
彼を先遣隊のメンバーに加えたことは、明らかな誤りである。映画でもアギーレに利用されて叛乱の責任者に仕立て上げられてしまう。これは、叛乱の責任をグスマンに押し付けることと、隊長のウルスアの処刑を彼の責任で行わせるためである。アギーレも氾濫や上司殺害の批判を受けることは避けたかったようだ。
それでも、形式的とはいえ国王という立場にあることを利用して、グスマンはウルスアの生命を助けることに成功する。だが、人の良い貴族のグスマンにできることは、そこまでが限界だった。形だけとはいえ、スペイン国王への叛乱の責任者となった精神的な重圧と、厳しい極限状況の中で精神に異状をきたし、広大で堅実な国家の国王になったのだと思い込んでしまうのである。
アギーレの傀儡とはいえ、形式的なリーダーが精神に異状きたしたことで、先遣隊はさらに危機的な状況に陥れられることになる。アギーレが怖くてグスマンに従っていた兵士たちの間にも、グスマンへの不満が高まり、結局は"臣下"に殺害されることで、彼は哀れな人生を閉じる。これは殺害犯(※)やグスマン本人が悪いというよりも、そもそもピサロが彼のようなストレスに弱い無能な人物を、危険が予想される先遣隊の任務に就けたことによって引き起こされたものというべきである。
※ 映画では犯人は明らかにされない。形式的で無能な国王の犯人探しなど、アギーレを含めて、隊員にとってはどうでもよいことだったのである。むしろほとんどの隊員は、犯人がグスマンを殺してくれたことを感謝していただろう。
ウ 修道士のカルバハルの参加
また、この先遣隊にはさらに目的にそぐわない人物が参加させられている。修道士のカルバハルである。ピサロとしては、探検隊の目的が、エル・ドラドの探索と先住民族への侵略にあるという本質を、彼の参加によって覆い隠したかったのであろう。
すなわち、当時の彼らにとっての"福音"であったキリスト教の宣教という"高邁"な目的のための探検であるという形式を整えたかったのである。そのためにカルバハルは参加させられたのだ。なお、この映画は、カルバハルによる日記を映画化したという形をとっており、ときどきカルバハルの日記の朗読がナレーション風に入っている。
カルバハルは、最初はウルスアに味方し、アティエンサからも頼りにされるのだが、アギーレの叛乱後は日和見主義に徹する。そのため、アティエンサは絶望し、自殺をするように先住民族のいる森の中に、単身で入ってゆく。少なくともカルバハルがこれを止めようとした形跡はない。
彼は、ほとんどなすところなく先遣隊に参加しているだけなのだが、敵意のない先住民族が接触してきたときに、重大な誤りを犯す。先住民族の男女がカヌーで筏に乗りつけたとき、彼らに聖書を渡すのだが、彼らがそれを床に投げると、聖書を汚したという理由で殺害してしまうのである。
結局、この先住民族の正体は分からないのだが、地域の先住民族の有力者だった可能性もあるだろう。もし、彼らを通して先住民族の一部族でも懐柔に成功していれば、その後の展開が大きく異なった可能性もあるのだ。
この先住民族が接触する前のことではあるが、河べりの村が燃えていたことがある。上陸するとスペイン人の死体ばかりでなく、スペイン兵のブーツや鎧が散乱しており、その村の住人には敵性があることが判る。しかし、村が燃えているのは、彼らの敵に襲われた可能性があるのだ。
すなわち、味方になり得る強力な先住民族の部族が付近にいた可能性があるのである。カルバハルに殺害された男女が、その部族の有力者だった可能性もあるのだ。それにもかかわらず、カルバハルの愚かな行為によって彼らを味方につける可能性を潰されてしまう。
友好的な先住民族を殺害したことは、上官であるアギーレにも責任はあるだろうが、やはりカルバハルという、他民族との接触の方法について理解していない人物を隊員にしたピサロにも問題があるというべきであろう。
3 最後に
ところで、この映画は、撮影についても、極限的な状況で行われたようだ。撮影は、実際にアマゾンで行われている。撮影現場では、キンスキーが現場で銃を発砲して監督のヘルツォークを激怒させたとか、キンスキーが撮影を降りたがったときにヘルツォークが銃で脅したなどという話が伝わっているが、事実かどうかを確認することはできなかった。
しかし、映画を観ていると、この撮影現場ならそのようなこともあったのではないかという気にはなる。実際に筏を組んで、アマゾンを下りながら撮影を行ったのだから、暑さ、湿度、直射日光といった厳しい自然環境にも苦しめられた。また、蚊や小さな昆虫にも悩まされ続けた。実際に映画でも、画面に羽虫が写っているシーンがいくつかある。
なにしろ CG 技術などなかった時代である。かなり危険な撮影も行っていたのであろう。冒頭で、山道を大部隊が移動するシーンでは、大砲の部品が墜落して爆発するカットがある。山道といっても、崖についている突起のような道である。いつ俳優が墜落しても不思議ではないような道だ。ここを、女性の乗った駕籠を捕虜の先住民族役のエキストラに担いで運ばせている。撮影時には駕籠自体は空だっただろうが、かなり危険な状態である。
筏で河を下っているとき、火薬の詰まった樽に焚火の火が燃え移ったため、アギーレが筏の外に投げ捨てると、筏の近くで爆発するシーンがある。さすがに撮影で投げ捨てられる樽には火薬は入っていなかったろうが、火はついているのだ。また、爆発するカットも筏のすぐ近くで火薬を爆発させて撮影しているのであろう。筏に乗っていれば恐怖を感じただろうと思う。
また、筏の上で大砲を数発、続けさまに撃つシーンがある。弾が出ているようには見えないので、空砲を撃っているのであろうが、いくら空砲とはいえ、至近距離で大砲を撃てば空気の振動で、耳にかなりの痛みを感じるはずである。ちなみに第二次世界大戦中の戦艦は、主砲を撃つときには、甲板から兵士たちを非難させている。振動で吹き飛ばされてしまうからだ。
このように、撮影そのものが、かなりの極限状況だっただろうと思えるのである。それが画面の中の兵士たちの表情に表れている。
ヘルツォークとキンスキーはこの映画の後でも、コンビを組んで、「フィツカラルド」(1982 年)と「コブラ・ヴェルデ」(1987 年)を作成しているが、「アギーレ/神の怒り」には及んでいないような気がする。