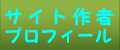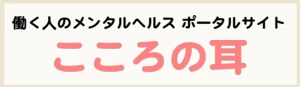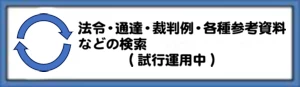※ イメージ図(©photoAC)
労働者が仕事とは関係なく心の健康問題を起こして、それまでの仕事ができなくなり、その企業で就かせることができる他の仕事もない場合、どのように対応するべきでしょうか。
会社と労働者の雇用契約の骨幹は、労働者が働くことと引き換えに賃金を支払うことです。従って、その労働者が、その企業で考え得るどのような仕事もできなくなり、しかも回復の見込みがないのであれば、会社を辞めて頂くしかありません。そこから先は、国の福祉事業の役割です。
しかしながら、労働者の解雇には、様々な公法上・私法上の制限があります。仕事ができなくなったとしても、簡単に辞めさせることはできません。また、必要な手続きを踏まない解雇は、他の労働者のモラール(就業意欲)に影響を与えるばかりか、ときには社会的な批判を浴びることにもなりかねません。
辞めさせる以外の方法がないのか、また解雇とするのか普通退職とするべきなのか、解雇の手続きはどのようにするべきかについて解説します。
- 1 本人が辞めるという意思表示をする場合
- (1)本人の辞意の法的な有効性と産業医の立場
- (2)退職勧奨は許されるか
- 2 解雇
- (1)解雇に関する一般的な考え方
- (2)病気休職制度がない場合
- 3 休職制度と解雇
- (1)休職してもその期間内に回復の見込みがない場合
- (2)最長保障期間経過後の取扱い
- (3)休業期間の通算とクーリング
- 4 最後に
1 本人が辞めるという意思表示をする場合
執筆日時:
(1)本人の辞意の法的な有効性と産業医の立場

※ イメージ図(©photoAC)
労働者が心の健康問題に罹患(※)して、それまでの仕事ができなくなることがある。このような場合、どのような対応をするべきだろうか
※ 本稿の心の健康問題は、業務上の疾病ではないことが前提である。
まず、労働者の側から自由な意思で任意に退職したいと表明するのであれば、その辞意のきっかけが会社に促されたことにあるのか、本人の自発的なものかによらず、雇用契約が終了することに法的な問題はない(※)。
※ いったん、辞表を提出してしまえば、使用者の側が認めない限り、労働者の側から一方的に撤回することはできない。その当時の意思能力がなかったことを理由に無効と認められる場合(民法第3条の2)もあるが、過去の判例ではそれが認められるケースはかなり限定されているのが実態である。
とは言え、後になって本人が「辞意は心の健康問題によるもので無効だ」と訴える可能性はある。会社としても、この種の訴えを受けることで会社の対外的なイメージに影響を与えることがある。法的な評価として問題はないとしても、こころの健康問題を抱える労働者の辞意を受け入れることには、慎重な対応が望まれる。
しかし、心の健康問題に罹患しているときに退職などの重大な決定をすることは、筆者としては避けるべきだと考えている。また、産業医は企業からは独立した存在であり、本人に対して辞意を保留することを勧めたとしても企業に対する背任にはならない(※)だろう。
※ 現実には、会社が本人に対して退職を勧奨しているような場合、産業医としては難しい立場となる。しかし、産業医としての立場を貫くべきであろう。
(2)退職勧奨は許されるか

※ イメージ図(©photoAC)
また、会社側が本人に対して辞職を促す「退職勧奨」を行い、本人がこれを受け入れれば、雇用関係は終了する。その退職勧奨が社会通念上、違法なものでなければ、退職勧奨を行うことそれ自体に、とくに法的な問題はない。
しかし、退職勧奨が、社会通念から外れるほど、あまりに執拗又は強引に行われたのであれば、そのこと自体が違法性を帯びることがある。そのような場合、雇用関係の終了の合意という法律行為は取消し(民法第 96 条)の対象となり、退職勧奨という事実行為は不法行為(民法第709条以下)となって、損害賠償の対象となることもあり得よう(※)。
※ 最1小判昭和55年7月10日(下関商業高校事件)は、初回の退職勧奨から一貫して応じないと表明しているにもかかわらず、事業者側の職員から執拗に退職を勧奨されたことから、違法な退職勧奨により精神的な損害を被ったとして損害賠償を認めた。なお、東京高判平成24年11月29日(日本航空事件)、京都地判平成26年2月27日(エム・シー・アンド・ピー事件)、東京高判平成8年3月27日(エール・フランス事件)なども退職勧奨についての慰謝料を認めている。
退職勧奨が許されないというわけではないが、あまりに強硬又は長期にわたって行うことは避けなければならない(※)。
※ 仮に隠したとしても、他の労働者は会社による退職勧奨の扱いを必ず知ることになる。それが、他の労働者のモラール(就業意欲)にどのような影響を与えるかについても考えなければならない。
2 解雇
(1)解雇に関する一般的な考え方

※ イメージ図(©photoAC)
現実には、本人としても生活があり、簡単に辞めることはできないことが多いだろう。そうなると、労働契約法第 16 条の趣旨からも、疾病に罹患したために働けない(※)という理由で、簡単に解雇又は退職処分とすることはできないことに留意するべきである。
※ 疾病に罹患したという理由だけで解雇することはできない。それが業務に起因していれば、一定の要件を満たさない限り解雇できないことは当然である。そうでなくても、解雇するにはあくまでも「働けない」「異常な行動をとる」などの雇用を続けることができない合理的な理由が必要である。
さらに、現実には、合理的な理由があるように思えても、一方的に解雇することは簡単ではない。最2小判平成24年4月27日(うつ病解雇事件)は、労働者が40日間の無断欠勤をして会社が解雇したケースで解雇の有効性が争われた事件だが、無断欠勤の原因が会社対応に不備があったことが大きいとされて解雇は無効とされている。その労働者が社内でいじめを受けたとして会社に調査と休職を求めたにもかかわらず、会社側が適切に対処しなかったとされたことが、理由であった。
【労働契約法】
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
判例では、疾病を解雇することの有効性は、その労働者が職種を限定して雇用されているのか、職種を限定せずに雇用されているのか(※)によって、取り扱いが異なる。
※ 日本国内では、職種を限定した雇用契約は多くない。例えば、高級フランス料理店がフランス料理の料理人を雇用するようなケースである。一方、学卒者の新規採用などは、ほとんどの場合、職種が限定されていないと考えられる。
これについては、三柴が次のようにまとめているのが参考となる。
この点にかかる判例法理は、おおむね、労働者の労働契約が、①職種非限定契約と解される場合、②職種限定契約と解される場合、の2種類に応じて形成されて来ており、代表的な裁判例としては、①につき、片山組事件最1小判平成10年4月9日・労働判例736号15頁(推定私傷病事案)、東海旅客鉄道(退職)事件大阪地判平成11年10月4日・労働判例771号25頁(私傷病事案)、北産機構事件札幌地判平成11年9月21日・労働判例769号20頁(私傷病事案)など、②につき、カントラ事件大阪高判平成14年6月19日・労働判例839号47頁(推定私傷病事案)などが挙げられる。
これらの判例が形成した法理を要約すると、以下のように言える。すなわち、②の場合、原則的には、当該職種に求められる健康状態、職業能力(職能)が回復しなければ、たとえ復職の申し出がなされても、債務の本旨に従った履行の提供があるとは認められず、従って、復帰を認める必要はない。但し、労働時間や職務内容につき、一定の軽減がなされたリハビリ勤務を経れば、2~3か月程度で当該職種に復帰できるような場合には、信義則上、かような経過勤務への復帰させる義務が使用者に課せられる。
他方、①の場合には、当該労働者の休職に至る事情、能力、経験、地位、企業の規模、業種、その労働者の配置の実状等、労使の双方にわたる様々な事情を考慮して配置可能性のある職種、ポストがあるのであれば、債務の本旨に従った履行の提供があるものとして、復帰させる義務が使用者に課される、と。
※ 三柴丈典「職場復帰支援のポイント~法学者の立場から~(心の健康詳説職場復帰支援の手引き 所収)」(中央労働災害防止協会2010年)
すなわち、職種を限定せずに雇用している場合には、職種転換が可能であれば、簡単に解雇できないと考えた方がよい。簡易な業務に従事させることができるのであれば、処遇(賃金)レベルは合理的な範囲で下げることは可能であるが、職種を変えて職を維持することが必要となる。
解雇するのであれば、他に可能な仕事がないことを証明できる場合に限定するべきである。
一方、職種を限定して雇用している場合に、職務を維持することが不可能で短期には回復が見込めないような場合には、雇用契約の解消することが可能ということになろう。
(2)病気休職制度がない場合
ア 休業させることの必要性

※ イメージ図(©photoAC)
休職制度がないために休職を経ていない場合で、解雇等となって争われるケースについての判例はほとんどない。しかし、休職後に労働者が復帰を希望した場合に、会社側がこれを認めずに解雇や退職扱いとして争われるケースの判例が数多く出されており、これらが参考となる。
病気休職制度があれば、とりあえずその制度を利用することが多いだろう。問題は休職制度がない場合である。休職制度そのものは法定の制度ではなく、必ず設けなければならないわけではない。従って、中小零細企業の場合、休職制度がないケースはあり得る。その場合、有給休暇の消化や、病気休暇などの制度があればそれによって、当面は対応することになろう。
また、休職制度がない場合であっても、有給休暇を使い切り、病気休暇制度の終了した時点で働けないからといって、ただちに解雇できるわけではない。一定の期間後に回復する見込みがあれば、解雇することはできないと考えた方がよい。
東京地判平成22年3月24日は、心身の故障のため職務の遂行に支障があるとの理由で解雇された中高一貫校の教員について、回復可能性の判断が「やや性急」であったとして無効(※)としている。
※ 解雇という法律行為は無効(従って解雇後の賃金の支払い義務もある)とし、さらに、解雇に関する一連の経緯についての事実行為について不法行為(民法第709条以下)として損害賠償請求を認めた。
休職制度がない場合にまで、休職をさせなければ解雇できないというわけではないが、休職を経ずに解雇するのであれば回復の見込みがないことを証明する必要があろう(※)。それができなければ、傷病手当金の支給される18箇月を無休のまま様子を見て、その後、解雇するという方法を取るのが無難であろう。なお、休業後の解雇については後述する。
※ 現実には主治医が回復できないという診断書を書くことは考えにくく、これを証明することは困難だろう。
イ 解雇予告の必要性
仮に解雇が有効な場合だったとしても、普通解雇(一方的な雇用契約の解除)とするべきか、普通退職(労使の合意の上の退職)とするべきかは問題となる(※)。
※ 解雇の場合、1か月の解雇予告または解雇手当が必要となる。しかしながら、現実に働いていないであろうから、有給休暇が残っていない限りあまり意味のある議論ではない。
現実には、労働者側が退職を望んでいないわけであるから、解雇としか考えられない。就業規則に「心身の故障で勤務ができない場合は解雇する」としてあるか「心身の故障で勤務ができない場合は退職するものとする」と定めてあるかによって、それほど大きな違いはない(※)。
※ これについは、休職明けについての取り扱いについての解説で後述する。
予定した休業期間の終了と同時に解雇予告を行い、そのまま30日間休業を延長してから解雇するべきである。
3 休職制度と解雇
(1)休職してもその期間内に回復の見込みがない場合
法律の実務者で、「私傷病が、休職をさせても休職の最長保障期間内に職場復帰が可能となるまで回復する見込みがない場合は、休職を認めない(ただちに退職させる)」との規定を設けるよう企業に勧める方がおられる。
確かに、このような規定は契約法的な観点からは合理的なものといえなくもない(※)。しかし、以下の理由から、筆者はそのような規定は採用するべきでないと考えている。
※ 就業規則に定めがない場合について、下級審判例で、従業員の病状の程度が重く、回復の可能性がなく、かつ業務における支障が大きい場合は休職させることなくただちに退職させることができるとするもの(東京地判平成14年4月24日)がある。従って、法的にこのような規定は有効であると考えられる。
【休業期間中に回復が見込めない場合の考え方】
- 私傷病の休業制度には、従業員の安心感を醸成してモラールを向上させるという福利厚生的な意義もあること。(「突然、不治の病に罹ったとしても、いきなり路頭に迷わせたりはしないので、安心して働いて下さい」ということ。)
- 医学的に回復する見込みがないとしても、現実問題として、医学的な個人情報を入手して一定期間内に回復不能と判断することは困難であること(そもそも心の健康問題で一定の期間内に治らないと診断できることはほとんどない(東京地判平成17年2月18日参照)。また、あったとしても、医師が会社に告げることはあり得ない。また、本人から聞き出すにしても、医師が本人に知らせないこともあろうし、家族には企業に話す義務はない。
- 医学的に回復が不可能だと企業が判断し得たとしても、本人や家族が回復可能だと思っていれば、企業の判断を本人に伝えることでトラブルになりかねない。
※ 柳川行雄「職場復帰に関する企業の規程例」(心の健康詳説職場復帰支援の手引き(中央労働災害防止協会 2010年)所収)参照
短期的な企業の利益よりも、他の労働者のモラールに与える影響の方がはるかに重要なのである。法律的に正しいことが、経営方針としても正しいとは限らないのである。
法律や医学の専門家の助言は、真摯に聴いて参考とする姿勢が必要ではあるが、最終的な結論は経営的な面から事業者が判断しなければならない。そこを誤ってはならないのである。
(2)最長保障期間経過後の取扱い

※ イメージ図(©photoAC)
私傷病による休業制度は解雇の猶予措置である(※)との考え方があり、休業の最長保障期間が過ぎた場合は自然退職(自動退職)または解雇すると、就業規則に定められることが多い。そして、解雇には種々の制約があるため、自然退職とする方が有利だと企業にアドバイスする専門家は多い。
※ これについて厚生労働省労働基準局「労働基準法(改訂新版)」(労務行政 2005年)は、「このような休職期間満了による自然退職は、解雇なのか労働契約の自動的終了であって解雇ではないのかが問題となる
」とし、その結論については「解雇ではないとみるべきではなかろうか
」と、必ずしも明言していない。一方、東京大学労働法研究会「注釈労働基準法上巻」(有斐閣 2003年)は病気休職期間満了後に病気が治癒しない場合の労働契約の終了は(就業規則の表現に言及せずに)「解雇」であるとし、道幸哲也他「リストラ時代 雇用をめぐる法律問題」(旬報社 1998年)も「解雇と解釈するべきではないか
」としている。
これに対し、判例は、休職期間満了による当然退職の規定を、公序良俗に反しない(東京高判昭和58年2月23日)とし、あるいは有効(神戸地姫路支判昭和57年2月15日)とし、また札幌地決昭和57年1月18日は自然退職規定による退職は解雇ではないなどとしている。
なお、三柴丈典「職場復帰支援のポイント~法学者の立場から~」(心の健康詳説職場復帰支援の手引き(中央労働災害防止協会 2010年)所収)は、三柴はこのような規定が無効となることがありうると指摘している。
また、判例も、自然退職の規定を有効としつつも、就業規則の規程の違いで労働者の身分保障に実質的な差異が出ないようにしている(※)。
※ 例えば、東京地判昭和59年1月27日は、「病気休職制度は傷病により労務の提供が不能になった労働者が直ちに使用者から解雇されることのないよう一定期間使用者の解雇権の行使を制限して労働者を保護する制度である
」とした上で、「(就業規則の)自然退職の規定の合理性の範囲を逸脱して使用者の有する解雇権の行使を実質的に容易ならしめる結果を招来することのないよう慎重に考慮
」すべきだとする。
そして、就業規則に自然退職としている場合について、神戸地姫路支判昭和57年2月15日の他、例えば東京地判昭和59年1月27日や広島地判平成2年2月19日は、労働者が職場復帰を可とする主治医の診断書を提出して復職を求めれば、企業の側が復職ができない理由を証明しなければ退職の効果を主張することはできないとし、しかも「治癒=職場復帰できる状態」か否かの判断基準を自然退職と解雇で区別しているわけではない。それであれば自然退職とするか解雇とするかで、実務上それほど大きな違いはない(野田進「『休暇』労働法の研究」(日本評論社 1999年)も同旨)ように思える。
また、高橋(※1)は、会社にとって必要な人材を機械的に退職させないために、休職期間満了時の取扱いについては「規程類については多少幅のある内容」とするべきとする。そのような趣旨からは自然退職とするのではなく、解雇としなければならない(※2)こととなる。
※1 高橋信雄「職場復帰のポイント~経営の視点から~」(心の健康詳説職場復帰支援の手引き(中央労働災害防止協会 2010年)所収)
※2 昭和27年7月25日基収1628号は、休業期間終了後の退職について、期間満了の翌日等一定の日に労働契約が自動終了することを明白に就業規則に定めて明示し、かつ、その取扱いについて規則どおりに実施し、例外的な運用や裁量がなされていないならば、終期の到来による労働契約の終了となり解雇の問題は生じないとする。なお、東京地決昭和30年9月23日も同趣旨である。
この理由としては、定年制度に関する厚生労働省労働基準局「労働基準法(改訂新版)」(労務行政 2005年)の以下の記述が参考となる。すなわち、「(定年制度の就業規則の)なかには会社の都合や労働者の事情を考慮して定年に達した者をそのまま勤務延長し、あるいは身分を変更して嘱託等として再雇用し、引き続き使用している例が見られる。このような取扱いをしている場合には、定年に達した後も労働者は引き続き雇用されることを期待することとなり、特に使用者からそのような例外的取扱いをしないことが明示されるまでは定年後の身分が明確にならないこととなる。したがって、この場合の定年制は、定年に達したときに解雇することがあるという解除権留保の制度にすぎないものと解され、解雇に関する規定の適用を受けることとなる
」という。
定年の場合も私傷病休業の終了での自然退職の場合も、労働契約の終了を定めた条項という意味では同じであるから、同局のこの考え方は休業の終了の場合も当てはまる。むしろ、退職規程の合理性(労働契約法第7条)は、定年の場合の方がより推認されやすいこととなろう。
なお、自然退職とする場合は、休職を命じるときは相当な理由が必要になるだろう(加茂善仁「Q&A労働法実務シリーズ 解雇・退職(第3版補訂版)」(2008年)及び山川隆一「雇用関係法(第3版)」(新世社 2003年)も同旨)。また、休業の最長保障期間は労基法第21条に定める場合を除き、入社まもない従業員についても30日以上としなければならない(労基法第20条との整合性)ことに留意すべきである。
そもそも、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(職場復帰支援の手引き)は休業の趣旨をメンタルヘルス不調から回復するための「休養」の手段と考えており、「働けないので、本来なら解雇するところを一時猶予して休業させる」ことを想定しているのではない。つまり、休業しやすい制度(休業の開始に大きなハードルがなく、職場復帰も十分回復してから行う)が望ましいのである。であれば、休業の最長保障期間が終了したときに自然退職すると規定(して解雇ではないと理解)することは、職場復帰支援の手引きの基本的な考え方と矛盾することになる。従って、最長保障期間が経過した時点で職場復帰できない場合、解雇の手続きによることが望ましいと考えられる。なお、解雇予告の期間中に従業員の健康状態が復職可能なまでに回復して、従業員が復職を希望する場合に、解雇予告を取り消すことは可能である(昭和33年2月13日基発90号)。
また、自然退職とすることは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の平成17年改正によって示された精神障害者の雇用の促進という理念とも適合しないように思える。厚生労働省の「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会報告」(平成16年)も、「企業に採用されてから精神障害を有するようになった者の雇用の継続も課題となっている
」としている。さらに、中央労働災害防止協会の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための方法等に関する検討委員会報告書」(平成20年)(※)が「休業期間の最長(保障)期間満了後の雇用契約の解除は、解雇制限法理(労働契約法16条参照)の制約を受ける
」としていることの趣旨も、まさにこの点にある。
※ この報告書は筆者(柳川)が担当して取りまとめている。
(3)休業期間の通算とクーリング
ア 疾病の同一性の判断の問題
最近では就業規則に、一度休業した従業員が再び同じ疾病で休業する場合、休業の最長保障期間の算定に当たっては、前の休業期間を算入(通算)するとの規定を設ける企業が増えつつある。これは精神疾患で休業を繰り返すケースに対応するためである。しかし、この場合に実務上で問題となるのは、精神疾患の場合、何をもって同じ疾病と判断するのかが難しいということである。
しかも職場復帰支援の手引きは、休業に当たって提出させる診断書に疾患名の記入は必ずしも必要ないとしており、その点との整合性をとるべきであろう。筆者は、すべての精神疾患および心身症は同じ疾患であるとみなしてもよいのではないかと考える。
イ 通算の制度の法的な制約はあるか
なお、法的には、休業は法律上の義務ではなく、通算の制度なども(契約上の制約はあるにせよ)原則として企業の判断で(労使自治により)決められるべきものである。
判例では「原告の主張によると、疾病の種類が異なる場合には休職期間を通算しないことになるが、そうすると、疾病を併発した者の場合、休職期間が著しく長期(中略)となり、この点においても原告の主張は合理性を欠くというべき
」として異なる疾病での休業期間の通算を適法とするもの(大阪地判平成15年7月30日)がある。これは、公社の制度(郵政事業庁職員休職規程第4条第2項)に関する判断ではあるが、判旨は民間企業の休業制度の場合にも当てはまろう。
なお、判例で、過半数組合の合意を得た上での休職期間の通算制度の導入(「欠勤後いったん出勤して、三カ月以内に再び欠勤するときは、前後通算する」を「六カ月以内、または同一ないし類似の理由により再び欠勤するときは、欠勤期間を中断せず、前後通算する」と変更した)を適法とするもの(東京地判平成20年12月19日)がある。
ウ 就業規則の不利益変更の問題
ただし、それまで精神障害の疾病の同一性を個別に判断していた場合、すべての精神疾患を同一のものと判断する制度に変更するのであれば、これにより労働者側に不利になることが考えられる。その場合、クーリング(職場復帰後一定期間を経過した場合はそれ以前の休業は最長保障期間に算入しない)制度を採用(第5条第2項)し、クーリング期間を3カ月などとすることにより調整することなども考えられよう。
職場復帰した従業員が3カ月以内に別な疾患で休業するようなことは、ほとんど考えられないからである。なお、島他の調査(※1)によると「同一の私傷病による休職が、一定期間以内であれば通算する規則のある事業場は35.1%であり、通算する際の休職の間隔は、平均して6.8か月であった
」とされており、また、田中他(※2)の調査では「復職により休職期間はリセットされる」とする事業場は514事業場中314事業場(61.1%)で、リセットに必要な勤務日数の平均値は149.9日であったとされている。3ケ月はこれらの平均必要日数よりも約2カ月から4カ月短いことになる。
※1 島悟他「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰に関する研究」(2009年)
※2 田中克俊「復職前の夜間睡眠の状態と復職後の経過の関連(リワークプログラムを中心とするうつ病の早期発見から職場復帰に至る包括的治療に関する研究)」(2009年)
4 最後に
最後になるが、心の健康問題によって勤務の継続が難しくなった労働者について、いかにスムーズに雇用関係を解くかを考えるようなことは避けなければならない。
雇用関係を解く方向でのみ考えることのデメリットは、以下の3点が挙げられる。
【心の健康問題を有する労働者を解雇することのリスク】
- 心の健康問題を有する労働者もまた、企業にとっては有用な人材であることも多い。そのような場合、その人材の有効活用を図れなくなるという問題が生じる。
- 少なくない労働者は、心の健康問題を自らと関係のあることとして理解している(※)。そのため、心の健康問題を有する労働者を解雇することは、他の労働者の会社に対する忠誠心やモラールに悪影響を与えるリスクを内包している。
- 解雇された労働者と訴訟での争いになれば、マスコミやSNSによって情報が広まることにより、会社のイメージを低下させるリスクがある。
※ 小倉一哉他「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」(労働政策研究・研修機構,労働政策研究報告書No22,2005年)によると、「今のような調子で仕事を続けたら健康を害すると思うか」という問いに対し「よくそう思う」と回答した者が17.8%、「ときどきそう思う」が39.3%となっている。そして、そのうち51.6%が健康を害する内容として「心理的・精神的な破綻」と回答している(複数回答)。

※ イメージ図(©photoAC)
繰り返しになるが、企業にとっての最大の財産は人材なのである。これを活かせず、また多くの従業員から不信の目で見られるようでは経営は成り立たないのである。また、ネット社会においては企業イメージは、BtoC 企業のみならず、BtoB 企業においても重要となっている。労働者を大切にしない企業というイメージが生じることは、企業経営にとって致命的なものになりかねないのである。
もちろん、一定の配慮を行った上で、労働者を解雇せざるを得ない場合もあることは否定できないが、原則は雇用を守る道を探るべきである。それは、その労働者の持つ能力をできる限り引き出し、それに見合う処遇をすることにより、労働者と企業の双方の利益になる道を探るということである。
それこそが、心の健康問題を有する労働者を処遇する場合の基本となるべきことなのである。
【関連コンテンツ】

病気休職の職場復帰は、完治後ではない
病気休職の職場復帰は、完全に治ってからするべきという考え方は医学的にも法律的にも大きなリスクがあります。職場復帰のときをどのように定めるべきかについて解説します。

職場復帰における試し出勤と労働者性
心の健康問題によって休業した労働者の職場復帰に当たり、試し出勤の期間中について、労働者との契約的な関係をどのように理解するべきかを解説しています。

職場復帰時の試し出勤等の趣旨と長さ
心の健康問題によって休業した労働者の職場復帰に当たり、試し出勤及び慣らし勤務の意味と、その長さをどのように決めるべきかを解説しています。

職場復帰の「リハビリ勤務」とその妥当性
試し出勤、慣らし勤務とリハビリ勤務の違いを明確にし、リハビリ勤務を行うことの問題点について解説します。