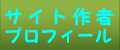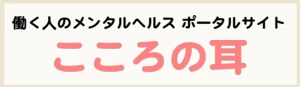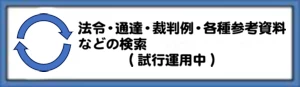※ イメージ図(©photoAC)
ある災害について国が労働災害であると認定した場合、事業主の側からその取り消しの訴えや不服審査請求をすることは可能でしょうか。
訴えが可能かについては、東京地裁の昭和36年11月21日の判決が否定的に判断しており、国もできないという趣旨の国会答弁を行うなど否定的に理解されてきました。ところがメリット制が適用される事業主について、これを肯定的に解する高裁判決が、2017年から2022年までの数年間で複数出されたのです。
これを受けて、厚労省は、不服審査についても事業主の労災支給処分に対する不服申立適格についての検討会を立ち上げて、2022年10月26日から2回の検討を行い、同12月13日に事業主側からの不服審査を可能とする(※)内容の報告書を公表しました。
※ 厳密には、事業主に労災認定決定についての不服審査の請求を認めるものではなく、保険料認定処分の不服申立等において、労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認めるというものである。しかし、実質的には労災認定の決定が無効であることの確認の請求を認めるものと言えよう。
その後、厚労省は通達によって事業主からの不服審査を可能とする措置をしました(※)。ただし、最終的に保険料(徴収額)の決定にあたってその労災の認定はないものとして算定するするとことになったとしても、労災支給決定は取り消さないとしています。従って、その通りに運用されるのであれば、労働者に不利益はないこととなります。
※ 厚労省は、この通達を WEB 上で公開していない。
ところが、2024年7月最高裁第一小法廷(※)は、原審の高裁判決(二審判決)を破棄して、事業主の側からの労災認定の取消訴訟を提起することはできないと判断しました。
※ 最高裁は、判例の変更を行う場合は大法廷で審理をする(裁判所法 10 条三号)が、小法廷で判断をしているので、過去の判例を変更するものではないこととなる。
労災保険の不服審査は、このサイトの趣旨である労働安全衛生とは異なる範疇のことではありますが、労働災害に関するこれまでの常識を覆す可能性があるもので、安全衛生の担当者にとっても重要なものですので、考え方や経緯等を分かりやすく解説します。
- 1 はじめに
- (1)事業主の労災認定取消の訴えについての原告適格
- (2)判例の動向
- (3)厚生労働省の検討会の検討結果と問題点
- (4)厚生労働省の検討会への批判
- 2 この制度改正は優良な事業主にとって利益とはならない
- 3 一般財団法人あんしん財団について
- 4 最後に
1 はじめに
(1)事業主の労災認定取消の訴えについての原告適格
執筆日時:
最終改訂:

※ イメージ図(©photoAC)
ある人が別な人との間に争いごとが生じ、裁判所で争いたいと考えたとしても、すべての争いごとが裁判所に訴えることができるわけではない。裁判に訴えるためには、いくつかの訴訟要件を満たす必要があり、そのひとつに「訴えの利益」(※)がある。訴えの利益がなければ、裁判所は訴えの実質的な審議をせずに訴えを却下(いわゆる門前払い)してしまう。
※ 「裁判」という制度は、法律によって当事者の争いごとの最終的な判定を行う仕組みである。訴えの利益があるというためには、その裁判制度を利用することが、その争いについて適切かつ必要でなければならない。
法律によって解決するべき問題ではないこと(宗教上や学説上の争いなど)を訴えられても裁判所では判断ができないし、裁判をする必要のない訴訟(当事者にとって法的な利益のない訴え)を乱発されては裁判所の業務に支障がでる。そのため、「訴えの利益」という概念が生まれ、訴えの利益がなければ訴えることができないこととされたのである。
この訴えの利益に含まれる概念に「当事者適格」がある。災害が発生して労働災害と認定されたときの事業主を考えてみよう。この事業主はその災害が労働災害ではないとして国を訴えることができるだろうか。それは、その災害が労働災害ではないと認められることによることで、事業主が法的な利益を得られるかによって定まるのである。
確かに、自社で労働災害が発生すると事業主には、刑事上、民事上、行政上などの様々な不利益が生じる。
しかし、刑事責任(業務上過失致死傷罪や安衛法違反)は、発生した災害が労働災害かどうかとは直接は関係がない。民事責任(損害賠償責任)も、実質的には労働災害として認定を受けたことによって影響を受けるとしても、法的に直接的な関係があるわけではない。行政罰(入札からの排除、資格の喪失など)は、法的な関係があるにしても、直接的なものではない。
従って、事業主には、国の労働災害認定の取消しを求める法律上の利益がない。このため、労働災害認定の取消しを求める訴訟の当事者適格がないというのが、従来の判例であり、厚労省の見解でもあった。学説も多数説はこれを指示しているといってよい。
実を言えば、メリット制の適用される事業場においては、労働災害の認定が行われると労災保険の料率が上がるため、原告適格を認めるべきとの学説(※)があったことは事実である。しかし、少数説にとどまっていた。
※ 保原喜志夫「労働判例研究第109回」(ジュリスト Vol.278)、斎藤浩「労災業務上認定に対し使用者が起こす取消訴訟の原告適格について」(立命館法学 2021年 Vol.395)など
(2)判例の動向
ア 最高裁による平成13年判決

※ イメージ図(©photoAC)
ところが、2001年(平成13年)に最1小判平成13年2月22日が、「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定取消訴訟において、事業主は、その事業が労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項各号所定の一定規模以上の事業である場合には、労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加することが許される
」としたのである。
分かりやすく言えば、メリット制の適用がある事業主は、労災保険の不支給決定取消訴訟において、被告である労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加(補助参加)(※)することが許されるとしたのである。
※ 民事訴訟法第42条による制度で、他人の間で起きている訴訟について、その結果がどうなるかに利害関係のある第三者が当事者の一方を補助するために訴訟に参加すること。
この事件は、労働者の側が不支給決定取消訴訟で労働基準監督署長を訴えたわけだが、被告ではない(訴えられていない)事業主が、被告である労働基準監督署長への補助参加が可能であるとしたわけである。労災認定取消訴訟の原告適格を直接認めたわけではないが、メリット制が適用される事業主については、訴訟の当事者となる利益を認めたものと理解された(※)。
※ しかし、最高裁の意図はそうではなかったのである。そのことは、2024 年の最高裁の判例によって明らかになるが、そのことは後述する。
イ 東京高裁平成29年判決
前記の最高裁判決が影響したと言われるが、その後の高裁判決で、労災認定取消訴訟の原告適格を認める判決が2件出された。
そのひとつが、東京高判平成29年9月21日(医療法人社団総生会事件)である。これは、東京地判平成29年1月31日(医療法人社団総生会事件)の原告適格に関する判断を維持したものである。
この東京高裁の判決文(※)は、東京地裁判決文を準用して、修正するという形をとっている。次に示す引用文は厚生労働省において、修正後の形にしたものである。
※ 厚生労働省の資料では「医療法人社団X事件」とされている。
上記(イ)のとおり、特定事業においては、当該事業につき業務災害が生じたとして業務災害支給処分がされると、当該処分に係る業務災害保険給付等の額の増加に応じて当然にメリット収支率が上昇し、これによって当該特定事業主のメリット増減率も上昇するおそれがあり、これに応じて次々年度の労働保険料が増額されるおそれが生ずることとなる。
したがって、特定事業主は、自らの事業に係る業務災害支給処分がされた場合、同処分の名宛人以外の者ではあるものの、同処分の法的効果により労働保険料の納付義務の範囲が増大して直接具体的な不利益を被るおそれがあり、他方、同処分がその違法を理由に取り消されれば、当該処分は効力を失い、・・・これに応じた労働保険料の納付義務を免れ得る関係にあるのであるから、特定事業主は、自らの事業に係る業務災害支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有する
※ 厚生労働省「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会 第1回参考資料2」による。
これが、労災認定取消訴訟で、事業主の当事者適格を認めた最初の判決となったが、この当時はあまり注目されることはなかった。
ウ 東京高裁令和4年判決

※ イメージ図(©無料の写真素材「ぱくたそ」 )
そして、2022年に入って、東京高判令和4年11月29日(一般財団法人あんしん財団事件)が、事業主は労災認定の取消しを求める訴えの原告適格があるとしたのである(※)。
※ 労働新聞社「労災支給取消し訴訟 特定事業主の原告適格認める 地裁に審理差し戻し 東京高裁」(2022年12月15日)
東京高裁は、「事業主は労災認定の取消しを求める訴えの原告適格がない」とした東京地判令和4年4月15日を破棄し、判決を東京地裁に差し戻した(※)のだ。
※ この高裁判決は上告され、2027年7月4日に最高裁によって破棄されることとなる。なお。仮に高裁判決が破棄されずに確定されていれば、東京地裁は、高裁の差し戻した理由に拘束されるので、差し戻し審で事業主に原告適格がないとすることはできなかった。
なお、原審の東京地裁も、保険料の認定処分に対する取消訴訟(※)において、労働保険料の算出において考慮される労災認定の違法性(従って、労災認定が誤りであること)を、保険料の認定処分が取り消されるべき事由として主張することは許される余地があるとしていた。
※ 保険料の認定処分の対象は事業主であるから、その取消訴訟について、事業主原告適格を認められることは当然である。
しかし、東京地裁は、そのような主張が行われて、業務災害支給処分の違法性を理由に労働保険料の認定処分を取り消す判決がされた場合であっても、同判決に生じる拘束力(行政事件訴訟法第33条1項)により、行政庁が同判決と整合しない当該業務災害支給処分の取消義務は負わないとしている。
また、業務災害支給処分の違法性を理由に労働保険料の認定処分を取り消す判決がされた場合に、同判決に生じる拘束力(行訴法33条1項)により、行政庁が同判決と整合しない当該業務災害支給処分の取消義務を負うか否かについては、要件の判断を誤った業務災害支給処分により過大な保険給付がされることはメリット制の適用の有無にかかわらず生じ得るところ、徴収法は、そのような場合であっても、労災保険事業全体の長期的な収支においてその均衡を図ることを想定していることに照らし、消極に解するのが相当である。
※ 東京地判令和4年4月15日(一般財団法人あんしん財団事件)より。「弁護士 師子角允彬のブログ」から引用した。
例を挙げて説明しよう。国がある災害を労働災害だと認定して労災補償給付を行ったために、企業の労災保険料率が上昇したとしよう。そこで、事業主が「保険料率の上昇は、国が誤って労働災害を労働災害だと認定したためであり、取り消されるべきだ」と主張して訴えた。裁判所は、この主張を認め、災害が労働災害ではないことを理由に、原告を勝訴させたとしよう。
この場合、本来であれば、国は判決に従ってこの事業主の労災保険料率を元に戻さなければならないこととなる。しかし、労働者への労災保険の支給は取り消す必要はないとしたのである。これは、労災補償給付を受ける労働者にとっては有利な判断である。これが、後に厚生労働省の報告書に影響を与えることとなる。
エ 山口地裁令和4年判決
なお、ここまでに挙げた2件の高裁判決はいずれもメリット制について適用のある事業主について、労災認定取消訴訟の原告適格があると判断したものである。これに関連して山口地判令和4年9月21日(株式会社Z事件)も次のように述べている。
労災保険制度の趣旨、内容等に照らせば、個々の労災支給処分がされる段階において、特定事業主が違法・過大な労災支給処分の是正を通じて労働保険料の是正を図ることは、迅速な労災支給処分や財政の均衡確保といった趣旨とは両立し難い。
このような労災保険制度の在り方を踏まえれば、特定事業主の利益(他の特定主との関係で、個々の保険給付等の差に見合った労災保険に係る費用の公平な分担がなされるべき利益)は、メリット制が適用されるに至り初めて考慮されるべきものであって、それ以前の個々の労災支給処分の段階において考慮されない。
※ 厚生労働省「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書」による。
ただ、事業主側が労働災害認定取り消し訴訟を行う動機は、必ずしもメリット制による労災保険料の増額の防止に限られるわけではないだろう。仮にそのような訴訟が行われるとすれば、おそらくひとつには、労災が認定されることによる企業の社会的評価の低下を恐れる(※)ことが挙げられよう。
※ 現実に企業の社会的な評価につながりやすい災害は、過労死と精神疾患である。また、労災かどうかが争われやすいのもこの類型であろう。しかし、後述するように、優良な企業であれば、そのような訴訟を行うことはまれではないかと思える。
そして、さらに重要なこととして、労働災害として認定されると、その後、民事訴訟を起こされた場合に事業主側に不利益に評価されがちな(※)実態があることもあるかもしれない。
※ 労働災害の民事訴訟は、労災が認定された後で行われるケースが多い。
(3)厚生労働省の検討会の設置と検討結果
ア 検討会の設置と検討の経緯
以上の状況を受けて(※)、厚生労働省は、行政による不服審査手続きについても事業主の原告適格について検討するため、事業主の労災支給処分に対する不服申立適格についての検討会を2022年10月26日に立ち上げた。
※ この委員会を立ち上げた時点では、一般財団法人あんしん財団事件の高裁判決(2022年11月29日)は出ていない。地裁判決が、労働保険料の算出において考慮される労災認定の違法性を、保険料の認定処分が取り消されるべき事由として主張することは許される余地があるとしたことが直接の契機となっている。
そして、2022年10月26日からわずか2回の検討会を開催したのみで、同年12月13日に事業主側からの不服審査を可能とする報告書を公表したのである(※)。
※ やや分かりにくいが、厳密には労働災害であることを認定した決定について取消しを求めることを認めたわけではない。労災保険料の決定に対する不服審査において、その災害が労働災害ではないという主張を認めるということである。このこと自体は、東京地判令和4年4月15日(一般財団法人あんしん財団事件)でも否定はされていなかった。
それにしても行政は結論を急ぎ過ぎているのではないかという印象を受ける。急いだのは、おそらく次のような理由だったのだろう。
労災保険に関する行政処分への訴訟は、原則として行政への不服審査を行った後でないとできないこととされている。ところが、当時は、労災保険料決定についての行政の不服審査制度では、労働災害がなかったと主張することが認められていなかった。
しかし、一般の事業主が労災保険料決定に関して、労働災害そのものがなかったと主張する可能性はあった。ところが、その場合、事業主は、いったん行政への不服審査を行い、棄却されたのちに訴えを起こさなければならないことになる。
このような事態を避けるために結論を急いだ可能性はあるが、せめて高裁判決の妥当性への最高裁の判断を待つこともできたのではないかと思われる。
イ 検討会の検討結果
この検討会の結論は、次の3点にまとめられた。
- 保険料認定処分の不服申立等において、労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認める。
- 保険料認定処分の不服申立等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災支給処分が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
- 保険料認定処分の不服申立等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災支給処分を取り消すことはしない。
※ 厚生労働省「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書」による。
これは、先述した高裁判決が、メリット制の対象となる事業主の、労災認定取り消し訴訟の当事者適格を認めたことを、保険料認定処分の不服申立等に転用したものである(※)。しかし、その一方で、東京地判令和4年4月15日(一般財団法人あんしん財団事件)の判決文から、労災支給処分の支給要件非該当性が認められた場合であっても労災支給処分を取り消すことはしないとして労働者の保護を図っている。
※ 先述したように、正確には原審の東京地裁の判決をそのまま採用したともいえる。高裁は、東京地裁判決のこの部分については判断していない。
厳密には、事業主に労災認定決定についての、不服審査の請求を認めるものではないが、実質的には労災認定の決定が無効であることの確認の請求を認めるものと言えよう。
(4)厚生労働省の検討会への批判
厚生労働省に提出された「団体からの意見要望」(※)によると、4つの団体から事業主による労災認定の取り消しを認めることへの反対の意思表明が行われている。
※ 第2回「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」資料の参考資料1
これについては、とくにコメントはしない。事実関係を紹介しておくにとどめる。
(5)行政による不服審査手続き制度の改正
厚生労働省の検討会による報告書の結論は、2023 年の初頭に、通達(※)による解釈の変更が行われて、そのままの形で不服審査制度の取扱いが変更されることとなった。
※ 行政は、その通達を 2024 年7月現在、WEB 等では公開していない。
2 最高裁の最終的な判断
(1)最高裁が労災決定の取り消し訴訟について事業主の当事者適格を認めなかった
ところが、2022年7月になって、最高裁が、一般財団法人あんしん財団事件の高裁判決(2022年11月29日)を破棄し、事業主は労災認定の取消しの訴えができないとする東京地裁の判決を確定させてしまう(※)のである。
※ 朝日新聞2024年7月4日「労災認定、事業主は「不服申し立てできない」 最高裁が初判断」
なお、この最高裁の判決は第一小法廷で下されている。最高裁は前の最高裁の判例を変更する場合は大法廷で判決を下す必要がある(裁判所法 10 条三号)。従って、かつて、最1小判平成13年2月22日が、「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定取消訴訟において、事業主は、その事業が労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項各号所定の一定規模以上の事業である場合には、労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加することが許される
」とした判例は変更されていないのである。
最高裁は、上告を門前払い(却下又は不受理)する場合はもちろん、棄却する場合も口頭弁論を開かずにする(民事訴訟法第319条)ことが普通である。この場合は原判決が破棄されているので、口頭弁論は開かれている。従って、厚労省は口頭弁論の時点で勝訴の可能性が高いことは分かっていたのではないかと思われる。
(2)行政の不服審査と司法による訴訟で取扱いが異なる
最高裁は、労災認定決定の取消し訴訟については事業主には原告適格がないと判断している。労災保険料決定に対する変更を求める訴訟について事業主に原告適格があることは当然である。
しかし、誤解してはならないが、後者の訴訟において、該当する災害が労働災害ではないと事業主が主張することが認められるかどうかについては、この最高裁判決では判断をしていないのである。
確かに、本稿の冒頭に掲げた最1小判平成13年2月22日は、該当する災害が労働災害ではないと事業主が主張することを認めていると理解されなくもない。しかし、この判決も、厳密には労災不支給決定の取り消し訴訟において、被告側への補助参加が許されるとしただけなのである。
事業主は労災認定の取消しの訴えができないとしている以上、労災保険料決定に対する変更を求める訴訟においても、該当する災害が労働災害ではないと事業主が主張することを認めることができるかどうかについても消極的に解するべきではなかろうか。
仮にそうだとすれば、労災認定の決定が無効であることの確認について、事業主は、実質的に対して不服審査を請求できるにもかかわらず、裁判所へ訴えれば却下されるということになる。従って、これについては事実上、行政の不服審査が終審ということになる(※)。
※ だからといって、制度的に裁判をすることを禁止しているわけではないので、日本国憲法第76条第2項2文に違反するわけではない。
これは、行政の取扱いが、最高裁が判断していないことを先行的に認めてしまったということである。行政と司法の取扱いの間に齟齬があるというべきであり、好ましいことではない。今後の行政の動きに注目したい。
3 厚生労働省の検討結果の問題点等
(1)厚生労働省の検討結果への懸念
ア 重大な変更を拙速に行うべきではない
そもそも一般財団法人あんしん財団事件は労働基準監督署長(国)が被告となっているのであり、上告をしたのは国の方なのである。事業主は労災認定決定の取消しを求める訴えはできないとして、国自身が争っていたのだ。にもかかわらず、その結審を待つことなく、労働災害ではないことの実質的な確認を、行政の不服審査手続きにおいて、事業主が求めることができるとしたことはやや理解に苦しむ。
先述したように、事業主の側から労災保険料決定への不服審査請求が行われ、労働災害ではないという事業主の主張を行政が認めずに、行政訴訟になる事態をおそれたのかもしれない。しかし、自己矛盾という気がするのは、筆者だけではないだろう。
厚生労働省が、このような労災補償制度の考え方の骨幹を変更するようなことを、わずか2回程度の委員会の開催で結論付けたことについては、強い疑問を感じる。
イ 与党による労災給付取消の判断に繋がらないか
しかし、行政の取扱いは、「労災ではないと判定された」場合であっても、「労災支給は行う」というものである。このことだけについては、東京地裁の判断に適合している正しい結論であると筆者は考えている。しかし、与党の大臣級の議員が生活保護バッシングや貧困バッシングを行っているような状況(※)で、現在の与党の広範な理解を得られるのかという点について、やや危惧の念が感じられる。
※ 例えば、世耕弘成氏は「(生活保護受給者は)一定の権利の制限があって仕方がない」と延べ、また片山さつき氏は「生活保護は生きるか死ぬかという状況の人がもらうべきもの」という発言をしている。このような発想は、日本国憲法第25条に反しているばかりか、貧困家庭に生まれた若者の能力を発揮する機会を奪うものであり、わが国の経済・科学・文化の健全な発展を阻害するという観点からも誤った思想というより他はない。
現在の与党は、貧困家庭に対する自己責任論的な発想が強い。そして、その背景にあるのは、国民への生活保障はできる限り押さえたいという発想があることは言うまでもない。この発想でこの報告書の結論を評価すると、労災でないなら労災支給は行うべきではないという考えに行きつくのではないだろうか。
ウ 労災給付取消は、我が国の被災労働者の労働能力の回復を阻害する
そもそも、現代国家の労災補償制度は、働く人が労働災害に遭ったとき、これを手厚く補償することにより、労働者の生活の安定と安心感につなげるものである。この制度は、国民が安心してその能力を発揮できるようにサポートする制度であり、たんに福利厚生にとどまらず、国家が発展してゆくために必要なものなのであることを再確認しておきたい。
この報告書の結論は、労働災害に遭ったときに、企業による労災認定取り消しの不服申し立てや取り消しの訴えをするという判断によって、労災保険給付の遡及的な取り消しのおそれがでることになりかねないリスクを有している。そのような状況になれば、労働災害に遭った労働者は、安心して治療を受けることが困難になろう(※)。これは、労働能力の速やかな回復という観点からも重大な問題である。
※ 労災であれば医療費の自己負担はないが、労災でないということになれば3割は自己負担となる。しかも、労働災害でないと労基法第19条第1項の労災の解雇制限がなくなるので、療養のための休業中に解雇される恐れがある。これでは、必要な治療を受けることに消極的にならざるを得ないこととなろう。
エ 事業主の労災認定取消の主張を認めれば、様々な弊害を生む
そもそも一私企業である事業主の不服申し立てや訴えをするかどうかの判断によって、労災に遭った労働者の保障に影響があるという制度は、社会の公正の観点からどうなのだろうか。そのような制度の下では、事業主が被災労働者の生殺与奪の権を握ることになりかねない(※)。
※ 労災でないということになれば、先述したように労基法第19条第1項の労災の解雇制限がなくなるので、事業主は労働者を解雇することが可能となるケースが出てくる。ブラック企業であれば、「不服申し立てや訴えをしないのと引き換えに、『自主的に』会社を辞めろ」と労働者に迫ることも考えられるのである。
また、労働行政機関としても、自らの労災認定の判断に対して事業主側から不服申立等が行われると膨大な業務量が発生することになる。さらには、労災の判定が誤っていたということになれば、行政の側としても自らの職業上の評価を落とすのではないかとの危惧から認定に消極的になる可能性も否定はできないだろう。
(2)この制度改正は優良な事業主にとって利益とはならない

※ イメージ図(©無料の写真素材「ぱくたそ」 )
最終的に破棄されたものの、一般財団法人あんしん財団事件の東京高裁判決は、事業主側からの労働災害取消しの訴えの原告適格を認めた。また、その直後に、厚生労働省が保険料認定処分において事業主の「労災ではない」という主張を認めるとしたことは、一見すると事業主にとって有利な方向への転換だと思われるかもしれない。
しかしながら、実際にはそうではないだろう。というのは、労災認定事案のほとんどを占める業務上負傷については、事業主が業務上だと認めて労災請求をしているケースがほとんどなのである。事業主からの労災申請の協力が得られないケースでも、そのほとんどが業務上か否かを争う余地のないような事案である(※)。
※ 労働災害として認定された事例の中に、きわめてまれにではあるが疑問を感じるようなケースがあることを否定はしない。しかし、そのような場合でさえ事業主が争うようなケースはまれである。また、ごくまれなケースに拘泥して、大多数の労働者の保護を犠牲にするようなことがあってはならない。
事業主側が労働災害該当性を争う余地があるとすれば、ほぼ業務上疾病に限られるといってよい。現実には、過労死事案と精神障害事案が該当するだけだろう。そして、事業主が労災認定の適否を争うとすれば、先述したようにメリット制による保険料率の上昇よりも、労災を発生させたという「汚名」を返上したいということと、その後の民事賠償訴訟の展開を不利にしたくないというケースがほとんどではないだろうか。
しかし、よく考えてみて欲しい。労働災害認定取り消しの訴えを起こしてみても、敗訴すれば民事訴訟と併せて2度にわたって報道機関や SNS で話題になることになるのだ。一方、逆に労災認定取り消し訴訟で勝訴しても、その後の民事訴訟で敗訴すれば、労災給付額が控除されないこととなるリスクが発生する(※)ため、賠償額が巨額のものになるおそれがでるのである。
※ 行政は現在はしないと言っているが、労災保険給付を取り消さないという保障はどこにもない。SNSなどで問題に火が付き、与党ばかりか一部の野党の政治家によって政治問題化し、行政としても取り消さざるを得なくなる可能性はあるのだ。
また、被災者の側が意地になって労災保険の給付を受けなかったとしても、禁反言に触れるので民事賠償請求の場で労災保険を受けろとは言えない。そうなれば、わざわざ訴訟をして、保険金の支払いを拒否するようなものである。その負担が自らにかかってこないという保障はどこにもないのだ。
しかも、国を相手に労災認定の取消訴訟をしてみても、勝訴する確率は高くはない。それなら、むしろ労災給付の妨害などせずに、民事訴訟になる前に示談ですませる方が得策(※)である。通常の事業主にとって、事業主側からの労働災害取消しの訴えの原告適格を認めることや、保険料認定処分の不服申立を認めることは、利益になるようなものではないのである。
※ 示談書には公開禁止の義務を定めることも可能である。また、訴訟の手間やコスト、さらには訴訟への報道による影響を考えると、ほとんどの労災事案では「訴訟にしない」ことが最も合理的な判断なのである。
(3)一般財団法人あんしん財団について
最後に、一般財団法人あんしん財団について、一言触れておこう。同財団の労災認定取消し訴訟の背景の理解の一助となるだろうからである。一般財団法人あんしん財団は、財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団が改称した法人である。公益法人改革のきっかけとなったKSD 事件で有名な法人(※)なので、旧名称の方がよく知られているかもしれない。
※ 他にも、日本経済新聞「「あんしん財団」に業務改善命令 厚労省」(2010年6月18日)などが報じたように、2010年に厚生労働省から法令順守体制の抜本的な見直しを求める改善命令を出されたこともある。
一般財団法人あんしん財団事件(※1)は、事業主の労災取消訴訟の原告適格が問題となったことから、判例集に搭載される有名な事件となってしまった。この財団は、労働関係の判例集によく登場する法人である(※2)が、今回の事件はこれまでのものに比較しても、かなり有名になっている。
※1 なぜか、厚生労働省の資料では、一般社団法人Y財団事件(下線強調筆者)とされている。しかし、日本経団連の資料などにも「一般財団法人あんしん財団事件」とされているので、本稿はこの名称を用いている。
※2 「一般財団法人あんしん財団事件」で検索すると、様々な判例がヒットする。東京地判2018年2月26日もそのひとつで、財団の出した配転命令が無効とされている。また、弁護士ドットコムニュース「慣れない営業で成果出ず、地方転勤断ったら解雇 地裁は無効と判断 弁護士「企業への警告だ」」(2022年11月22日)は別な事件だが、ここでも配転命令が無効とされている。
さらに、同財団は、過去に不当労働行為を行ったとされたこともある。詳細は、東京都「あんしん財団事件命令書交付について」(2022年12月07日)を参照されたい。
一般財団法人あんしん財団は、労働災害防止対策や独自保険の事業を行っている団体である。労災保険関連のこのような判例が有名になることはあまりよい影響を与えないようにも思えるがどうなのだろうか。
また、同財団は、この労災認定により、保険料率が上がったために財団が損害を被ったとして、別途、この労災の被災者と国に対する損害賠償請求訴訟を行っている(※)。企業が労働災害の被災者を訴えたという例は、筆者は他には聴いたことがない。きわめて特殊な事例で前例はないだろう。
※ 弁護士ドットコムニュース「「虚偽にもとづく労災認定だ」財団法人が職員を提訴、職員側「嫌がらせだ」と反訴」(2021年5月17日)、機関誌連合通信社「労災被害者に損害賠償請求/あんしん財団/女性職員が「反訴」申し立て」(2021年5月20日)による。
本稿で取り上げた一般財団法人あんしん財団事件も最終的に敗訴したわけだが、この労災の被害者を訴えた訴訟も、勝訴する可能性があるとは思えない。何のためにこのような訴訟をするのか、不思議という気はする。
4 最後に
すでに述べたように、事業主側からの労働災害取消しの訴えの原告適格を認めることや、保険料認定処分の不服申立の場において労働災害が発生していないとの事業主からの主張を認めることは、多くのまじめな事業主にとってほとんど利益になることはないと思われる。

※ イメージ図(©無料の写真素材「ぱくたそ」 )
その一方で、一部の企業が悪用することも考えられるのである。
また、現在の与党の新自由主義的な風潮から、労働者への労災給付の決定を遡及して取り消せという政治主張を誘い出す原因となることも予想される。そうなると、わが国における被災労働者の労働能力の回復を阻害し、労働者への福祉の後退や、国家の健全な発展を損なう結果になりかねないのである。
長い眼で見た場合、事業主側からの労働災害取消しの訴えの原告適格を認めたり、事業者の側の労働災害ではないという主張を認めることは、わが国の労働者の健全な職業生活を損なうことになるとの強い危惧を感じざるを得ない。
厚生労働省が、わずか2回の委員会で、事業主からの保険料認定処分の不服申立の場において、労働災害ではないという主張を認めるという結論を出したことは、きわめて疑問であると最後に指摘しておく。
【関連コンテンツ】

労働災害の損害を取り戻す方法
労働災害が起きたときに、労働者がその損害を回復するために取り得る公的制度、民事訴訟制度等の手立てについて解説しています。

労働災害発生時の責任:民事賠償編
労働災害が発生したときの責任のうち民事賠償責任について説明しています。