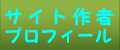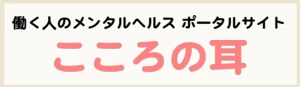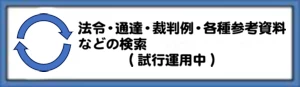産業保健担当が知っておくべき法律学の基礎についてわかりやすく説明しています。
シリーズ第3回の本稿では、労働災害が発生したときの責任のうち民事賠償責任について説明しています。
- 1 はじめに
- (1)民事賠償と労災補償の関係
- (2)民事賠償の法的な根拠(概説)
- 2 安全配慮義務と債務不履行
- (1)債務不履行責任とは
- (2)債務不履行責任と安全配慮義務
- 3 注意義務違反と不法行為責任
- (1)不法行為とは
- (2)労働災害と不法行為
- 4 安全配慮義務違反と不法行為責任の詳細
- (1)挙証責任
- (2)時効
- (3)過失相殺
- (4)損害賠償の範囲
- (5)加害者からの相殺の可否
- (6)賠償金への課税
- (7)その他
- 5 その他の民事賠償責任
- (1)会社法第429条第1項の責任
- (2)自賠責法第3条の責任
- 6 その他の問題
- (1)過失とは何か
- (2)その他の問題
1 はじめに
執筆日時:
最終改訂:
(1)民事賠償と労災補償の関係
ア 労災補償は、すべての損害を補償するものではない

労働災害が発生した場合、労災補償以外にも民事賠償(損害賠償)請求をされることがあるということは、一般の事業者にもよく知られるようになってきている。なお、労災補償と民事賠償の関係については、別に稿を起こすつもりなので、本稿では詳細には触れない。ただ、労災補償が、迅速で確実な補償という観点から補償額を単純な計算方法で定められるようになっていること、また事業者に過失がなくても補償をさせる制度であることなどから、損害の一部についてのみしか補償されないものなのだということのみを指摘しておく。
このため、労災補償制度では補償されない“差額”は、民事賠償として請求されることになるのである。ところが、この金額がかなりの高額となり、1億を超えるようなケースも散見されるようになってきた。中小規模の企業では、企業の存続にかかわるようなケースさえ散見される。ただ、賠償額は個々の事例の状況によってまったく異なる。相場が存在しているなどとは思わない方がよい。
イ 労働基準法の労災補償は、事業主の義務である
また、労働基準法上の労災補償(労災保険の話ではない)は、労働者が請求しなくても、労働基準法によって、事業者は補償をしなければならないことになっている。しかし、民事賠償については、事業者の側が自らしなければならないという法律上のルールはない。事業者の側が自ら賠償をしない場合に、労働者の側が賠償をして欲しいと思うのであれば“請求”をしなければならない。請求しても事業者の側に拒否されれば、訴訟上で請求するしかない。とはいえ、訴えるにしても、請求に法的な根拠を説明しなければ、裁判所に相手にしてもらえない。
(2)民事賠償の法的な根拠(概説)
そこで、民事賠償請求するには、どのような法的な根拠があるかを、まず全体的に概説してから、各論に入ることとしよう。この法的な根拠はいくつか存在している。
ア 契約上の根拠
まず、大企業などでは民事上の契約が根拠となるケースがある。社内の規程等で、労働災害が発生した場合について(労災保険外の)、上積み補償を規定しているときである。この契約上の定めも法的な根拠にはなるが、このような規定があれば、通常は、企業側がそれに従って支払うであろうから、本稿ではこれについては取り扱わない。
イ 債務不履行責任
法律上の根拠としては、まず、民法415条の債務不履行責任がある。民法415条には、契約の相手側が債務を履行しないことによって損害を受けた場合は、その賠償を請求できると定めている。そこで、この条文を根拠として、事業者の側には労働者の安全に配慮すべき債務があったのにもかかわらず、その債務を履行しなかったことにより、労働者の側に労働災害という損害が発生したとして請求することができるわけである。この債務が、いわゆる"安全配慮義務"である。
ウ 不法行為責任
また、民法709条、715条等の不法行為責任も根拠となる。民法709条は、故意または過失によって他人に損害を与えた場合などには、損害を賠償する責任があると規定している。ただ、労働災害の場合は、通常は、故意は問題とならず過失が問題となるが、これについては後述する。
一方、715条は、労働者等が不法行為を行ったことによる損害の賠償を、その労働者を雇用していた事業者等に対して請求する場合に根拠とすることができる条文である。
なお、労働災害に関する民事訴訟では、民法の717条を根拠とする場合もある。これは土地工作物と呼ばれるもので、土地工作物に瑕疵(欠陥)があって、その瑕疵のために他人に損害を負わせた場合の、損害賠償の規定である。
損害賠償をすべき者は一義的には占有者であるが、占有者がその土地工作物について十分な対策を採っている場合は、持ち主に賠償責任がかかり、しかも持ち主の賠償責任は過失がなくても発生する。ただ、産業保健に関する労働災害では717条はあまり問題にならないと思う。
なお、土地工作物とは、建物や土地に固定された機械設備だけではなく、クレーンのワイヤロープなども含み(最1小判昭和37年4月26日、最3小判昭和52年10月25日など)、かなり広く解釈される傾向がある。
エ 会社法における責任
また、その他には会社法429条第1項の責任がある。役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)が、職務を行うについて悪意又は重大な過失によって第三者に損害を与えた場合の賠償責任である。
では、以下、これらについて詳細に解説しよう。
2 安全配慮義務と債務不履行
(1)債務不履行責任とは
先ほど民法415条を根拠として、労働災害が発生した場合には損害賠償責任が発生すると述べたが、まず、これを詳しくみてみよう。
民法415条は次のようになっている。これがいわゆる債務不履行時の民事賠償責任である。
【民法】
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
2 (略)
例えば、ある物を購入するため、その物を所有している会社と100万円で売買する契約を結んだ者がいるとする。ところが、その物を150万円で買いたいという者が他に現れたために、売主の会社がその物の引き渡しを拒否したという場合、買主は契約を解除して100万円を支払う義務を免れることができることは当然である。またこのような場合には、発生した損害の賠償を、売主に対して請求することもできるのである。
ただし、賠償を求めることのできる額は、原則として「通常生ずべき損害」に限られている(民法416条1項)。特別な損害については、そのような損害の発生を予見できたような場合にのみ請求できる(民法416条2項)。また、賠償は原則として金銭で行うべきこととされている(民法417条)。
ただし、この条文によって損害の賠償ができるためには、相手側に故意・過失又はそれと同視し得る事情があることが必要である。なお、「これと同視し得る事情」とは、履行補助者の故意・過失である。先ほどの例で、物の引き渡しをする義務は(売買契約の相手側である)売主の会社にあるわけで、会社の従業員や取締役には物を引き渡す債務はない。
だが、実際に物の引き渡しを拒んでいるのは従業員や取締役などである。そこで、会社の債務を履行する補助者である従業員や取締役などに故意・過失があっても、会社に損害賠償を請求できるということである。もちろん、彼らは会社の債務の履行補助者ではあっても、会社とは別な"人"であるから、彼らに債務不履行責任による損害賠償を請求することはできない。
(2)債務不履行責任と安全配慮義務
そして、民法の1条2項には「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とある。裁判所はこの1条2項を根拠に、事業者には労働者の安全を守るべき債務があるとして、その安全配慮義務に違反して労働災害が発生したときは事業者には賠償責任があるというわけである。
【ちょっと専門的な話】
最高裁が、事業者の安全配慮義務を認めたのは、国家公務員についての事件が最初であった。そのためよく誤解されるのだが、実は、裁判所が国家公務員の保護を民間労働者よりも厚くするべきだなどと考えていたわけではない。労働者に対する安全配慮義務について、下級審はそれまでも民間の企業については認めていたのだが、国家公務員については認めていなかった。専門用語を使わせて頂ければ、その背景には特別権力関係の考え方があったといわれる。
そのため、国家公務員が公務災害に遭った場合には、国の不法行為責任を追及するしか方法がなかったのである。ところが、ある公務災害の事件で、不法行為については時効が成立していたため、安全配慮義務違反で損害賠償を請求したのである。下級審判決は、従来の判例に従ってこれを認めなかったので、最高裁まで争われることとなったのである。
その結果、最高裁は国家公務員に対する国の安全配慮義務を認めるに至ったのである。すなわち民間人の場合、下級審判決で認められていたために最高裁まで争われなかったにすぎないのである。
なお、この理論が一般的となるまでは、労働者側は不法行為責任を追及することが一般的であった。安全配慮義務違反と不法行為責任の違いの詳細については後述するが、被告の側に故意・過失があるか否かについての挙証責任は、不法行為責任では被告の側にあるが、債務不履行責任では被告の側にあるため、安全配慮義務の理論を裁判所が認めたとき、原告の側に有利になるといわれたものである。しかし、実務家の実感では、さしたる違いはないというのが本当のところのようだ。
【ちょっと専門的な話/挙証責任とは】
民事訴訟の世界では、裁判所(又は裁判官)は、原告と被告の争いについてどちらを勝たせるかについて判断をしなければならない。裁判官が確信を持って判断できるだけの証拠が原告又は被告から提出されればよいのだが、必ずしもそういう場合だけではない。このような場合、裁判所自らが証拠を調べることは、人事訴訟(親子関係とか夫婦関係とかのことで、会社の人事とは関係はない)は別として、管轄に関することなどを除けば認められていない。
しかし、判断するのに十分な証拠がなくても、結論は出さなければならないので、本来、主張・立証をするべき者に不利益な判断を下すのである。例えば、ある労働者が"がん"に罹り、職場に原因があったとして損害賠償請求をしたとしよう。訴訟の過程において、職場で発がん性を有する化学物質等や放射性物質等を、その労働者が取り扱っていたことすら明確にならなければ、裁判所はどのような判断を下すだろうか。このような場合は、訴えは認められないのである。
一方、その労働者が会社の安全配慮義務違反を理由に訴えて、その労働者が仕事で発がん性物質を取り扱っており、そのことと労働者ががんにり患したことの間に因果関係があることまで証明したが、事業者の側に過失があったか否かは不明瞭だという場合、他に特段の事情がなければそのような請求は認められることになる。
このように、ある事実について審議不明な場合に、不利益な判断を下される立場のことを挙証責任というわけである。
3 注意義務違反と不法行為責任
(1)不法行為とは
民法の不法行為とは「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること」である。ここにいう故意又は過失は、結果についてのものであり、原因に対するものではない。すなわち、機械設備の安全装置が無効となっていたためにけがをしたという場合を考えよう。
この場合、怪我をしない利益が侵害されたというのが"結果"である。そして故意があったというためには、結果である"怪我"をさせるという故意が必要で、原因である"機械設備の安全装置を外すこと"を故意に行ったというのは、本条にいう故意には当たらない。この場合は、機械設備の安全装置を外したことが、怪我という結果をもたらしたわけであるが、怪我という結果から見れば安全装置を外したことは過失になり得るにすぎない。
そして、故意に怪我をさせていれば、通常は、労働災害とはならないケースが多いであろうから、通常の労働災害では故意ではなく過失が問題となる。
なお、故意又は過失によって他人の権利等を侵害しても、その行為に違法性がなければ損害賠償責任を負うことはない。
(2)労働災害と不法行為
民法で不法行為に関する条文は、第3編債権の第5章が不法行為に当てられており、第709条から第724条までかなりの量がある。しかし、前述したように、実務上、労働災害に関する民事賠償の根拠となるのは、第709条、第715条、第717条のみである。しかも、第717条は産業保健の世界ではあまり使われることはない。
なお、労災事件で、不法行為責任を追及する場合は、事業者の側の注意義務違反によって不法行為が成立しているという主張をすることが多い。
ア 第709条
第709条は、不法行為を行ったものを、直接、訴える場合の条文である。例えば、会社そのものが労働者の労働災害の防止を図るための注意義務を果たさずに、有害な化学物質を安易に労働者に取り扱わせて、労働者が職業性疾病に罹患したという場合に、会社を訴えるようなケースである。
安全配慮義務と違い、事業者(会社、個人事業主)だけでなく、取締役や従業員、産業医などの、労働者と契約関係のない個人も訴えられ得る。例えば、安全の分野だが、労働者が作業している場所で、近隣住民からの苦情に対処するためバックブザーを切った状態で、フォークリフトをバックで走行させて労働者に激突して災害となった事例で、労働者が会社とともにその運転手を訴えたケースがある。この事件の判決は、その運転手、支店長及び会社は連帯して1,520万円を支払えという結論となった(東京地判平成18年4月7日)。
なお、ここではあえて安全分野の例を挙げたが、実際に従業員が訴えられるケースは、ハラスメントの場合がきわめて多い。虐め・嫌がらせによって精神障害に罹患したとか症状が悪化したというような場合である。他の分野では、実はあまり例は多くはない。
なお、公務員の場合には例外規定があり、原則として、業務遂行を行っていて第三者の権利を侵害した公務員個人を訴えることはできない。
また、元請けや発注者、親会社、子会社、機械設備や原料の製造者でも訴えることは可能であるし、元請けや親会社が訴えられるケースは現実にも少なくない。元請けや親会社が訴えられることが多いのは、カネのない会社や人を訴えても意味がないということもあるが、元請けや親会社が実質的に下請けや子会社の仕事の内容を管理していることが多いためでもある。
イ 第715条
第715条第1項は、会社には故意・過失はないが、その労働者が故意・過失によって第三者の権利を侵害したというような場合に、その会社を訴えるときの条文である。分かりやすくいえば、上司や同僚の注意義務違反によって災害が発生した場合に、会社を訴える根拠となる条文なのである。
もちろん、その労働者が会社の仕事をしていて、第三者に損害を与えたという場合でなければならない。もっとも、従業員がマイカー通勤の途中で交通事故を起こしたケースで、会社に民法715条を適用して損害賠償責任を認めたケースもある(福岡地飯塚支判平成10年8月5日など)。
なお、雇用関係がなくても、事業のために他人を使用している者に対して、その被用者の不法行為について賠償責任を問うことができる。
実際の労働災害で、会社に対して不法行為責任により損害賠償を請求しようという場合に、よく使われる条文である。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、損害賠償の請求はできないとされている。
第715条第2項は、使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負うとされている。事業を監督する者とは、実際上現実に使用者に代わって事業を監督する地位にある者のことである。具体的には、その被用者の選任・監督に携わる者が対象となる。工場長、中小企業の社長ばかりか、現場監督なども対象となり得る。工場長や現場監督については、不法行為を行った被用者の選任・監督にあたっていれば、「使用者に代わって事業を監督する者」と判断されることが多いので注意が必要である。
実際には、この条文は労働者が社外の第三者を被害者とする交通事故を起こした場合に、中小企業の代表取締役に民事賠償を請求するときに用いられることが多い。民法第715条2項に関しては、交通事故に関する判例をよくみかける。中小企業では、形式的に会社形式をとってはいるが、実質的に個人経営だという会社が多い。そうなると会社と代表取締役は別な"人"であるから、形式的に考えれば代表取締役に責任を問うことはできないことになる。しかし、実質的には代表取締役の個人経営で、会社には金はないが、代表取締役は資産家だというような場合がある。そのようなときには、この条文が使えるわけである。
また715条第3項には、前二項の規定は、「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」とされている。「求償権の行使」とは、ここでは弁償させることと考えて頂ければよい。
現実には、労働災害で求償権を行使するようなケースはめったにない。実際に求償権を行使するための訴えを起こしてみたところで、どれだけの金額が認められるかは不明であるし、認められたところで相手側にそれだけの財産がなければ意味はない。実際に支払われる金額よりも、訴訟費用の方が高くなることも考えられるからであろう。
4 安全配慮義務違反と不法行為責任の詳細
さて、安全配慮義務違反による債務不履行責任と、不法行為責任について、その違いに注目しながら、詳しく説明してゆこう。なお、訴訟に当たっては安全配慮義務と不法行為責任のどちらか一方でしか請求出来ないというわけではなく、両方を根拠にして訴えを起こすことの方が普通である。
安全配慮義務違反で訴えて請求が認められなかった場合に、不法行為責任で新たに訴えを起こすことができるかについては、理論的に考えるとできそうな気もするが、現実には認められないだろうと思う。
(1)挙証責任
先ほど説明した挙証責任について説明しよう。
繰り返しになるが、民事訴訟では、労働者の側が「事故に遭ったから損害賠償をしてくれ」といって訴えても、裁判所が自ら積極的に事実関係を調べてくれることはない。裁判所は当事者(原告と被告/労災の民事賠償裁判では、通常は労働者と会社)の言い分(主張)と彼らの提出する証拠をみて、判断を下すわけである。当事者が主張していないことについて裁判所が判断をすることはないし、原則として自ら証拠を探してくることもない。
たとえ本当に事業者の責任で災害に遭ったのだとしても、原告が以下のことを証明できなければ敗訴することになる。このことは、労災事件で民事賠償訴訟を行いにくい理由の一つであるとして、批判されることも多い。しかし、業務とはなんの関係もない怪我や疾病で訴えられた場合に、それが業務とは無関係だと事業者が証明できない限り、事業者が負けるというのはおかしいというのが民訴法の考え方なのである。
【不法行為責任】
- 加害行為の存在、損害の発生、損害額、加害行為と損害との因果関係を証明する必要あり。
- 被告に故意又は過失があることを証明する必要あり。
【安全配慮義務違反】
- 原告側が、安全配慮義務の内容を特定することの他、その不履行があったことを証明する必要がある。
- 原告側が、損害額及び業務(※)と損害との因果関係を証明する必要がある。
- ただし、被告の側に故意又は過失(又は履行補助者の故意又は過失)があることを証明する必要はない。
※ 最高裁(最3小判平成9年11月28日)は、安全配慮義務違反ではなく、業務と損害との因果関係を問題にする。しかし、業務と損害の間に因果関係があっても、ただちに事業者の側に損害賠償責任が生じるわけではない。厳密には、安全配慮義務違反と損害との因果関係が問題にされるべきであろう。
(2)時効
ア 民法改正前の災害
時効制度については、2020年4月1日施行の改正民法により、大きく変わっている。2020年4月1日前に発生した労働災害については、原則として改正前の規定が適用される。現実には、改正前の規定が適用されるケースも多いであろう。そこで、まず改正前の規定について、解説しよう。
改正前の民法では、不法行為の時効は、3年の短期時効の他20年という除斥期間が定められていた。いずれかひとつでも該当すると、時効で権利が消滅してしまうことがある。
【不法行為責任】
- 短期時効: 損害及び加害者を本人又は法定代理人が知ったときから3年
- 除斥期間: 不法行為の時(疾病では損害発生時)から20年
一方、安全配慮義務違反は、民法715条の債務不履行責任を「流用」しているといってよい。従って、事項についても、債務不履行責任と同じ10年で消滅することとなる。
【安全配慮義務違反】
- 損害(災害)が発生したときから10年。(じん肺では最終管理区分決定の時(死亡したときは死亡の時)から10年とする判例あり)
時効については、期間の長さだけでなく、起算点(いつから)が実務上きわめて重要となる。通常の債務不履行責任では、本来の債権を請求できるときから10年ということになっている。先述した売買契約の例では、買主が売主に対して「売買契約の対象となった物を引き渡せ」といえるようになってから10年が時効たつと損害賠償請求もできなくなるというのである。
ところが、これを労働災害の安全配慮義務違反に機械的に当てはめるとやや不都合な結果となることがある。労働災害の場合、本来の債務とは安全配慮義務である。そして、会社を辞めてしまえば安全配慮義務を果たせなどと言っても意味はない。そのため、債務不履行に関しての時効の一般的な理論を当てはめると、会社を辞めてから10年を経過すると損害賠償請求ができなくなるという結論になるのである。事実、過去の下級審判例ではそのような判断をするものもあった。しかし、職業がんやじん肺などでは、退職後10年以上たってから発症することもあり得る。そこで、最高裁の判例は、この一般理論を修正して損害が発生してから10年としたのである。
なお、不法行為については3年と20年の2種類が定められている。この20年の方は、除斥期間という、時効とはやや性格の違うものだという考えがあった。例えば、最判平成元年12月21日は、これを除斥期間と解する。この考え方に従うと、「事項の中断」という制度が適用されないのである。しかし、改正民法では明確に時効であるとされた。
※ 請求の権利を行使するなどにより、時効の進行を止め、再びその時点から新たに時効を進めるようにすること。すでに経過した時間はリセットされてゼロから進行する。
イ 民法改正後の災害
2020年4月1日以降に発生した災害については、改正後の民法が適用される。消滅時効の期間は、原則として「債権」と「債権以外」の2種類となった。また、時効の中断や停止という考え方も整理されている。
【2020年4月施行改正民法の時効の改正点】
- 債権の消滅時効期間が、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合は20年)に変更された。
- 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間に統一された(※)。
- 「中断」という用語が「更新」に、「停止」が「完成猶予」に変更され、その事由(原因)が修正された。
- 旧民法では、予め当事者が事項についての合意をすることはできなかったが、協議による時効の完成猶予に関する規定が新設された。
※ 不法行為責任については、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」という規定が残った。なお、所有権は放置しても消滅時効にはかからない。ただし、第三者が事項によって所有権を取得すると、元の所有者の所有権は消滅する。
安全配慮義務違反による民事賠償請求権は、債権の消滅時効にかかるため、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」で時効にかかり、また、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合」は災害発生時から20年でも時効にかかることとなった。これだけを見ると、有利になったのか不利になったのか判然としがたいが、実際には多くの労働災害で被災者や遺族が権利を行使することができることを知っていることが多いであろうから、実質的には10年が5年に短縮されたといえるだろう。
なお、改正前の民法では、債権の種類によって短期時効(旧民法170条~174条)を定めていたが、改正後はこれが削除され債権の消滅時効は1種類となった。
一方、不法行為責任については新724条の規定により「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年の経過」により消滅することとなる。20年が時効であると明記されたことが変更点である。先述したように、時効は中断することが可能なので、労働者にとって、やや有利になったといえようか。
(3)過失相殺
労働災害では、労働者の側にも過失がある場合がある。そのような場合には賠償額を減額処理されることがある。また、長時間労働などで精神障害を発症した場合などには、労働者の側に発症しやすいような素因があると、過失相殺の規定を準用して減額されることがある。
不法行為責任と安全配慮義務違反では、若干の違いがある。
【不法行為責任】
- 根拠は民法722条
- (裁判所は)原告の側に過失があれば、することができる。(しなくてもよい)
- 100%の過失相殺(結局、請求は認められない)は不可
【安全配慮義務違反】
- 根拠は民法418条
- (裁判所は)原告の側に過失があれば、しなければならない。
- 100%の過失相殺も可能
(4)損害賠償の範囲
損害賠償の範囲は、事業者の側の安全配慮義務違反や注意義務違反と相当因果関係のある損失に限られる。また、米国で認められているような「懲罰的賠償」の考え方は日本にはない。
死亡災害が発生すれば、近親者(遺族など)も精神的なダメージを受けることになる。しかし、近親者と事業者との間に契約関係があるわけではないので、債務不履行責任で遺族固有の慰謝料を請求することはできない。事業者が遺族に対する債務の不履行をしたわけではないからである。請求するのであれば、不法行為責任で請求するべきである。
では、本人が死亡している場合の本人の慰謝料はどうなるだろうか。かつて判例は、原則として遺族は本人の慰謝料を請求できないが、死亡時に債権として成立していればそれを相続して請求することは可能だとしていた。しかし、本人が即死した場合には慰謝料の請求は認めなかった。即死したのであれば精神的な苦痛など感じなかったはずという"論理"が根拠となっていたのである。
しかし、本人が即死した場合としばらく生きていた場合で請求できる範囲が異なるというのはいかにも不公平である。そこで、裁判所は請求できる範囲を拡大していった。本人が死亡する前に、「向こうが悪い、向こうが悪い」と言ったのは、慰謝料を請求する意思であるとして債権として成立していたと判断したり、死亡者が「残念、残念」と言ったのを慰謝料請求の意志であると判断してみたりといった形で慰謝料請求を認めるようになった。
しかし、さすがにばかばかしいと気が付いたのか、最近では即死した場合でも本人の慰謝料を認めるようになっている。
このほか注意すべきことは、訴訟の弁護士費用も損害に含まれるということである。もちろん、弁護士と不相当な金額で契約してもすべて認められるなどということはない。相当な金額に限られることは当然である。かつては、債務不履行責任による損害賠償については認められなかったが、平成24年に最高裁は安全配慮義務違反についても、損害として弁護士費用を認めた。
(5)加害者からの相殺の可否
裁判所によって、損害賠償の請求が認められた場合、被告の側が原告に対して債権を有していたとしよう。例えば、本人にも事故の原因となる過失があり、その事故によって事業者側が損害を受けていたというような場合などが考えられる。そのときに被告の側から、債権と損害賠償債務を相殺できるかという問題である。
この場合、不法行為による場合にはできないが、債務不履行による場合はできるとされている。大した違いはないと思うかもしれないが、不法行為の場合、たとえ損害賠償債務の数倍の債権を被告の側が有していたとしても、いったんはカネを支払わなければならない。そうすると、そのカネが他の債権者に差し押さえられてしまうかもしれないし、誰かに贈与されたり、何かの支払いに使われたりするかもしれない。
そのあとで、自らの債権を行使しようとしても、原告側に仮にカネがあったとしてもそれを支払わせるには大変な手間がかかるし、相手がすでに無一文になっていたらどうしようもないのである。
(6)賠償金への課税
賠償金への課税は、不法行為責任か債務不履行責任かでとくに違いはない。企業側でも労働者側でも課税対象とはならない。ただし、過大な見舞金・損害賠償金や、企業独自の判断で行う休業期間中の給与支払いなどは課税対象となり得るので注意が必要である。
【企業側】
- 心身に加えられた損害に対する損害賠償金は、消費税を含めて課税対象とはならない。原則として必要経費となる。
【労働者側】
- 心身に加えられた損害に対する損害賠償金は、原則として課税対象とならない。
- 本人が死亡した場合も、本人に対する慰謝料を含めて相続税の対象とならない。ただし、本人が存命中に賠償金の支払いが確定した場合は、その後、受領前に死亡した場合であっても相続税の対象となる。
(7)その他
その他、注意すべき事項としては以下のようなことがある。
- 不法行為(災害発生)の翌日から遅延損害金が発生する。
- 会社の分割のとき、個別に催告される。
【不法行為責任】
【安全配慮義務違反】
- 請求日の翌日から遅延損害金が発生する。(現実には訴状送達の翌日からということになる)
やや細かな話だが、不法行為の、会社分割のときの個別の催告について説明しておこう。会社が不法行為を行ったとき、債務を免れる手段として、会社分割の手続きをして、めぼしい財産を他の企業に移転してしまうことがある。ところが制度上は、債権者が一定の期間内に異議申し立てをしないと、会社分割を認めたようなことになってしまうのである。
そのため、会社法で、不法行為による損害賠償の債権者には個別に催告(お知らせ)をしなければならないようにしているわけである。債権者が、この催告をみて異議申し立てをすると、会社は債権者保護手続きをとらなければ会社分割ができないようになっている(登記ができない)のである。
5 その他の民事賠償責任
この他の、労働災害が発生したときの民事賠償の法律上の根拠としては、以下のようなものがある。
(1)会社法第429条第1項の責任
これについては先述したが、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うというものである。ここにいう悪意又は重大な過失とは、会社に対する任務懈怠(きちんと仕事をしなかったこと)についての、悪意又は重大な過失である。従って、役員として会社が第三者に対して損害を与えるようなことをしないように監視する仕事をしていなかったことを認識していた(悪意)場合には成立するということになる。
なお、この責任は不法行為責任とは別な法定の責任である。つまり時効は通常の債権に関する規定の10年が適用され、損害遅延金は請求したときから発生することとなる。
【ちょっと専門的な話】
法律の格言に「特別法は一般法を破る」というのがある。ある事実関係に適用される法条文について、一般的に適用される条文(一般法)と、ある特別な場合に適用される条文(特別法)があるときは、後者の方が優先して適用されるという趣旨である。
例えば、民法は人と人との関係一般について適用があり、労働基準法は事業者と労働者の間の関係について適用がある。この場合、事業者と労働者も人(法人も含む)であるから原則として民法の適用もある。しかし、同じことについて、民法と労働基準法の双方に、同じ事実関係について適用される規定があれば、労働基準法を優先して適用するのである。この場合、労働基準法の規程は、民法という一般法に対する特別法ということになる。
そこで、会社法429条の規定は民法の不法行為法の特別法ではないかとの説がある。つまり、会社法429条によって会社の役員等の責任が問われ得る場合には、その役員等は民法の不法行為の責任は問われないというのである。しかし、判例は、この場合は双方の規定が適用されるとして、このような考え方を否定している(最大判昭和44年11月26日)。
大阪高判平成23年5月25日(大庄事件)がいわゆる「過労死」にこの条文を適用している。この事件は上告されたが平成25年9月24日に棄却されて確定した。
(2)自賠責法第3条の責任
労働災害に関する民事訴訟で重要な条文に自賠責法第3条がある。自賠責法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」とされている。また、同条の但書には、「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない」とされている。しかし、この但書のような証明をすることは容易ではなく、実質的に無過失責任といってもよい。
本来は、労働者が業務上で、社外の第三者を被害者とする交通事故を起こした場合に、その被害者が会社に損害賠償を請求するときに使われることを想定した条文である。しかし、労働者が同僚の運転する会社の自動車で交通災害に遭ったときにも用いられることがある。なお、自賠法第3条にいう「他人」とは運行供用者と運転者は含まれず(最3小判昭和47年5月30日)、運転者には運転の補助に従事する者も含まれる。ややこしいが、運行供与者は当然のこととして、運転をしている者や運転の補助をしている者は、自賠法第3条によっては保護されないということである。
なお、自賠法第3条の責任の適用の有無と、自賠責保険の適用の有無とは直接リンクするわけではない。
注意しなければならないのは、労働者がマイカーを業務に使用しているような場合には、そのマイカーで事故が起きたときにも自賠法第3条の責任が発生するということである。その意味でもマイカーを業務に使用することは避けるようにするべきである。
6 その他の問題
(1)過失とは何か
基本的に、民事賠償における過失も、刑事罰編で述べたことと同じであると考えて頂いてよい。すなわち、過失とは、判例がほぼ一貫して採用する「新過失論」によれば
- ① 結果(労働災害)の発生を予見しなかったこと(結果予見義務違反)
- ② 予見した結果を回避しなかったこと(結果回避義務違反)
の2つの義務を果たさなかったことである。
刑事罰編の繰り返しになるが、ここでも問題は、例えば、有害性の知見のない化学物質を、有害性がないものとして労働者に取り扱わせていたが、そのときは判明していなかっただけで実は有害性があり、結果的に災害が発生したという場合などである。この場合は、事業者は結果を予見することはできなかったわけだから、過失はなく、責任は問われないのかということである。
これに関することだが、厚生労働省は、平成24年の胆管がん問題に関して通達(平成25年3月14日基発0314第1号)を発出している。これによると、(洗浄又は払拭の業務等の業務に限られてはいるが、)安衛法上、SDSの交付対象とならない物質(GHS分類を行った結果、有害性区分等を有しないもの)は、危険有害性が高いものとみなして取り扱うべきこととされている。ここでは、このことだけを指摘しておきたい。
(2)その他の問題
さて、ここまで述べてきたこと以外にも訴訟になるとさまざまなコストが発生する。それらの問題をいくつか取り上げよう。
ア 仮差押えの問題
仮差押えは、中小零細事業において問題となることで、ある程度の規模以上の企業では問題とはならない(裁判所がまず認めないからだ)が、意外と深刻な問題となることがある。
原告(労働者等)の側からみれば、訴訟して仮に勝訴したとしても執行(カネをとる)ができなければ意味がない。そのため、(小規模の企業や個人事業主などを訴えるときは)民事保全法により、訴訟の前に会社の債権(や不動産)に仮差押えをかけることがあるのである(通常は供託金(請求金額の2~3割が相場)が必要)。
これが会社の「信用」に影響を与えることがある。例えば、不動産に仮差押えをかけられた場合、法律上は売買することも、抵当権の設定も可能だが、現実にはそのようなことはできなくなると思った方がよい。
なお、保全命令(仮差押命令等)に対しては、保全異議の申立てや保全取消しの制度がある。また、執行の停止(又は既にした執行の取消し)には仮差押解放金の供託という方法がある。訴える前に、カネの積みあいをすることになるわけである。
イ 裁判所の場所の問題
訴訟実務では、どこ(場所)の裁判所が管轄するかがきわめて重要であり、これだけで決定的な影響があることもある。例えば、東京の会社が福岡で訴えられたとした場合、請求金額が100万円程度なら、争わずに敗訴してしまった方がかえって安くつくこともある。
そして、損害賠償請求事件では、原告の住所地の地裁又は簡裁に訴えることができる(民訴法5条1号 + 民法484条)のである。距離的に離れた裁判所で訴訟することのコストはかなり大きい。労働者を雇用するときに裁判所の管轄を契約で決めることはまずないので、訴えられるときは、どこで訴えられるか分からないと思っておいた方がよい。
また管轄の問題とは別な話だが、外国人を雇用していて労災が発生した場合に、その外国人が自国で訴訟をすることが認められるケースがある。こうなると、外国で訴訟をする費用は膨大なものになってしまう。
ウ 弁護士費用
弁護士報酬が意外と高額になることがある(弁護士への依頼を否定的に考えているわけではない。専門家に依頼したからこそ賠償額が低く済むということもあろう)。
ところが、勝訴しても原告からは回収できない(民訴法61条の訴訟費用に含まれない)のだ。なお、原告の訴えが不法行為になるような場合には、弁護士費用を原告に請求できるという判例があるが、実際に訴えても訴訟倒れになる可能性もあり、通常は請求しない。
ただし、負けたときは労働者側の弁護士費用も払わされることになる。こちらは「損害」に含まれるためである。