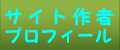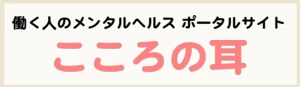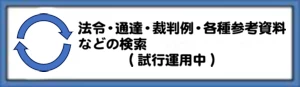2017年に民法が大幅に改正をされました。このうち、消滅時効と法定利率は災害発生時の損害賠償請求に大きな影響を与えます。
民法改正のうち、産業保健担当者が知っておくべき項目について、かみ砕いて解説をします。
1 はじめに
執筆日時:
最終改訂:
(1)民法の大改正
2017年6月2日、民放の大幅な改正が公布された。我々の生活に密接した法律で、しかも策定以来、120年間にわたり、ほとんど動きがなかったものだけに、これだけ大きな改正があると、様ざまな影響があるのではないかと思われている方も多かったのではないだろうか。しかし、改正事項の多くは、判例の積み重ね(判例法理)を条文化したものが多く、改正条文が多い割に、専門家はそれほど大きな影響はないという評価が多かった。
しかし、実務家や事業者から改正の要望が大きかった事項を中心に、判例法理とは別な、いくつかの実質的な改正も行われている。例を挙げれば、①消滅時効制度と②法定利率がある。そして、この2つは、労働災害が発生した場合の民事賠償にも直接かかわってくる。
なお、この他の実質的な改正としては、③保証に関する見直し、④主債務の履行状況に関する情報提供義務、⑤債権譲渡に関する見直し、⑥約款(定型約款)に関する規定の新設などがある。
(2)労基法との関係
ア 改正前の賃金の時効の規定
消滅時効制度改正のひとつとして、“賃金に関する債権”をはじめとする短期消滅時効に関する規定がすべて削除されたことが挙げられる。これにより、賃金債権に関して、労働基準法との逆転現象が起きてしまったのだ。
改正前には、民法第174条により、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は1年の短期消滅時効にかかるとされていた。しかし、これではあまりに短いというので、労働者を保護する観点から、労働基準法(労基法)に第115条を設けて、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と定めたのである。
イ 改正前の民法と労基法の関係
そして、法令の規定は、一般的な規定よりも、対象の範囲が狭い特別の規定の方が優先して適用されるのである。これを法格言で“特別法は一般法を破る”という。
民法第174条の賃金債権の消滅時効の規定は“すべての使用人の給料に係る債権”に適用されるが、労基法第115条の規定は“労基法上の労働者の、会社等(使用者)に対する賃金債権”などにのみ適用される。
すなわち、労基法の“労働者”よりも民法の“使用人”の方が対象の範囲が広いので、民法の規定が一般法、労基法の規定が特別法となって、労基法の規定が民法の短期消滅時効の規定に優先されて適用されていたのである。そのため改正前の民法第174条は、家事使用人など労働基準法の適用のないごく一部の労働者にしか適用されていなかった。
ウ 改正後の労基法との逆転現象と現在の動き
ところが、今度の民法の改正で短期時効の規定が削除されてしまい、これまで民法第174条が適用されていた使用人の賃金債権についても、新しい消滅時効の規定である新166条(短期時効5年、長期時効10年)が適用されることになった。
しかし、労基法が民法よりも優先されて適用されることに変わりはないため、労基法の労働者ではない使用人の給料にかかる債権の消滅時効は5年(長期10年)の消滅時効であるにもかかわらず、労基法上の労働者の賃金債権は2年の消滅時効にかかるという逆転現象が起きたのである。
これでは、労基法が労働者を保護するという趣旨に反することとなるとされ、厚労省の委員会での検討、審議会での審議を経て、労基法の規定も以下のように改正された。
| 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|
|
|
|
すなわち、労基法本文では消滅時効は5年間とされたものの、附則で当分の間は3年とされたため、若干の緩和はされたものの逆転現象は解消されなかったのである。
これはいわゆる「サービス残業」(賃金不払い残業)が発覚したときに、企業側の支払いが膨大となるため、企業側に配慮したものとしか思えない。賃金債権の消滅時効が問題となるのは、実質的に「サービス残業」発覚時くらいのものだからである。
なお、この改正は改正民法が施行された2020年(令和2年)4月1日から施行されている。なお、改正消滅時効が適用されるのは施行の日(2020年4月1日)以降に発生した賃金債権であり、それまでに発生した賃金債権は2年の消滅時効にかかるので留意が必要である。
関係条文を挙げると次のようになっている。消滅時効について、当分の間は3年と定めているのは、附則143条の第3項である。
【労働基準法】
(記録の保存)
第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
(付加金の支払)
第114条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
【労働基準法附則】
第143条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
【労働基準法附則(令和二年三月三一日法律第一三号)】
(施行期日)
第1条 この法律は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
(付加金の支払及び時効に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第百十四条及び第百四十三条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第百十四条に規定する違反がある場合における付加金の支払に係る請求について適用し、施行日前にこの法律による改正前の労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合における付加金の支払に係る請求については、なお従前の例による。
2 新法第百十五条及び第百四十三条第三項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。
(3)労災発生時の民事賠償と民法改正との関係
さて、先ほども述べたように、時効制度と法定利率の改正は、労働災害が発生した場合の民事賠償の問題にかかわってくる。そこで、本稿では、時効制度を中心に民法改正の内容について説明する。
2 改正民法の概要
(1)時効制度
かつて、公務員(自衛隊員)について安全配慮義務違反による民事賠償請求を最高裁が最初に認めたとき、実は不法行為責任は消滅時効にかかっていたのである。そのため、原告側は、あえてその当時は公務員には認められていなかった(※)安全配慮義務違反を追及したのである。そのことからも分かるように、時効期間は、実務上でも、意外に重要な意味を持つことがあるのだ。
※ それまで、下級審は、民間の場合は安全配慮義務違反による損害賠償請求権の存在を認めていたが、公務員には認めていなかった。そのため、民間の労働者の場合は最高裁まで争われたことがなかったが、本件は最高裁まで争われたわけである。
さて、よく知られているように、労働災害が発生した場合の民事賠償請求の法的な構成は大きく2通りある。1つは債務不履行としての安全配慮義務違反を問うものであり、もうひとつは不法行為責任を問うものである。今回の民法改正では、その双方について時効の制度が変更されている。まず安全配慮義務違反(債権関係)の方から見てゆこう。
ア 債権(安全配慮義務)
(ア)債権に関する改正
債権関係の時効制度は、次表のように改正されている。なお、安全配慮義務と関係の薄いものは省略した。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|
|
(債権等の消滅時効) 第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 2 (略) 3 (略) (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。 |
(消滅時効の進行等) 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 (略) (債権等の消滅時効) 第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 (略) |
(イ)時効期間
前表を見れば分かるように、改正前は第167条で10年間の時効のみが定められていたが、改正後は第166条で短期5年と長期10年の2つの時効が定められ、第167条で人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、長期20年とされた。従って、新民法の下では、安全配慮義務違反による民事賠償請求権は、短期5年、長期20年のいずれかの時効が完成したときに、消滅時効にかかることとなる。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|
|
|
今回の改正では、権利を行使することができる時からの時効が20年に延長されたとはいえ、5年という短期時効制度が創設されたのであるから、実質的にみれば原告(労働者)にとって不利になったと言えよう。労働災害が事故による負傷であれば、通常であれば、災害発生と同時に被災者は「行使することができること」を知ることになるからである。
その意味で、実質的に考えれば、時効期間は改正によって半分に短縮されたと考えることができる。
(ウ)時効の起算点
a 長期時効
では、長期時効の「権利を行使することができる時」とは、いつのことであろうか。
まず、債券一般のことを述べよう。債権者(甲)と債務者(乙)がいて、乙がその債務(A債務)を履行しないとする。そのために甲に損害が生じたとすると、甲は乙に対して損害賠償を請求することができる(民法415条)。
そして、甲にとって権利を行使することができる時とは、賠償の請求ができる時(損害が発生した時)ではなく、本来の債務の履行を請求できる時なのである。
そして、安全配慮義務違反による民事賠償請求であっても、法律的な構成は、この損害賠償の請求と同じである。そこで、この理論を安全配慮義務違反による民事賠償に当てはめると、本来の債務とは安全を配慮する義務ということになる。従って、権利を行使することができる時とは、事業者に安全を配慮せよと請求できる時=通常は災害が発生した時であろう=ということになる。
ところが、このことを徹底すると、職業性疾病の場合に不都合が起きることがある。すなわち、会社を辞めて21年後に発症したとしよう。この場合、会社を辞めた後は、安全配慮義務など履行のしようもない。従って、権利を行使することができる時とは会社を辞める前ということになる。すなわち、会社を辞めて20年が経過してから職業性疾病に罹患すると、民事賠償が請求できなくなるということになりかねないのである。
このことは改正前の民法第167条では10年だったから、問題はさらに深刻であった。当初、下級審判例は、この理論を採用して退職後時効期間経過後には賠償請求ができないとするものと、できるとするものに分かれていたが、最高裁判例はこれをできるとした。
最高裁は、権利を行使することができる時(時効の起算点)を「疾病の発症の時」としたのである。なお、じん肺については、最終の管理区分決定の時とし、本人が死亡しているときは死亡の時(※)としている。
※ 本稿では詳細は省略するが、死亡時別途進行説を採用している。
この考え方は、改正後においても継承されるものと考えられる。
b 短期時効
次に短期時効の起算点である「権利を行使することができることを知った時」とは、いつのことだろうか。先ほども述べたように、アクシデントによる負傷などでは、損害の発生の時には権利を行使することができると分かるだろうから、長期時効の起算点と一致するであろう。
なお、権利を行使することができることを知った時とは、先ほどのじん肺に関する最高裁の判決に照らせば、損害賠償請求ができるという事実関係を知った時であって、それが法的に請求できることを知った時ではないこととなる。しかし、札幌地判平成22年3月26日などは、本人が法律的に損害賠償請求をできると知った時であるとしているようだ。
問題は職業性疾病の場合にどうなるかである。じん肺などでは、それが職業性の疾病であるということは判っているであろう(判っていなければそもそも管理区分決定を行政に申請しないであろう)が、職業性がんなどでは必ずしもそうではないからである。
例えば、大阪の印刷業で胆管がんが発症した事件の発覚前に、印刷業で働いていて胆管がんに罹患した労働者(丙)がいたとしよう。丙が、大阪の印刷業の事件を知って、自らも職業性疾病ではないかと考えたが、すでに発症から5年を経過していたというような場合である。
これは、私見だが、後述する最判昭和48年11月16日の理論に照らせば、客観的にみて一般人が損害賠償を請求できると知り得るような事実関係を知った時と考えるべきであろう。従って、この場合も損害賠償請求は可能であると考える。
イ 不法行為制度
(ア)不法行為に関する改正
不法行為関連の時効制度の改正点は、次表のようになっている。新たに724条の2が追加されて、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について期間の延長が行われて、改正前の3年から5年に変更されている。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|
|
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。 |
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 |
以上をまとめて単純化すると、次表のようになる。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|
|
|
(イ)短期時効の期間の延長
すなわち、労災による民事賠償は、「人の生命又は身体を害する不法行為」であるから、実質的に短期時効が3年から5年に延長されて、安全配慮義務と同じになったわけである。これが、原告にとって有利となることはいうまでもない。
なお、「損害及び加害者を知った時」とは、「賠償請求が事実上可能な程度に知った時」(最判昭和48年11月16日)と考えられている。今回の改正後によって、この考え方が変更されることはないものと思われる。
(ウ)20年が時効であることの明確化
また、改正前の第724条後段については、かつては時効なのか除斥期間なのかが争われていた。そして、1989年に最高裁判例はこれを除斥期間であると明言した。しかし、近年では、通説は、これを時効説としており、今回の改正では、通説に従って時効であると明記されたことになる。
これを除斥期間として形式的に適用すると、時効と異なり、除斥期間には更新(中断)制度がないことなどから、不法行為の時から20年間を経過すると、ほぼ確実に消滅してしまう。従って、これが時効であると明言されたことは、原告側にとって有利な改正といえよう。
【除斥期間と時効の違い】
- 時効の効力は、その起算日にさかのぼる(民法144条)が、除斥期間にはそのような効果はないと考えられている。
- 消滅時効には更新(改正前の中断)が認められ(同改正後147条、148条)、一定の事由によって、それまでの期間の経過は効力を失い、その事由の終了の時点から新たに時効期間が進行するが、除斥期間にはそのような制度はない。
- 消滅時効の効力は、時効によって利益を受ける者が援用しなければ効力が発生しないのに対し(同145条)、除斥期間はそのようなことはなく期間の経過によって当然に効果が生じる。
1989年に、最高裁がこれを除斥期間としたことで、その後、問題となる事案が生じた。それは、不法行為の時から20年以上の期間を経て発症する疾病などである。例えば、じん肺、公害病(水俣病)、薬害(予防接種によるB型肝炎)などについて、これを形式的に除斥期間とすると、病気に罹患したにもかかわらず民事的に救済されない場合が出てきてしまうのである。
そのため、判例は、起算点の「不法行為の時」を「損害の全部または一部が発生した時」であるとして、被害者の救済を図った。
ところが、今回の改正でも、長期時効の起算点は「不法行為の時」のままとなっており、「損害の発生時」とはされなかった。時効と明記されたのであるから、「不法行為の時」を「損害の全部または一部が発生した時」であるとする必要はなくなったと考える余地もあるかもしれないが、時効と明記されたとしても、起算点についての判例の考え方は変わらないのではないかと思う。
ウ その他
(ア)用語の改正
時効に関する法律用語として、分かりにくいと悪評のあった「中断」が「更新」、「停止」が「完成猶予」と修正された。
なお、時効の更新とは、法定の事由があったときに、それまでに経過した時効期間がリセットされ、改めてゼロから起算されることである。その事由が終了した時から新たな時効期間が再び進行する。
また、完成猶予とは、時効が完成する際に、権利者が時効の中断をすることができない場合に、法定の事由があれば、その事由が消滅した後一定期間が経過するまでの間、時効の完成を猶予するものである。
(イ)更新(中断)される場合の縮小
そして、裁判上の請求、支払督促、調停、破産手続等への参加については、改正までは、それだけで中断(改正後の更新)の事由とされてきたのだが、改正後は、新第147条により、それだけでは完成猶予(停止)されるのみで、確定判決や裁判上の和解などで権利が確定しない限り更新されないこととされたのである。
この改正は、原告側に不利になると思われるが、実務上はそれほど大きな影響はないように思える。
なお、強制執行の手続きが終了した場合(新148条)や、相手側の承認(新152条)の場合も時効が更新されることとされているが、これは従来と変わらない。
(ウ)完成猶予(停止)
改正後の民法で、完成猶予(停止)されるとされているものに、仮差押え(新149条)、催告(新150条)、協議合意(新151条)、天災(新161条)がある。これらのうち、新151条の協議合意は、新たに設けられたものである。また、天災等について旧161条の猶予期間は2週間とされていたが、新161条で3か月に延長された。
この改正は、原告側やや有利になると思われるが、実務上はそれほど大きな影響はないように思える。なお、原告と被告の協議が整えば、時効を完成させないだけのために、訴えを起こさなければならなくなるということはなくなる。
(エ)その他
時効の援用権者について、第145条に「消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む」との例示列挙がされた。
その他、商行為によって生じた債権について5年間の短期時効を定めていた商法第522条は、意味がなくなったことから削除された。
(2)法定利率
法定利率は、民法策定当時から5%とされており、最近では、かなり非常識な値になっていた。交通事故などでも、訴訟で争いが長くなると、賠償金の利子がばかにならなくなるため、加害者側が相当と考える金額を供託することも多かったほどである。
そのため、利率について改正の要望が強かったが、改正後は、当面3%とし、6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率を基にして、変動させることになった。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|
|
(法定利率) 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 2 法定利率は、年3パーセントとする。 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。 4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。 5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。 |
(法定利率) 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 |
人の生命又は身体を害されたことによる民事損害賠償では、将来発生する損害(働けなくなった場合の将来の賃金損失や将来の治療費等)を法定利率で割り引いて、一時金として算出することが普通なので、一般には法定利率が下がることは、原告に有利になるものと思われる。
しかし、不法行為責任では、損害発生の翌日から遅延損害金が発生し、安全配慮義務違反(債務不履行)の場合は請求日の翌日(実際には訴状送達の翌日)から遅延損害金が発生する。この遅延損害金も法定利率で計算されるので、原告側が不利になることもあり得よう。
(3)施行日
民法改正は、一部の規定を除き,2020年(平成32年)4月1日から施行されている。なお、一部の例外とは、定型約款に関する規定と、公証人による保証意思の確認手続に関する規定である。