問13 次のイ~トのうち、労働安全衛生法令上の免許でないもののみの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ ガス溶接作業主任者免許
ロ 林業架線作業主任者免許
ハ 船内荷役作業主任者免許
ニ 揚貨装置運転士免許
ホ 特別ボイラー溶接士免許
ヘ フォークローダー運転士免許
ト 発破技士免許
(1)イ ハ
(2)イ ホ
(3)ロ へ
(4)ハ へ
(5)ニ ト
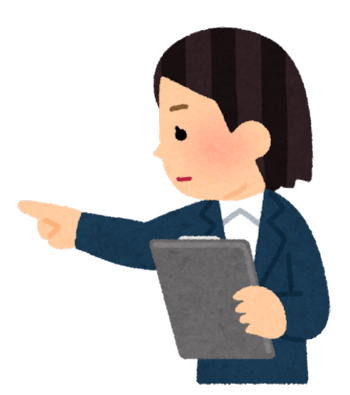
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2017年度(平成29年度) | 問13 | 難易度 | 免許制度に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法令の免許 | 1 |
問13 次のイ~トのうち、労働安全衛生法令上の免許でないもののみの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ ガス溶接作業主任者免許
ロ 林業架線作業主任者免許
ハ 船内荷役作業主任者免許
ニ 揚貨装置運転士免許
ホ 特別ボイラー溶接士免許
ヘ フォークローダー運転士免許
ト 発破技士免許
(1)イ ハ
(2)イ ホ
(3)ロ へ
(4)ハ へ
(5)ニ ト
正答(4)
【解説】
安衛法上、免許等を受けることが必要なもののひとつに、安衛法第12条による「衛生管理者」がある。また、免許、技能講習の修了等が必要なものに、同第14条による「作業主任者」及び同第61条による「就業制限」がある。
そして、作業主任者が必要な作業と就業制限を受ける業務の範囲は政令で定められる。一方、どのような資格が必要かは省令に定められている。
どのような業務や作業主任者に、どのような資格が必要かについては、厚生労働省の「労働安全衛生法に定める資格等一覧」を参照されたい。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)
以下により、正答は(4)となる。
イ 免許である。ガス溶接作業主任者、安衛則第 314 条により免許である。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 (略)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 (略)
(ガス溶接作業主任者の選任)
第314条 事業者は、令第6条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
別表第一 (第十六条、第十七条関係)
| 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) |
| 令第6条第二号の作業 | ガス溶接作業主任者免許を受けた者 | ガス溶接作業主任者 |
| (略) | (略) | (略) |
ロ 免許である。林業架線作業主任者は、安衛則第 151 条の 126 により免許である。
【労働安全衛生法施行令】
(ガス溶接作業主任者の選任)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ~ハ (略)
四~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 (略)
(ガス溶接作業主任者の選任)
第151条の126 事業者は、令第6条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
別表第一 (第十六条、第十七条関係)
| 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) |
| 令第六条第三号の作業 | 林業架線作業主任者免許を受けた者 | 林業架線作業主任者 |
| (略) | (略) | (略) |
ハ 誤り。船内荷役作業主任者は免許ではなく技能講習である(安衛則第 450 条参照)。
【労働安全衛生法施行令】
(ガス溶接作業主任者の選任)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~十二 (略)
十三 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が500トン未満から500トン以上となつたもの(510トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(技能講習の受講資格及び講習科目)
第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 (略)
(船内荷役作業主任者の選任)
第450条 事業者は、令第6条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
別表第一 (第十六条、第十七条関係)
| 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) |
| 令第6条第十三号の作業 | 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 | 船内荷役作業主任者 |
| (略) | (略) | (略) |
ニ 免許である。揚貨装置運転士は、安衛則第 41 条及び同規則別表第三により免許となる。
【労働安全衛生法施行令】
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 (略)
二 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
三~十六 (略)
【労働安全衛生規則】
(就業制限についての資格)
第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第三 (四十一条関係)
| 業務の区分 | 業務につくことができる者 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 令第20条第二号の業務 | 揚貨装置運転士免許を受けた者 |
| (略) | (略) |
ホ 免許である。特別ボイラー溶接士は、安衛則第 41 条及び同規則別表第三により免許となる。
【労働安全衛生法施行令】
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五~十六 (略)
【労働安全衛生規則】
(就業制限についての資格)
第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第三 (四十一条関係)
| 業務の区分 | 業務につくことができる者 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 令第20条第四号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | 特別ボイラー溶接士免許を受けた者 |
| 令第20条第四号の業務のうち溶接部の厚さが25ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務 | 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者 |
| (略) | (略) |
ヘ 技能講習である。最大荷重が1トン以上のフォークローダーの運転には、ショベルローダー等運転技能講習の修了が必要となる(安衛則別表第三)。なお、安衛則では特に規定されていないが、「ショベルローダー等」という用語には、通常、フォークローダーが含まれる(安衛法別表第 19 参照)。
【労働安全衛生法施行令】
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十二 (略)
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四~十六 (略)
【労働安全衛生規則】
(就業制限についての資格)
第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第三 (四十一条関係)
| 業務の区分 | 業務につくことができる者 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 令第20条第十三号の業務 |
一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
| (略) | (略) |
ト 免許である。発破技士は、安衛則第 41 条及び同規則別表第三により免許である。
【労働安全衛生法施行令】
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二~十六 (略)
【労働安全衛生規則】
(就業制限についての資格)
第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第三 (四十一条関係)
| 業務の区分 | 業務につくことができる者 |
|---|---|
| 令第20条第一号の業務 |
一 発破技士免許を受けた者 二 火薬類取締法第31条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者 三 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験に合格した者 |
| (略) | (略) |









