問3 機械設備について事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)連続した一団の機械で、共通の動力しゃ断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものには、機械ごとの動力しゃ断装置を設けなかった。
(2)木材加工用の横切用丸のこ盤で、反ばつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものには、反ぱつ予防装置を設けなかった。
(3)動力で駆動される遠心機械について、1年2か月間使用しなかったが、その問、1年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなかった。
(4)機械の刃部の調整の作業において、機械の構造上、労働者に危険を及ぼすおそれがないものであったので、当該調整作業の問、機械の運転を停止したが、起動装置に錠をかけたり表示板を取り付けることはしなかった。
(5)食品加工用ロール機を使用して食品の原材料を圧延するとき、労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に覆い、囲い等を設けることが作業の性質上困難であったので、当該箇所に覆い、固い等を設けないで労働者に用具を使用させて作業を行わせた。
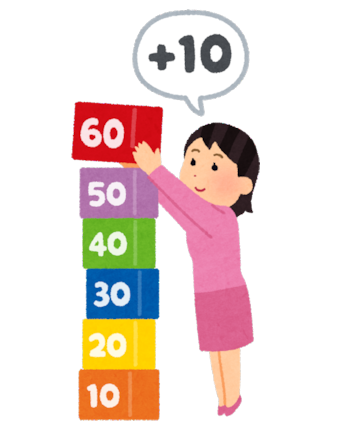
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2014年度(平成26年度) | 問03 | 難易度 | 機械による危険の防止に関するやや詳細な知識問題。難問の部類だろうか。 |
|---|---|---|---|
| 機械による危険の防止 | 5 |
問3 機械設備について事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)連続した一団の機械で、共通の動力しゃ断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものには、機械ごとの動力しゃ断装置を設けなかった。
(2)木材加工用の横切用丸のこ盤で、反ばつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものには、反ぱつ予防装置を設けなかった。
(3)動力で駆動される遠心機械について、1年2か月間使用しなかったが、その問、1年以内ごとに1回の定期自主検査を行わなかった。
(4)機械の刃部の調整の作業において、機械の構造上、労働者に危険を及ぼすおそれがないものであったので、当該調整作業の問、機械の運転を停止したが、起動装置に錠をかけたり表示板を取り付けることはしなかった。
(5)食品加工用ロール機を使用して食品の原材料を圧延するとき、労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に覆い、囲い等を設けることが作業の性質上困難であったので、当該箇所に覆い、固い等を設けないで労働者に用具を使用させて作業を行わせた。
正答(5)
【解説】
(1)違反とはならない。安衛則第 103 条は、原則として「機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない」とするが、但書において「ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない」としている。
【労働安全衛生規則】
(動力しや断装置)
第103条 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2及び3 (略)
(2)違反とはならない。安衛則第 122 条は、木材加工用丸のこ盤には、原則として割刃(※)その他の反ぱつ予防装置を設けなければならないとする。しかし、「横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く」とされている。従って、本肢の場合に反ぱつ予防装置を設けなくても違反とはならない
※ 割刃とは、丸のこの刃を覆うカバーのような形状をしており、切断される材料を押さえるような作用をする。実務においては、「刃先が見えない」「材料を切断するときに、材料が動かしにくい」などの理由で、外されていることがあるので注意する必要がある。
※1 図は、厚生労働省「雇用環境・均等局作成テキスト」より引用
【労働安全衛生規則】
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第122条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
(3)違反とはならない。安衛則第 141 条但書は、動力により駆動される遠心機械について「1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては」、定期自主検査の義務を除外している。従って、本肢については、ただちに違反とはならない。
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第141条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五 (略)
2~4 (略)
(4)違反とはならない。安衛則第 108 条第1項は、機械の刃部の調整の作業においては、原則として機械の運転を停止しなければならないとする。しかし、機械の構造上、労働者に危険を及ぼすおそれがないときは除外している。
すなわち、本肢の場合、調整作業の問、機械の運転を停止したが、これは同条第1項の規定により運転の停止をしたわけではない。従って同条第2項の適用はなく、起動装置に錠をかけたり表示板を取り付けることはしなくとも違反にはならない。
もっとも、運転したまま安全に調整を行える設備だったとしても、運転を停止した状態で調整を行っているときに、ふいに動き出せば労働者に危険を及ぼすことは考えられる。やや設問が非常識ではないかという気がしないでもない。
【労働安全衛生規則】
(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)
第108条 事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3及び4 (略)
(5)違反となる。安衛則第 130 条の8は、「食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない」とする。これには本肢のような例外規定はない。
なお、食品加工用ロール機とは、製麺用ロール機、製菓用ロール機等の食品の原材料を圧延する機械のことである。原材料の送給に必要な箇所を除けば、覆い又は囲いを設けることが困難なことは考えにくい。
また、「覆い、囲い等」の「等」には光線式安全装置及び作業を行う労働者が自ら操作できる急停止装置が含まれるのである(※)から、原材料の送給に必要な箇所についても、これらを取り付けることが困難ということはないだろう。
※ 平成 25 年4月 12 日基発 0412 第 13 号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(抄)」の記の第2の1の(1)のウの④参照
この点、安衛則第 143 条のような、粉砕機又は混合機から内容物を取り出す場合とはわけが違うのである。
【労働安全衛生規則】
(ロール機の覆い等)
第130条の8 事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
(内容物を取り出す場合の運転停止)
第143条 事業者は、粉砕機又は混合機(第130条の5第1項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
2 (略)










