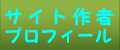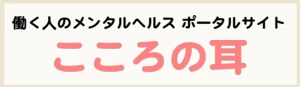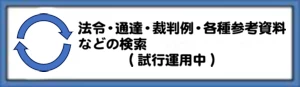このページは、2017年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問18を題材に、労働災害が発生した場合の損害額と労災補償額の大小関係を論じています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
問題の解説そのものをご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2019年12月01日執筆
2020年03月21日修正
1 初めに
2017年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問28及び労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」の問1に、「法令に基づいて被災者に支払われる労災保険による補償費」と「これ以外の損失及び費用」のどちらが「一般に」大きいかを問う問題が出題されている。
最初これを見たとき、「労災保険による補償額」と「全損害額」の比較の問題だと思い込んでしまった。まさか、補償給付とその他の損失・費用の比較ができるとは思えなかったからだ。
とはいえ、現に、このような出題がされているのである。だとすれば、何か根拠となる調査研究が行われているのであろう。おそらく、労働政策研究・研修機構が独自に行った調査研究か、厚労科研で行われたか、厚生労働省の委託事業で行われたのではないかと考えて、かなり調べてみたのだが、そのような文献やデータは見つからなかった(※)。
※ そもそもそのような調査研究があれば、学者が個人で行った小規模なものは別にして、筆者(柳川)が知らないはずがないと思うのだが。
ただ、このような調査研究を行うとすれば、その方法は下記のいずれかによるしかないであろう。
- ① 事業者に対する質問票又は面接による調査
- ② 裁判例の分析
- ③ 理論的な推計
しかし、この問いは「労働災害」全体について尋ねており、訴訟となった労働災害について尋ねているのではない。であれば、②とは考えにくい。また、③についてはこのような事項について合理的な推計ができるとも思えない。おそらく①によったのではなかろうかと思われる。
2 労災補償給付とその他の費用の推計の試み
しかし、そのような文献が見つからない以上、本問を個人が解こうとすれば、事業者に対する調査を現実に行うことは不可能であるから、推定によるしかない。そこで、推計をしてみることにしよう。
(1)前提条件(労働災害をどのようにとらえるか等)
そもそも、この問題は前提が必ずしも明確ではない。①本肢にいう労働災害には、労災補償が行われない救急箱災害は含まれるのだろうか。②労災補償給付がされない損失及び費用の範囲はどこまでなのだろうか。③さらには「一般的に」という言葉の意味をどう理解するべきだろうか。
本問にこたえるには、これらが明らかになっていなければならないが、問題文が何も言っていない以上、これらを“推理”しなければならない。
ア 考慮する労働災害の範囲
まず、本問にいう労働災害とはどの範囲を言うのかが問題となる。これが問題となるのは次のような理由である。
法律上の定義では、いわゆる“救急箱災害”も労働災害に含まれる。しかし、救急箱災害には労災補償給付は行われないので、出題者の意図としては本問の対象外としているのではないかとも考えられるのである。また、通常、労働災害といえば、統計では休業4日以上のものを指すので、出題者が無意識のうちにそれに限っていたのではないか、さらには、損害と費用が公的にかつ金額まで算定されているのは、訴訟で判決が出たもののみだろうから、訴訟で確定判決が出たものに限っているのではないかとも思われるのである。
しかし、このような疑問はあるものの、本問ではたんに“労働災害”として、限定はしていない。そこで、とりあえず救急箱災害を含むすべての災害と考えよう。
イ 費用と損害の範囲
次に、費用と損害の範囲がどこまでかである。これは、常識的には災害と相当因果関係のある損害および費用ということになろう。しかし、それを算定するのは極めて困難な面もある。やはり、ある程度の前提が必要となるのである。具体的に説明しよう。
(ア)会社側に発生する費用・損害
会社側に発生する費用・損害としては以下のようなものが考えられる(※)。
- ① 発生時の被災者の救護、医療機関への搬送、関係方面への連絡等の人件費等
- ② 災害の原因や事実関係の調査の費用
- ③ 関係機関への報告等の事務作業の費用
- ④ 災害直後の生産の一時的な停止による損害および生産ラインを再稼働するための費用
- ⑤ 事故処理、本人不在等による生産の停滞のための費用
- ⑥ 本人の休業中に他の労働者が代替するための費用
- ⑦ 社会的な制裁(入札からの排除、報道等による社会的信頼の失墜等)による損害
- ⑧ 訴訟になった場合の訴訟の費用
※ なお、再発防止のための対策の費用が、損害額に含まれないことは当然である。それは、災害が起きたから発生した費用ではなく、本来、発生する前に行っておくべき(支出しておくべきもの)だからである。
仮に出題者が対策の費用を全損害額に含めて出題していたとしたら、そのことだけでも出題ミスというべきである。
(イ)本人側に発生する費用・損害
また、本人側の損害としては、以下のものが考えられる。
そして、労災給付されないもののうち、最も重要なものは、③の本人及び関係者の精神的苦痛による損害である。これは、訴訟等になって債権として確定すれば顕在化するが、実際にはそうなっていないケースがほとんどであろう。その場合に、実際に精神的苦痛は存在しているのだから損害が発生していると考えるのか、債権として確定していないから発生していないと考えるのかが問題となる。
ただ、苦痛を受けているという事実は存在しているのであるから、損害は発生しているわけであり、問題文でも特に限定していないので本問にいう「損害」に含まれると考えよう。そうすると今度は、損害が発生しているとして、どのように金銭に換算するのかが問題となる。
- ① 医療機関での治療の費用(療養費)
- ② 入院のための付き添い、自宅療養中の介護の費用
- ③ 休業による賃金の損害
- ④ 本人の精神的損害、家族の精神的損害
- ⑤ 障害が残った場合の介護の費用
- ⑥ 障害が残った場合の労働能力の低下の損害
- ⑦ 死亡の場合のその後の賃金損失
- ⑧ 死亡の場合の葬祭料
ウ 「一般的に」の意味
本問は「一般的に」と言っている。これは何を意味するのであろうか。常識的には2つのことが考えられる。
ひとつは、損失を重みとした加重平均で、労災補償給付とその他の費用・損害の大きさを比較するという趣旨であり、もうひとつは、すべての被災者のうち補償費給付よりもその他の費用・損害が高い者の方が「一般的」だという意味である。
これは、出題者の意図は、おそらく後者の意味だったのではなかろうか。損失を重みづけとした加重平均と考えると、得られる数値はひとつだけであるから、「一般的に」という言葉は意味をなさなくなると思われるからだ。
(2)労災補償給付される範囲
ア 会社側の損害への給付はない
さて、次に労災補償給付される範囲を検討しよう。これは、法令によって明確であり、形式的には曖昧な部分はない。まず、会社側の損害・費用に対する補償が行われないことは当然である。
イ 本人の損害への給付は一部のみ
次に本人の損害であるが、これは次のようになる。これらのうち、年金の額を“補償給付”として考慮するかどうかは、民事賠償訴訟では問題となってきたが、問題では特に限定されていないので考慮すると考えよう。
- ① 医療費 原則として全額
- ② 入院のための付き添い 条件に合致すれば給付
- ③ 休業による賃金 休業4日目から平均賃金の8割
- ④ 本人や関係者の精神的損害 補償されない
- ⑤ 障害が残った場合の介護の費用 上限付きで給付
- ⑥ 障害が残った場合の労働能力の低下の損害 年金及び一時金の形で一定額を給付
- ⑦ 死亡の場合のその後の賃金損失 遺族年金または一時金の形で一定額を支給
- ⑧ 死亡の場合の葬祭料 一定額を給付
※ 休業補償給付は平均賃金の6割であるが、さらに2割の特別支給金が支給される。民事訴訟では、賠償の額を考える場合に、特別支給金は損益相殺(民法第536条第2項参照)の対象とはされないが、これも補償としての位置づけであるから8割と考えよう。
(3)労災保険の補償給付とその他の費用・損失の比較
では、以上の条件の下で、労災保険の補償給付とその他の費用・損失について、どちらが大きいか、場合を分けて比較を試みよう。
ア 救急箱災害
救急箱災害については、そもそも労災補償が行われない。従って、その他の費用・損害の方が大きいことは当然である。
また、その数は把握しようもないが、ハインリヒの法則を考えれば、新規に療養を受ける者の数よりも圧倒的に多いと考えるべきであろう。
イ 不休災害及び休業3日以内の災害
次に療養(医療機関での治療)が行われる不休災害及び休業3日以内の災害で障害が残らない場合はどうであろうか。このような場合、民事賠償の訴訟になることはまずないであろうから、精神的損害の大きさは分からない。ただ、休業補償給付が行われないのであるから、常識的に考えて費用・損害の方が大きいのではなかろうか。
本人の休業による賃金(不休災害の場合でも治療のため半日程度の休業が行われた可能性はあろう)、上司等の医療機関への同行、(行われるとして)災害の調査や労基署への報告に要する費用を考えれば、補償給される療養補償給付(治療代)を上回ると考えるのが自然であろう。
なお、この被災者数は、労災保険給付のうち新規要療養者数(新規受給者数にほぼ等しい)から新規休業補償給付者数(死傷病報告による休業4日以上死傷者数と大きくは乖離していない)を減じれば算定できる。これらの正確な数値は公表されていないが、新規要療養者数を新規受給者数(60万人程度)とし、新規休業補償給付者数を死傷病報告による休業4日以上死傷者数(10万人程度)と等しいと考えると、ほぼ50万人程度となる。
ウ 休業4日以上の災害(障害が残らない場合)
休業4日以上の災害で障害が残らない場合はどうであろうか。この場合は、療養補償は100%給付され、休業補償給付も平均賃金の8割であることを考えれば、労災補償給付の方が大きいかもしれない。近年の医療費は高額化しており、会社が支出する経費などよりはるかに高いことも考えられる。
しかし、会社側のコストの大きさも分からないし、補償されない精神的損害については金額に相場などがあるわけではない。不明というべきであろう。
エ 障害が残る災害及び死亡災害
障害が残った場合や、死亡の場合はどうであろうか。この場合は精神的損害の金額が高額になるだろうから、その他の費用・損害の方が大きいと思われる。しかし、このような重篤な災害については、労災補償給付も充実しており、障害が残った場合の医療費や介護費用を考慮すると、その他の費用・損害の方が大きいという明確な証拠はないというべきではなかろうか。
3 結論
このように考えると、ハインリヒの法則によれば、救急箱災害の件数と休業3日までの被災者の、全被災者に占める割合は、ほとんどだと言ってよいであろうから、ほとんどの被災者は労災補償給付よりも実際の損害・費用の方が大きく、本肢は正しいのではなかろうか。
だが、以上のような推計による結論は、常識的には本問の趣旨とは異なっているであろう。やはり、出題者の保有している根拠となるデータを探し出さない限り、正誤は不明というしかない。
やはり、この問題は、国家試験の問題としてきわめて不適切なものであり出題ミスというべきであろう。