問14 特定化学物質を取り扱う作業場において、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すべき事項として、特定化学物質障害予防規則上、誤っているものはどれか。
(1)特定化学物質の名称
(2)特定化学物質を含むものの成分及びその含有量
(3)特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
(4)特定化学物質の取扱い上の注意事項
(5)特別管理物質を取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場を除く。)において使用すべき保護具
※ 本問は、その後の法令改正に合わせて一部修正した。
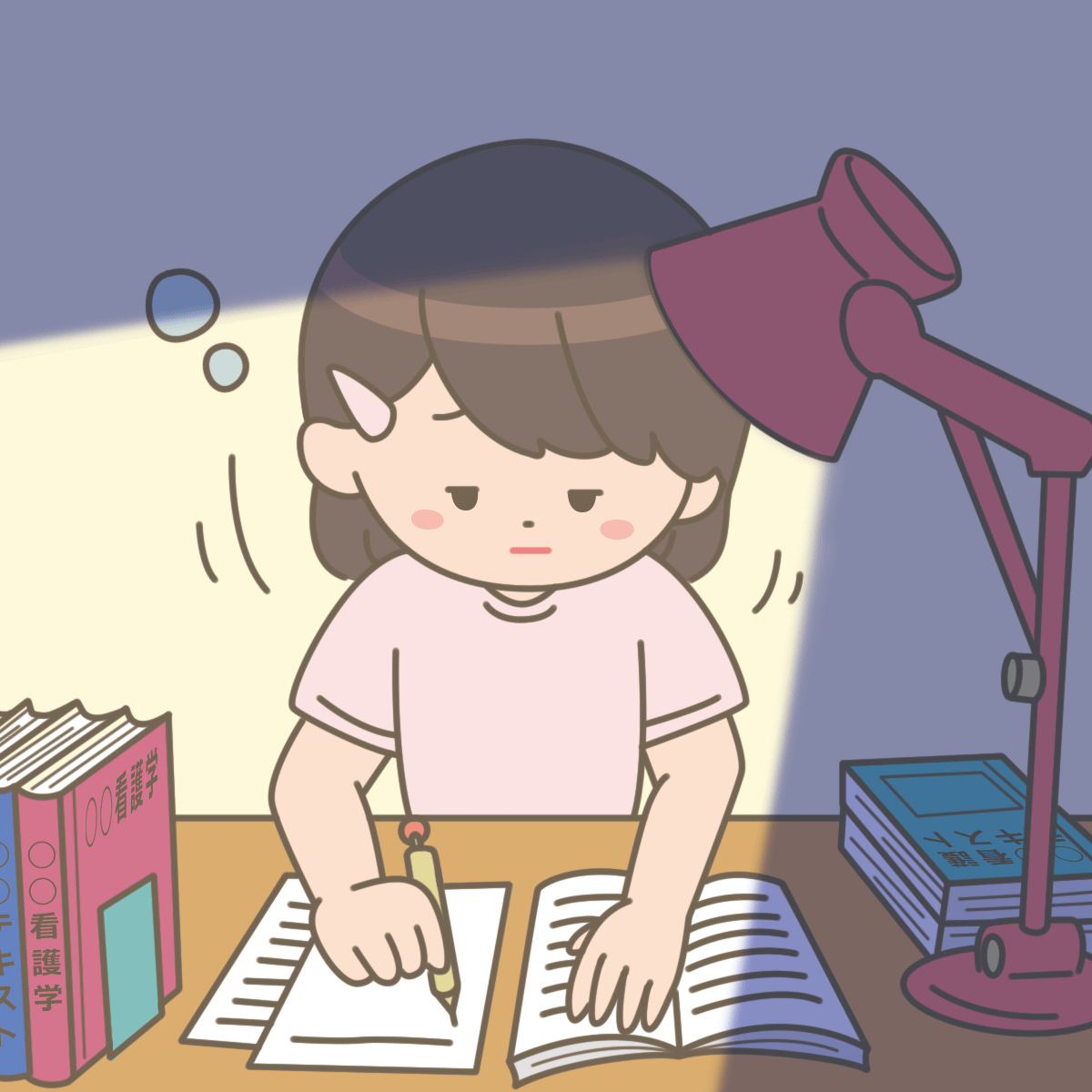
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2012年度(平成24年度) | 問14 | 難易度 | 特別管理物質に関するやや詳細な知識問題。実務経験がないと難問か。合否を分けるレベルだろう。 |
|---|---|---|---|
| 特別管理物質 | 4 |
問14 特定化学物質を取り扱う作業場において、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すべき事項として、特定化学物質障害予防規則上、誤っているものはどれか。
(1)特定化学物質の名称
(2)特定化学物質を含むものの成分及びその含有量
(3)特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
(4)特定化学物質の取扱い上の注意事項
(5)特別管理物質を取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場を除く。)において使用すべき保護具
※ 本問は、その後の法令改正に合わせて一部修正した。
(2)
【解説】
本問の掲示すべき事項は、特化則第 38 条の3に定められている。従って、条文を覚えていればそれによって解答すればよい。
【特定化学物質障害予防規則】
(掲示)
第38条の3 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 特定化学物質の名称
二 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
三 特定化学物質の取扱い上の注意事項
四 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具
五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
イ~ル (略)
(作業の記録)
第38条の4 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。)において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
一~三 (略)
※ 本問は出題当時は下記のように、特別管理物質に関するものであった。その後の法令改正に合わせて修正したものである。
問14 特別管理物質を取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場を除く。)において、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すべき事項として、特定化学物質障害予防規則上、誤っているものはどれか。
(1)特別管理物質の名称
(2)特別管理物質の成分及びその含有量
(3)特別管理物質の人体に及ぼす作用
(4)特別管理物質の取扱い上の注意事項
(5)使用すべき保護具
※ 特化則第 38 条の4等は出題当時は下記のように、特別管理物質に関するものであった。現在は 2023 年 10 月1日施行の改正(施行通達)により、上記のように修正されている。
(掲示)
第38条の3 事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 特別管理物質の名称
二 特別管理物質の人体に及ぼす作用
三 特別管理物質の取扱い上の注意事項
四 使用すべき保護具
(作業の記録)
第38条の4 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。
一~三 (略)
(1)正しい。特化則第 38 条の3(第一号)により、特定化学物質の名称は、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
(2)誤り。特定化学物質を含むものの成分及びその含有量は、特化則第 38 条の3に定められていない。
(3)正しい。特化則第 38 条の3(第二号)により、特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状は、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
(4)正しい。特化則第 38 条の3(第三号)により、特定化学物質の取扱い上の注意事項は、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
(5)正しい。特化則第 38 条の3(第四号)により、特別管理物質を取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場を除く。)において使用すべき保護具は、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
【条文を覚えていない場合にどう解くかのヒント】
オリジナルの問題について、条文を覚えていない場合の解き方を考えよう。
条文を覚えていなければ、掲示の必要性(労働者が知るべき事項かどうか)を判断して解答することとなる。
まず、(4)の取扱い上の注意事項と(5)の使用すべき保護具については、これを知らなければ、ばく露防止対策を採ることができない。当然に必要である。
次に、(3)の人体に及ぼす作用も必要である。それが分かった方が、なぜばく露防止対策をとるべきなのかが理解できるし、仮に病気になった場合に、それが原因だと気付けば対応を採れるからである。
問題は、(1)の名称と(2)の成分及び含有量である。これらは、労働者が自分の取扱っているものの有害性などを調べたいと思ったときに必要になるだろう。場合によっては、自らが病気になった場合に原因を知るためにも必要である。
ただ、「名称」と「成分及び含有量」は、双方とも有用ではあるが、そのいずれかが分かっていればよいだろう。ところで(旧)特化則第38条の3の特別管理物質の定義を詳細に読めばわかるが、特別管理物質という用語は混合物を含むのである。しかし、そこに含まれている純物質である特別管理物質が分かれば含有量まで知る必要はないだろう。
また、「成分及び含有量」としてしまうと、特別管理物質以外の成分も含まれてしまう。そのように考えると、どちらかを外すとすれば「成分及び含有量」ではないかと見当がつくのではないだろうか(※)。
※ 現在では、安衛法第 57 条(及び安衛則第 33 条)の表示義務(取り扱う労働者が知るべきこと)から、「成分及びその含有量」が除かれていることもヒントになるであろう。
従って、条文を知らなくても(2)が誤りではないかと見当は付けられるのではないだろうか。








