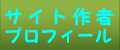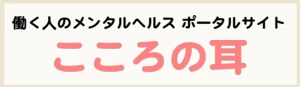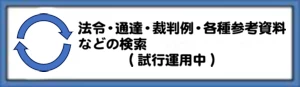産業保健担当が知っておくべき、安衛法違反についての「故意」についてわかりやすく説明しています。
罪を犯したというには、本人に「故意」または「過失」があることが必要ですが、安衛法は「過失犯」を処罰しないので、犯罪が成立するためには「故意」が必要となります。
本稿では、事業場における労働災害防止のために、何をしなければならないかという観点から「故意」とは何かについて解説しています。
- 1 背景事情
- (1)問題の所在
- (2)何も知ろうとしなければ違反は問われないのか
- (3)何も知ろうとしなかった場合の不利益は
- 2 規制対象についての誤解と故意
- (1)ある物質が法規制の対象にならないと思っていた場合
- (2)ある物質が法令名とは別の物質名で表示されていた場合
- (3)ある物質を別な物質だと思っていた場合
- (4)その他の評価の誤解
- 3 最後に
1 背景事情
執筆日時:
最終改訂:
(1)問題の所在
労働省に入省した頃、労働安全衛生法(安衛法)の違反について、先輩職員から次のような話を聞いたことがある。
【安衛法と処罰】
- 安衛法は、故意犯のみを処罰するので、労働安全衛生についてまったく何もしない事業者は、処罰することができず、ある程度、安全衛生活動に熱心な事業者でないと処罰できない。
- 安衛法は、安全衛生に熱心なほど違反を問われやすいのだ。
その先輩職員は、安衛法のこのような“問題点”を指摘され、その矛盾を実務において解決するのが、労働基準行政の第一線の職員の技術力であるといわれるのである。確かに、私が都道府県労働局に勤務していた頃、この先輩が指摘されたような問題点について、企業の側の方からも、やや皮肉をこめて指摘されたことがよくあった。
これはどういうことだろうか。この問いに答えるためには、刑法における故意について簡単に説明しておかなければならない。
刑法では犯罪の成立要件の一つである故意について、第38条において次のように定めている。
【刑法】
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
すなわち、刑法第38条第1項は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」として、故意のない行為は罪とならないと定めている(※)。なお、但書にある特別の規定とは、簡単に言えば“過失”のことである。過失犯を処罰するには、過失犯を処罰するという特別の規定がなければならない。しかし、安衛法には過失犯を処罰するという規定はない。
※ 大学で法律を修めた方でないと、刑法第38条第1項の「罰しない」という規定について、「罪にはなるが処罰はしない」という意味(処罰阻却事由)だと誤解されることがあるが、そうではない。故意のない行為は原則として犯罪に当たらないのである。
ここで、“故意”とは、簡単に言えば、“わざと”ということなのだが、法律学的にごく簡単に説明すると、事実関係を“認識”し、その結果を“認容”することだと理解されている。例えば、殺人の故意があるというためには、自分が行おうとしている行為が人を殺すということだということを理解した上で、かつ相手に死んで欲しい、あるいは死んでも構わないと思う必要がある。
ハンターが、山中で川辺にいた動物を猿だと思って射殺したところ、実はそれはハイカーだったという場合、いくら猿とハイカーを見間違うはずがないような状況だったとしても、これを殺人罪に問うことはできない。せいぜい、業務上過失致死罪になるだけのことである。なぜなら、このハンターは人を殺すという事実関係を認識していないし、そもそも人を殺してもよいとも思っていないからである。
労働安全衛生の実務では、どのようになるだろうか。今、ある労働者が高所作業をしていて開口部から墜落して死亡したとしよう。そして、責任者は、仕事を労働者に任せており、そこに開口部があることなどまったく知らなかったとしよう。この場合、安衛法違反を問うことはかなり難しい。
たしかに、理論上は、高所での作業をさせていた以上、開口部があるかもしれないとは認識していただろう。その状況で、具体的に開口部の有無を調べず、対策をとるための手立て(※)をとっていなかったのだから、“開口部はあるかもしれないし、労働者に墜落の危険が及んでは困るが、多少の危険があることはやむを得ない”という意味での故意(未必の故意)が存在するという“理屈”は立つかもしれない。
※ 開口部の確認、開口部の墜落防止措置を採るための施設・材料等の準備、さらには予算措置など
しかし、現実の司法実務においては、具体的に“その開口部”が存在していることと、“その周辺で労働者が作業する可能性”などを、事業者が明確に認識していなければ、故意があるとすることは難しいのである。
一方、責任者が、安全衛生対策をある程度は実施していたという場合はどうだろうか。作業場所の安全性の確認を行い、危険な開口部には墜落防止のためのてすりなどを設ける措置をとったとしよう。ところが、通路のうち一か所だけ、てすりを設けることが物理的に難しい場所があったとしよう。ところが、そこは恒常的に作業を行う場所ではなく、1日に数回程度しか通らない場所だからという理由で、労働者に一応の注意だけは与えて、墜落防止措置はとらなかったとしよう。
そして、まさにその場所から労働者が墜落したとする(※1))。この場合は、安衛法違反を問うことができる可能性が強い。その責任者は、高所に開口部があり労働者に墜落の危険があることを認識していたにもかかわらず、“墜落防止のための措置を採らないこと”を認識し、かつ認容もしている(※2))からである。
※1 もちろん、墜落しなくても、墜落の危険があれば安衛法違反となる。
※2 当然のことながら墜落することまで認容していなくても安衛法違反は成立する。安衛法が禁止しているの(構成要件)は、墜落防止措置をとらないことであるから、墜落防止措置をとらないということを認容していれば“故意”は成立するのである。
実は、このような問題は、安衛法のみならず、少なくない法定犯(※)についていえることではある。
※ 国が法違反になると定めたから犯罪になる行為のこと。殺人罪などのそれ自体が悪である自然犯との対比で用いられる用語である。もっとも、法定犯と自然犯の区別はそれほど明確なものではない。労働者の労働災害防止措置をとらないことも、それ自体が悪であるともいえるのである。
(2)何も知ろうとしなければ違反は問われないのか
そうなると、事業者は労働災害防止について、何も知ろうとしなければ法違反に問われることはないということなのであろうか。もちろん、そうではない。
一定の業務については、作業主任者を選任することが義務づけられており、その作業主任者に一定の業務を行わせなければならないこととされている。有機溶剤を使用させておきながら、有機溶剤を使っていたとは知りませんでしたでは、通らないのである。
すなわち、有機溶剤を使用させておきながら、作業主任者を選任していなければ、未選任の違反となるし、作業主任者に必要な業務を行わせていなければ、これも違反となるのである。
では、使用しているものが有機溶剤であることすら知らなかったらどうなるだろうか。それについては後述する。
また、50人以上の事業場では、衛生管理者や産業医を選任しなければならないこととなっている。彼らに、一定の業務を行わせなければならない以上、何も知りませんでしたでは済まないのである。
(3)何も知ろうとしなかった場合の不利益は
また、労働災害発生のリスクについて何も知ろうとせず、結果的に安衛法違反の状態となっていれば、労働基準監督官(監督官)による臨検監督が入れば、是正勧告を受けることになる。そのときになって、改善は大変だから、改善はするが、十分な余裕を設けてくれと言ったとしても、そもそも事業者は違反を犯さずに事業の遂行を行っていなければならなかったのである。それをしていなかったのだから、改善まであまり猶予は設けてくれなくても文句は言えない。
しかも監督官としても、猶予期間中に災害が発生するようなことになれば、責任問題にもなる。ある程度の危険な状況では改善するまで仕事をするなと命じられることもある。
事前に法令を遵守していれば、計画的にできただろうが、いきなり監督官がやってきて、短期間に改善をしろと言われるのだから、事業の遂行に支障をきたすこともあるのだ。
だからといって、是正勧告を受けてもそれを放置するようなら、悪質と判断されて、送検されることもあり得るだろう。
知らなければ良いなどというものではないのである。
また、実際に事故が発生したときに、安全配慮義務違反で民事賠償請求を受けることもあり得る。これについての詳細は当サイトの「労働災害が発生したときの責任:民事賠償編」を参照して頂きたい。
その他にも災害が発生すれば、様々な不利益を被ることとなる。それは、本サイトの「作業保健担当者のための法律学入門」の記事にゆずるので、そちらを参照して頂きたい。
2 規制対象についての誤解と故意
(1)ある物質が法規制の対象にならないと思っていた場合
ところで、ある化学物質を使用するときに、それが規制対象のものではないと思っていたときに“故意”は成立するだろうか。
例えば、リスクアセスメントには罰則はないが、容器又は包装への表示には罰則がある。もし、通知対象物を譲渡・提供するときに、政府の化学物質の情報提供サイト検索し、(サイトに情報がないか又は誤っていたために(※)その物質は通知対象物ではないと考えて、表示をしなかった場合に、罰則の適用はあるだろうか?
※ 政府のサイトには誤りがないなどというつもりはない。
この点、すなわち、罪を犯す意思がなければ罰せられないのであるから、この場合も罪にはならないのではないかと思われるかもしれない。しかしながら、この場合には、(まず間違いなく)故意はあるとされるだろう。法律用語を使わせて頂ければ、「法律の錯誤」にすぎないからである。
問題は、刑法第38条の第3項なのである。ここには「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と書かれている。
そして、この場合は、事業者はその物質が何かについては、認識しているのである。それが、規制対象となっていることは知らなくても、その物質であることは知っており、かつその物質に表示をせずに譲渡又は提供するという認識もあるのである。
たんに、その物質が法の適用になるということを知らなかったにすぎないのである。従って、これは法律の錯誤(3項)にすぎず(※)、故意に欠けるところはないのである。
※ 要するに規制がかかっていることを知らなかっただけなのである。
(2)ある物質が法令名とは別の物質名で表示されていた場合
次に、その化学物質が別な企業から購入したもので、その化学物質に付されていた名称がA物質とされていたが、安衛令別表第9では同じ物質がB物質と表記されていたとしよう。
ところが、事業者は、別表第9の物質名と異なっていたので別な物質だと思ったとしよう。そして、そのために、ラベル表示をせずに、譲渡又は提供をしたとしよう。
この場合、1項の「罪を犯す意思がない」行為にあたる(無罪)のか、法律を知らなかっただけ(有罪)なのか、どちらにあたるであろうか。
これについても、3項の法律の錯誤になる。というのは、安衛令で規制をかけているのは、AとかBとか呼ばれている、その物質についてなのである。すなわち、その物質を表す表記の方法として“B物質”と書いてあるにすぎないのである。
事業者は、A物質だと思っていたのであるから、その物質であると思っていたわけである。すなわち、故意に欠けることはなく、たんに法律を誤読していたにすぎないのである。
わかりやすくいえば、本名がAさんである俳優が、芸名でBを名乗っていたとしよう。Aさんの幼馴染で、Aさんが俳優だということを知らない甲さんが、Aさんをみて“Aさんだ”と思ったとすれば、それはAさんをAさんと思っているのであるから誤解はない。
一方、俳優としてのAさんしかしらない乙さんが、Aさんのことを“Bさんだ”と思ったとしてもそこにも誤解はない。AさんとBさんは同一人物であって、別な人ではないからである。
いささか、話が専門的になるが、これについては有名な判例がある。刑法の一般的な教科書に必ず書いてある、「むささび・もま事件」といわれる判例がそれである。
この事件では、被告人(上告人)は、その地方で“もま”と呼ばれる動物を捕獲したのである。ところが、法によって“むささび”を捕獲することは禁止されており、被告人が“もま”だと思っていた動物は、実は“むささび”だったので法違反を問われたという事件である。
被告人は、自分は“もま”が“むささび”だとは知らなかったのだから、故意がなく無罪であると主張した。この事件は最高裁まで争われたが、最高裁は被告人この主張を認めなかった。
その理由は、次のようなことである。すなわち、その地方で“もま”と呼ばれる動物は、法律が捕獲を禁止している“むささび”のことであり、被告人がその動物を“もま”であると認識してその動物を捕獲した以上、故意に欠けることはないというのである。
従って、別表第9には“ブテン”と書いてあるが、自分が譲渡又は提供する物質は“α-ブチレン”だと思っていたから故意がないと主張しても、意味はないということである。
(3)ある物質を別な物質だと思っていた場合
次に、ある通知対象物を、通知対象物ではない別な物質だと思っていたような場合を考えてみよう。
この場合は、故意はないこととなるのである。すなわち、ある通知対象物ではない別な物質だと思っていたのであるから、通知対象物を表示をせずに譲渡又は提供するという事実関係を認識していないからである。
こちらは事実の錯誤に当たるのである。これは、刑法の教科書に必ず書かれている「たぬき・むじな事件」といわれるケースと同じことなのである。
刑法の教科書には「むささび。もま事件」と「たぬき・むじな」事件は、刑法総論の教科書にはセットで記載されている。
この事件では、被告人は“むじな”が巣穴に入っているのを見つけ、これを捕獲しようとして、巣穴を塞いで“むじな”が出られないようにし、翌日、猟犬にこれを咬み殺させたのである。ところが、被告人が“むじな”だと思っていた動物は、実は“たぬき”だったのである。
そして、巣穴を塞いだ日は、狩猟法でタヌキを捕獲することは禁止されていなかったが、猟犬に咬み殺させた日は禁止されていたため、狩猟法違反で起訴されたのである。
この事件では争点はいくつかあったが、そのうちのひとつは、“むじな”を捕えようという意図で“たぬき”を捕獲したことが、事実の錯誤(無罪)なのか法律の錯誤(有罪)なのかである。
これについて最高裁は次のように判断した。“むじな”と“たぬき”は別な動物であると認識されている。従って、“むじな”を捕えるつもりで“たぬき”を捕えたことは、事実の錯誤にあたるので、故意は成立しない(無罪)としたのである。
さきほどの例でいえば、Aさんは俳優のBさんとは別人だったということである。甲さんは俳優のBさんを見て、Aさんだと思ったとしたら、これは人違いである。すなわち、そこに錯誤が認められるわけである。
従って、通知対象物を、通知対象物とは別な物質であると誤解して、それを譲渡又は提供するときに表示をしなかったとしても、故意がなく、安衛法違反は成立しないこととなる。
(4)その他の評価の誤解
ア 化学的な解釈についての誤解
また、ある通知対象物の水和物を譲渡提供する際に、水和物は通知対象物ではないと考えて表示をしなかったような場合はどうなるだろうか。
政府の公式な見解では、ある物質が通知対象物なら、その水和物も通知対象物であるとされている。これは、たんなる法的な解釈というより化学的な判断というべきであろう。水和物の中には通知対象物が含まれており、加熱することによって水和水は失われるからである。
この場合は、故意に気けるところはないと判断される可能性が高いのではないかと思う。
ただ、本件のようなケースでは、現実の取り扱いとしては、罪にはなるが情状を酌量されて起訴されない(起訴猶予)可能性もないわけではない。ただ、そこは検察官の判断しだい(起訴便宜主義)であり、状況にもよろう。
イ 法律的な解釈の誤解
ところで、法律の解釈を誤り、その結論について誤解した場合について、故意がないとした判例がある。最2小判昭26・8・17(毀棄窃盗被告事件)がその例であるが、この事件も刑法学においてきわめて有名な判決である。
この事件では、被告人が、ある犬を撲殺したのである。この犬が他人のものであれば器物損壊罪に当たるが、無主の犬であれば罪には当たらない。そして、その犬は他人の飼い犬だったが、鑑札を付けていなかった。
被告人は、その犬が他人の飼い犬だったことは知っていたが、鑑札を付けていない犬は、法律上、無主の犬であるとみなされると誤解していたのである。実際には、鑑札を付けていないからといって、法律上、無主の犬であるとみなされたりはしない。
これが事実の錯誤なのか、法律の錯誤なのかが争われたのである。最高裁は被告人の主張を認めて、原判決を破棄して高裁に差し戻した。
その理由として、判決文は、「鑑札をつけていない犬はたとい他人の飼犬であつても直ちに無主犬と看做されるものと誤信していたというのであるから、本件は被告人において右錯誤の結果判示の犬が他人所有に属する事実について認識を欠いていたものと認むべき場合であつたかも知れない」というのである。
つまりは法律的な評価の結果について、買主のいる犬と無主の犬とを誤解していたのであるから、法律的な事実の錯誤であると評価したわけである。
そうすると、ある化学物質について、法律的な解釈を誤って、法律の規制の対象とはならないと解釈していたとすると、違反は問えないということになるだろう。ただ、これは境界事例であって、現実にそのような事件が起きた場合、実務における判断でも違反にならないとされるかどうかは、かなり微妙であると考えた方がよい。
ウ 行政職員による誤った処分による誤解
また、行政の組織や職員が誤った説明をしたり、誤った処分をしたりしたために、法によって禁止されている行為を、許されると誤解した場合はどうなるだろうか。これについて、最3小判平元.7.18(公衆浴場法違反事件)がその例であるといえよう。
この事件では、Dが特殊公衆浴場の営業許可を受けていたのだが、そのDの実子が代表者を務める会社が、Dの特殊公衆浴場の営業を引き継いで行おうとして、営業許可の「変更届」を知事に提出したのである。
本来、そのような変更届は受理されるべきではないし、受理されたとしても会社に対する営業許可が出されたことにはならない。ところが、知事はこの変更届を受理してしまう。そのため、この会社は営業許可を受けたと誤解して、特殊公衆浴場の営業を行ったのである。
これにより公衆浴場法違反を問われたのであるが、1審では無罪、控訴審では有罪となったが、最高裁は「被告人には「無許可」営業の故意が認められない」として、これを無罪とした。
これは、知事の側(県の職員)にも問題のあるケースである。これも下級審の判断が分かれており、境界事例である。実際に、監督署がある化学物質について誤った解釈を事業者に示したために、事業者が違反をしていたというケースが発生したとしても、これが法違反にならないとされるかどうかは、かなり微妙なところだというべきであろう。
3 最後に
本稿では、安衛法における故意の問題について解説してきたが、基本的に、安衛法の内容を熟知してその遵守を図ることは事業主の責務である。
しかしながら、安衛法は、関連する政省令を含めると、膨大な量になり、解釈通達の類になると、行政の職員でさえその存在を知らないものがあるというのが実態である。
ただ、行政の職員やそのOBの強みは、法令を調べたり、通達を調べたりするノウハウを有していることである。とりわけ現職の職員は、これまで発出されたすべての通達にアクセスするシステムを用いることができるのである。
また、行政職員は、一般の方には難解に思えるような法令や通達を読みこなす能力も身に着けている。事業者の方も、法令の解釈について困ったときは、行政組織に相談をされるとよい。また、行政組織の敷居が高ければ、行政OBの社会保険労務士などに相談をされるとよいと思う。
なお、本稿では、化学物質を規制する法違反について、故意についての解釈をお示ししているが、CSRの観点からも法違反の状態になることは避けなければならない。事業場で用いている化学物質が規制対象になるかどうかの確認は、確実に行っていただきたい。